夫が亡くなった場合、家は誰のものに?相続の流れとトラブル回避のポイント
 1. 夫が死亡したら家を相続するのは誰?
1. 夫が死亡したら家を相続するのは誰?
夫(住宅ローン契約者)が亡くなった場合、返済中の自宅やその相続について、妻や子どもはどうなるのかが心配になることがあります。以下では、自宅の相続に関する基礎知識を解説します。
1-1. 法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた故人(被相続人)の財産を相続できる人のことです。被相続人の配偶者は、法律上の婚姻関係が成立している場合に限り、常に法定相続人となります。一方、事実婚の配偶者や元配偶者は、法定相続人として認められません。相続人には「配偶者」以外に「血族」が含まれ、それぞれの範囲と順位が次のように定められています。
- 配偶者
被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。 - 血族相続人(順位付き)
- 第1順位: 子ども(すでに亡くなっている場合は孫が代襲相続)
- 第2順位: 父母(両親がいない場合は祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(すでに亡くなっている場合は甥姪が代襲相続。ただし再代襲はなし)
これにより、たとえ配偶者が存命であっても、血族相続人がいる場合には、遺産の分割が必要となります。
続く部分で、実際に家がどう分割されるかを解説します。
1-2. 家は配偶者や子どもが相続するのが一般的
夫(住宅ローン契約者)が亡くなった場合、家族は「この家に住み続けられるのか」と心配するかもしれません。
一般的には、 配偶者や子どもが家を相続 することが多く、以下のような理由が挙げられます:
- 生活の安定:現在住んでいる家に引き続き住むことで、家族が平穏な生活を維持できる。
- 相続税の特例:被相続人が住んでいた宅地に関する税負担を軽減する「小規模宅地等の特例」が適用される。
これらの理由から、相続手続きが円滑に進めば、妻や子どもが家を引き継ぎ、これまで通り生活を続けることが可能です。
注意点:住宅ローンの返済
ただし、住宅ローンが残っている場合、その返済が問題になることがあります。たとえば、 団体信用生命保険(団信)が適用されていれば、ローンの残債は保険で完済されるケースが多いですが、適用されない場合は相続人が負担する可能性があります。この点については次章で詳しく解説します。
2. 夫が死亡したら、返済中の住宅ローンはどうなる?
住宅ローン契約者である夫が死亡した場合、ローンの残債の扱いは団体信用生命保険(団信)の有無によって異なります。
2-1. 団体信用生命保険に加入していた場合
団体信用生命保険(団信) は、契約者の死亡や高度障害発生時に住宅ローン残債を保険で完済する保険制度です。
- 団信加入時の対応
契約者が亡くなった場合、団信が適用されればローンの残債が免除され、遺族に返済義務はありません。
必要な手続き- 金融機関への連絡
- 必要書類の提出
- 保険会社の審査・承認
- 法務局への抵当権抹消登記手続き
- 返済が免除されない場合
- ローン返済を延滞していた場合
延滞により団信契約が失効する可能性があります。 - 共同ローンの場合
- 連帯保証:主債務者の返済は免除されますが、連帯保証人には返済義務があります。
- ペアローン:夫婦それぞれが契約したローン分はそれぞれの団信で管理され、妻のローンは引き継がれます。
- 親子リレーローン:子が団信加入者の場合、親の死亡では返済免除が適用されません。
- ローン返済を延滞していた場合
2-2. 団体信用生命保険に未加入だった場合
団信未加入の場合、ローンの残債は遺族に引き継がれます。妻や子どもが返済できない場合には、他の対応を検討する必要があります。
2-3. 住宅ローンの残債が支払えない場合
ローン残債の返済が難しい場合、以下の対応を検討します。
- 金融機関への条件変更の相談
- 返済スケジュールを延長することで毎月の返済額を軽減。
- 総返済額が増えるデメリットがあります。
- ローン借り換えを検討する
- 金利の低いローンに変更して返済負担を減少。
- 条件により、手続きコスト(40万~50万円程度)がかかります。
- 家を売却する
- 残債より高く売却できればローン完済可能。
- 信用情報に傷がつく前に売却を進め、住み替え先の選択肢を確保。
住宅ローンが支払えない場合でも、適切な対策を取れば家を失わずに済むケースもあります。金融機関や専門家への早期相談が大切です。
3. 夫の死亡後、家の相続税はどうなる?
夫が死亡した場合、その家を相続することにより相続税が発生する可能性があります。以下で相続税の計算方法や、配偶者に適用される軽減措置について解説します。
3-1. 相続税の計算方法
相続税の計算は以下のステップで行います。
- 基礎控除額を算出
- 計算式
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 - 例)妻と子ども2人が相続人の場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 計算式
- 課税遺産総額を算出
- 計算式
課税遺産総額=正味の遺産額-基礎控除額 - 例)正味の遺産額が2億円の場合
課税遺産総額=2億円-4,800万円=1億5,200万円
- 計算式
- 法定相続分どおりの取得金額を算出
- 法定相続分:妻1/2、子ども各1/4
- 例)課税遺産総額1億5,200万円の場合
- 妻:7,600万円
- 子ども:3,800万円(各)
- 相続税の速算表で税額を計算
- 妻:30%×7,600万円-700万円=1,580万円
- 子ども:20%×3,800万円-200万円=560万円(各)
- 合計:1,580万円+560万円×2=2,700万円
- 実際の相続割合で按分
- 妻1/2、子ども各1/4の場合
- 妻:2,700万円×1/2=1,350万円
- 子ども:2,700万円×1/4=675万円(各)
- 妻1/2、子ども各1/4の場合
3-2. 配偶者に適用される税額軽減措置
配偶者が相続する財産については、次の条件を満たせば相続税が軽減されます。
- 配偶者が取得する財産が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額を超えない場合、相続税が免除されます。
例)上記のケースでは、妻が1/2を相続しても法定相続分相当額以内のため、妻の納税額は0円になります。
3-3. 子どもにかかる相続税
配偶者に適用される軽減措置が子どもには適用されないため、子どもはそれぞれ675万円の相続税を納める必要があります。
相続税の計算は基礎控除額や速算表に基づきますが、配偶者には軽減措置があるため、妻の納税義務はゼロとなるケースがほとんどです。一方、子どもには相続税が発生します。相続税の計算や申告に不安がある場合、早めに税理士に相談することをお勧めします。
4. 夫の死後の不動産相続|よくあるトラブルと解決法
夫が亡くなった後の不動産相続では、スムーズに進むケースもあれば、トラブルになることもあります。以下では、具体的なトラブル事例と解決策について解説します。
4-1. 自宅を3人で平等に分割して相続したい
遺産の中で最も高額な自宅を、法定相続人(例:妻と子ども2人)で平等に分割したい場合、主な方法は次の3つです。
- 共有分割
不動産を共有名義にする方法。3人で平等に分けることが可能ですが、売却や改築の際に全員の同意が必要となるため、後々トラブルの原因になることがあります。 - 代償分割
妻が不動産を相続し、子ども2人に代償金を支払う方法。この場合、妻に十分な資力がないと実行が難しい点に注意が必要です。 - 換価分割
不動産を売却して現金化し、その金額を平等に分配する方法。現金での分配は公平ですが、住まいを失うデメリットがあります。
おすすめの方法
共有分割はトラブルを招きやすいため、代償分割または換価分割が望ましいです。ただし、代償金の支払い能力や家を手放したくない意向がある場合は慎重に検討しましょう。
4-2. 不動産の相続人が代償金を払えない
妻が不動産を取得し、子どもたちに代償金を支払う予定でも、一括で支払う余裕がないケースも考えられます。その場合の解決策は以下の通りです。
- 分割払いの提案
代償金を月々や年単位で分割して支払う案を提示します。相続人全員の合意が必要です。 - 自宅の売却
分割払いが認められない、もしくは支払えない場合には、自宅を売却して得た現金を分配する方法があります。ただし、住まいを失うデメリットが伴います。
注意点
家を売却する場合は、できるだけ高値で売れるように不動産の一括査定サービスを利用するなど、計画的に進めましょう。
4-3. 不動産の評価方法で意見が合わない
不動産の代償分割をする際、家の評価額を巡ってトラブルになることがあります。不動産の評価方法には以下があります:
- 実勢価格(取引価格)
実際に売買される価格。市場の動向に左右されます。 - 地価公示価格
公的に発表される標準価格。実勢価格より低いことが一般的です。 - 路線価
税務署が発表する価格。相続税の計算基準となります。 - 固定資産税評価額
固定資産税の課税基準。これも実勢価格より低い傾向があります。
解決策
- 双方の主張する価格の平均をとる。
- 不動産鑑定士に依頼して適正な価額を算出する(費用:10万~50万円程度)。
鑑定費用を節約したい場合は、価額についてお互いが妥協することも検討しましょう。
不動産相続では、共有分割は後々のトラブルを招く可能性が高いため、代償分割や換価分割を検討しましょう。代償金の支払いが難しい場合は分割払いの提案や売却を検討することが重要です。評価額のトラブルは妥協や専門家の意見を取り入れることで解決可能です。トラブルを未然に防ぐため、相続の際には専門家への相談をおすすめします。
5. 夫の死後の不動産相続|手続きの流れ
故人(夫)の財産を相続するには、必要な書類を揃えて一連の手続きを進める必要があります。以下に、不動産を含む遺産相続の手続きの流れを解説します。
1. 夫の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などを取得する
故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を揃えることで、相続人を特定する準備をします。戸籍謄本は、市区町村役場で取得できます。
2. 遺言の有無を確認する
遺言書がある場合、その内容が優先されます。遺言書があれば家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です(公正証書遺言は除く)。遺言書がない場合は、法定相続人が協議して遺産分割を決めます。
3. 遺産の額や内訳を確認する
不動産、預貯金、有価証券、債務(借金)など、故人の財産の詳細を調査します。不動産については、固定資産税通知書や登記事項証明書で確認することが一般的です。
4. 法定相続人は誰なのか確認する
戸籍謄本を基に、故人の配偶者や血族相続人(子ども、父母、兄弟姉妹など)を特定します。漏れがあると手続きがやり直しになるため、慎重に確認しましょう。
5. 法定相続人全員で話し合う
法定相続人全員で遺産分割協議を行います。誰がどの財産を相続するのかを合意する必要があります。この協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
6. 遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立したら、その内容を明記した「遺産分割協議書」を作成します。協議書には、相続人全員が署名・実印で押印します。
7. 登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する
不動産の権利関係を確認するため、法務局で登記事項証明書を取得します。
8. 固定資産評価証明書を取得する
相続税の計算や登記手続きに必要となるため、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得します。
9. 相続登記を申請して名義変更する
不動産を取得する相続人の名義に変更するため、法務局に相続登記を申請します。2024年4月1日から相続登記は義務化されており、手続きを怠ると過料が科される可能性があります。
10. 相続税の申告・納付をする
相続税が発生する場合は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付を行う必要があります。期限を過ぎると延滞税が発生するため注意が必要です。
相続手続きは複雑で、書類の準備や手続きが煩雑になりがちです。特に不動産相続では、名義変更や税務申告に必要な書類が多いため、相続手続きを円滑に進めるには早めの準備が肝心です。不明点があれば、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
夫(住宅ローン契約者)が死亡した場合、夫が団体信用生命保険(団信)に加入していれば、妻や子どもに住宅ローン残債の返済義務はなく、自宅に住み続けることが可能です。
一方、団信に未加入で返済義務が発生する場合や、ローンの組み方によって返済が困難になる場合には、金融機関に条件変更を相談したり、家を売却するなどの対処法を検討する必要があります。
また、家を相続する際には相続人同士の協議や不動産評価額の算定方法などでトラブルが発生することもあります。今回ご紹介した手続きの流れやポイントを参考に、スムーズに相続手続きを進めてください。不安がある場合は専門家への相談も検討しましょう。
関連記事はこちら
- 相続手続きの代行~費用相場や専門家選びのポイントを解説~
- 遺留分侵害額請求とは?改正で変わった内容や手続きのポイントを徹底解説
- 離婚した親の相続について徹底解説
- 遺産分割協議書の作成後に「騙された」と気付いた場合どうなる?
- 仲の良い兄弟でも争いが起こることもある――よくある相続トラブルの事例とその予防策
- 負の遺産がある場合の相続対策:相続人が取るべき行動とは?
- よく聞く代襲相続って? トラブルに関する事例や予防法を解説
- 軍用地の相続方法や手続き~重要なポイントを弁護士が解説~
- 相続の話はどう切り出すべき?事例を交えてご紹介
- 土地と現金を相続する際の分け方とは?遺産分割の方法と手続きの流れを解説
- よくある不動産登記トラブル3選
- 相続不動産の名義変更を成功させるには?費用や必要書類を徹底ガイド
- 養子縁組の相続トラブル5選:対策を解説します
- 家の名義変更って?これだけは知っておくべき知識8つを紹介!
- 遺産相続トラブルを防ぐ!調停・審判・訴訟の違いと弁護士活用のポイント
- 故人との同居の有無が「争続」の火種?!もめやすいケースと対処法を弁護士が解説
- 預金相続の手続き方法を徹底解説!
- 遺産に車があった場合はどのような手続きが必要?弁護士が解説します!
- 絶縁状態の兄弟姉妹との相続トラブル対処法
- 遺産に畑や山林がある!農家の相続を簡単に解説
- 遺産分割協議書を作成した後に「騙された」と気づいた場合、取り消しは可能?
- 子どもがいない夫婦の相続人は誰になるのか?注意点や対処法を弁護士が解説
- 不動産の名義変更は相続でどうする?必要な手続きや費用、注意点を解説
- 子どもがいない夫婦の相続ルールと注意点を解説
- 親が認知症になった場合の相続トラブルと対策について
- 株式相続の手続きとは? ~分割方法や評価額のポイントを徹底解説~
- 配偶者の連れ子に相続権はない!遺産相続の方法と対策
- 遺言書は全て有効?無効になるケースや注意点を解説!
- 「死後離婚」したい…相続に影響する?
- 息子の嫁に相続させたい!もめないための対処法を弁護士が解説
- 代償分割とは?代償金の決め方や相続税の計算方法について解説
- 弁護士が解説!お墓の管理と相続でトラブルを防ぐ2つのポイント
- 婿養子はどちらの財産も相続可能!妻の両親と実両親の相続分を徹底解説
- 一人だけに財産を渡してもいいの?遺言書作成の注意点や対策などを解説
- 「遺産隠し」されているかも…どうしたらいい?
- 遺言書の書き方は??要件や注意点を弁護士がわかりやすく解説
- 相続手続き、自分でやる?専門家に頼る?迷ったときの判断基準
- 不動産相続の分割方法から登記手続の必要書類まで解説
- 連れ子がいる場合の相続はどうなる?
- 借金は相続しなければならないのか?相続を回避するための手続きと注意点
- 遺言で赤の他人に財産を譲る方法と注意点
- 相続が発生!債務の支払いは?控除できる費用を解説
- 長男が先に亡くなっている場合、相続はどうなる?
- 子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみ?よくあるトラブルと対処法を弁護士が解説!
- 相続人で海外在住の場合、遺産分割協議書の作成はどうなる?
- 遺産相続で「がめつい」相続人とのトラブルが発生した場合の対処法は?
- 土地の相続放棄ができないケースとは?相続後に選べる対応策も解説
- 兄弟の子が相続人に?知っておきたい代襲相続のポイント
- 連帯保証人は相続放棄できない?
- 申述書の書き方と提出のポイントを徹底解説
- 親の借金を相続放棄できないケースとは?対策とポイント
- 実家の相続放棄おける重要なポイント
- 疎遠な相続人がいるときの遺産分割のポイント
- 土地の相続放棄は兄弟一人でも可能?
- 海外在住の相続人がいる時の相続手続きは?注意点を弁護士が解説
- 相続放棄の費用について徹底解説!
- 海外在住の相続人がいる場合の相続手続きで知っておくべき注意点
- 相続放棄は弁護士に相談を!
- 兄弟姉妹が亡くなった時の相続と注意点について解説!
- 独身の方が亡くなった場合の相続権は誰になる?
- 相続放棄はどの専門家に相談する?
- 妻が亡くなった時の夫の遺産相続:知っておくべきポイントと手続き
- 兄弟姉妹の相続と遺留分の関係について解説
- いとこの財産は相続できる?注意点は?
- 不動産が必要ない時は相続放棄できる?注意点を弁護士が解説
- 続放棄後も空き家の管理義務は続く?【2023年改正】知っておきたい対策と対応策
- 子どもがいない夫婦の相続人は誰になる?
- 銀行預金の相続手続きに期限はある?必要な手続きとポイントを弁護士が解説
- 遺産相続で起こりがちな10のトラブル|生前にできる解決策も徹底解説
- 自動車も相続手続が必要?手続の流れとケース別必要書類を解説
- 兄弟姉妹に遺留分が認められない理由と遺産を受け取る手段
- 株式の名義変更について 手続きや照会方法について弁護士が解説
- 不動産の相続手続きは自分でできる?手続きの流れと専門家に相談すべきケースを解説
- 遺産相続に必要な手続きと期限について解説!
- 配偶者がいない場合の相続はどうなる?
- 一人っ子相続で注意すべきポイントを弁護士が解説!
- 土地や不動産の相続放棄は可能?
- 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎた場合の対処法!!
- 現金を相続したら?税金は?弁護士が解説
- 身寄りのない方が死亡したらどうなる?生前の対策はどうしたらいい?
- 相続放棄の期限は原則3ヶ月以内 起算点はいつから?
- 年金受給者が亡くなったら?相続や手続きについて弁護士が解説
- 子供がいない夫婦の相続によくあるトラブルと対処法を解説!
- 相続放棄の判断は3カ月以内に!期間が過ぎたら「上申書」で対応可能!
- 生前に相続放棄はできない!考えられる代替策とは?
- 親の借金は相続放棄で解決できる?
- 養子縁組にしても元の親の相続はできる?
- 親の介護をしない兄弟より多くの遺産を相続するには?弁護士が解決策を解説!
- 事実婚の夫・妻には相続権がない!財産を渡すための方法と対策を弁護士が徹底解説
- 相続税はいくらかかる?計算方法や注意点の解説
- 口座名義人が死亡した銀行口座はどうしたらいい?
- 破産者は遺産相続できる??注意点を弁護士が解説
- 専門家に依頼すべき相続による不動産の名義変更について
- いらない土地だけの相続放棄はできない?
- 沖縄で遺言書(自筆証書遺言)を書く時のポイントを弁護士が解説!
- 両親が離婚しても子供には相続権がある!相続分や注意点について解説
- 8/30(金)休業のお知らせ
- 生活保護を受けている人が遺産相続、相続放棄できる??
- 兄弟が親の介護をしてくれない!遺産を多く相続するための対策を弁護士が解説
- 相続放棄の3ヶ月の期限と注意点!!
- 兄弟姉妹が亡くなった時行う相続対策とは?弁護士が3つ紹介
- 家族へ相続の話を切り出しやすいタイミングと主な相続手続きの期限
- 家族信託とは
- 遺産相続の手続きの期限は??期限が切れた場合のデメリットを解説します!
- 親が亡くなったときの遺産相続の相続税とは?弁護士が解説!!
- 相続会議への掲載が始まりました
- 12月休業日・年末年始営業に関するお知らせ
- 【休業のお知らせ】9月1日はお休みです。
- 台風接近に伴う休業のお知らせ(8月2日更新)
- 遺言書作成のメリットは?相続で家族をもめさせたくない方必見です!
- 自筆証書遺言の書き方を弁護士が解説
- 休業日のお知らせ(8月30日、9月1日)
- 臨時休業日のお知らせ(6月30日)
- 皆様への感謝を込めて - 琉球法律事務所の新たな挑戦、テレビCMを公開
- 【休業日のお知らせ(4月6日~4月7日)】
- 【年末年始に伴う営業日のお知らせ】
- 休業日のお知らせ
- 弁護士兒玉竜幸入所のご挨拶
- 休業日のお知らせ
- 弁護士兒玉竜幸入所のご挨拶
- 年末年始の営業について
- 休業日のお知らせ
- Kindle書籍「キャリアとしての『国際弁護士』のススメ」発刊❗
- Youtubeイベントに登壇❗
- 在宅勤務終了のお知らせ
- 不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいとき、どうすればいいですか?
- 在宅勤務のお知らせ
- 新型コロナウィルス(CORVID-19)感染者 およびその対応についてのお知らせ
- 休業日のお知らせ
- 退職のご挨拶(秀浦)
- 7月3日(土)軍用地相続セミナーを開催します【沖縄タイムス社後援】
- 休業日のお知らせ
- 年末年始の営業について
- 台風による営業停止に関して(9月3日追記)
- 休業日のお知らせ
- 当事務所で発生した新型コロナウィルス(CORVID-19)感染者およびその対応についてのお知らせ
- 愛人や隠し子に相続する権利はあるの?
- 養子縁組の子供の相続方法
- 異母兄弟がいる場合の相続方法
- 遺言執行を代わりに行ってもらうことはできる?
- 預貯金・借金などの相続財産の調べ方
- 遺産分割調停を欠席するとどうなる?
- 父の遺産を母がひとり占めすると言ったら?
- 「葬儀」にまつわる「相続」問題について
- 「香典」と「相続」にまつわる相続トラブルについて
- 【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止対応について
- 【相続Q&A】軍用地の倍率とは?相続に関係するの?
- 【5月18日(土)開催】沖縄相続トラブル・遺言無料法律相談会

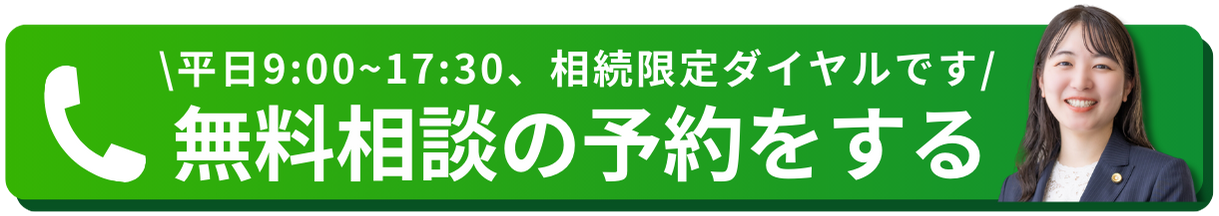
.png) 1. 夫が死亡したら家を相続するのは誰?
1. 夫が死亡したら家を相続するのは誰?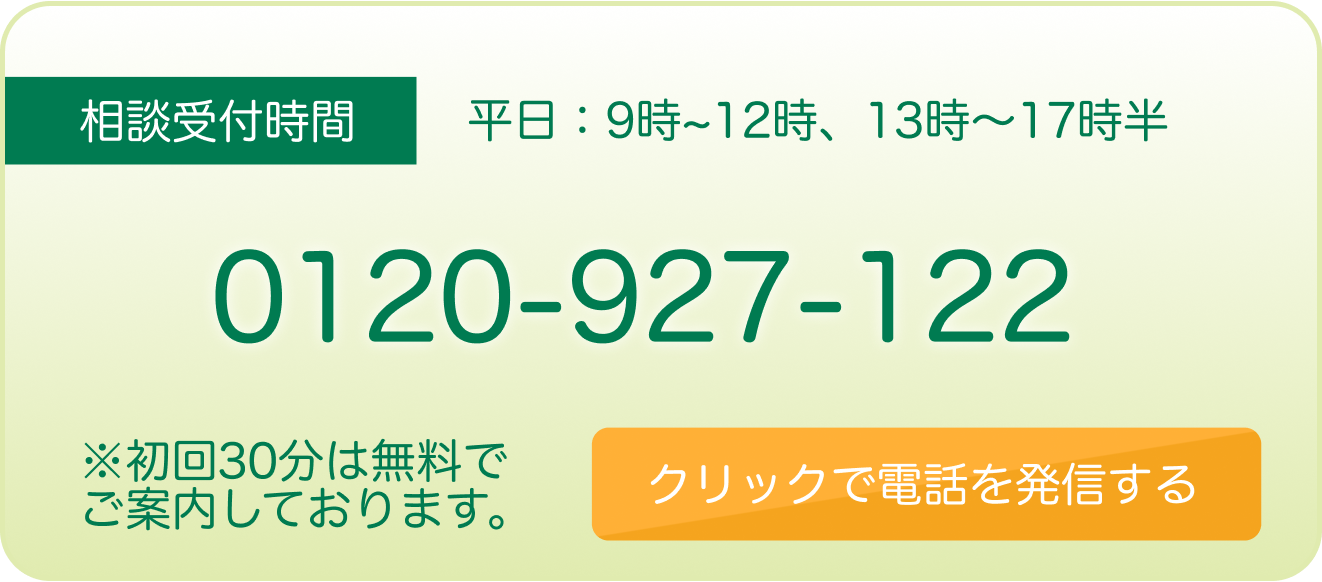
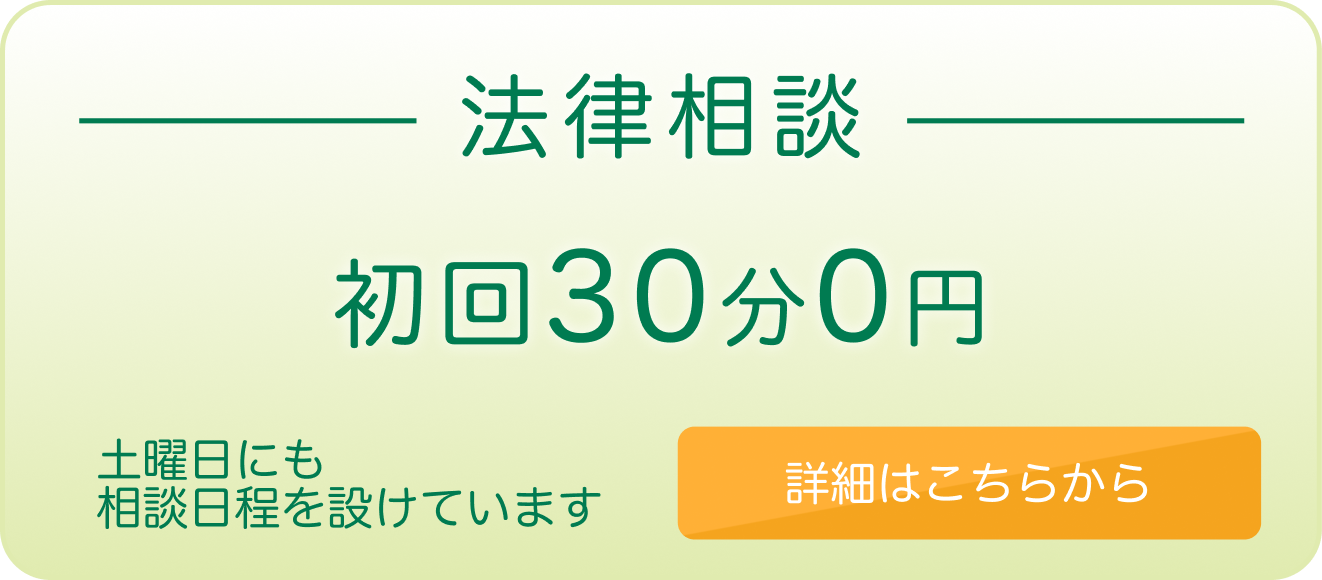
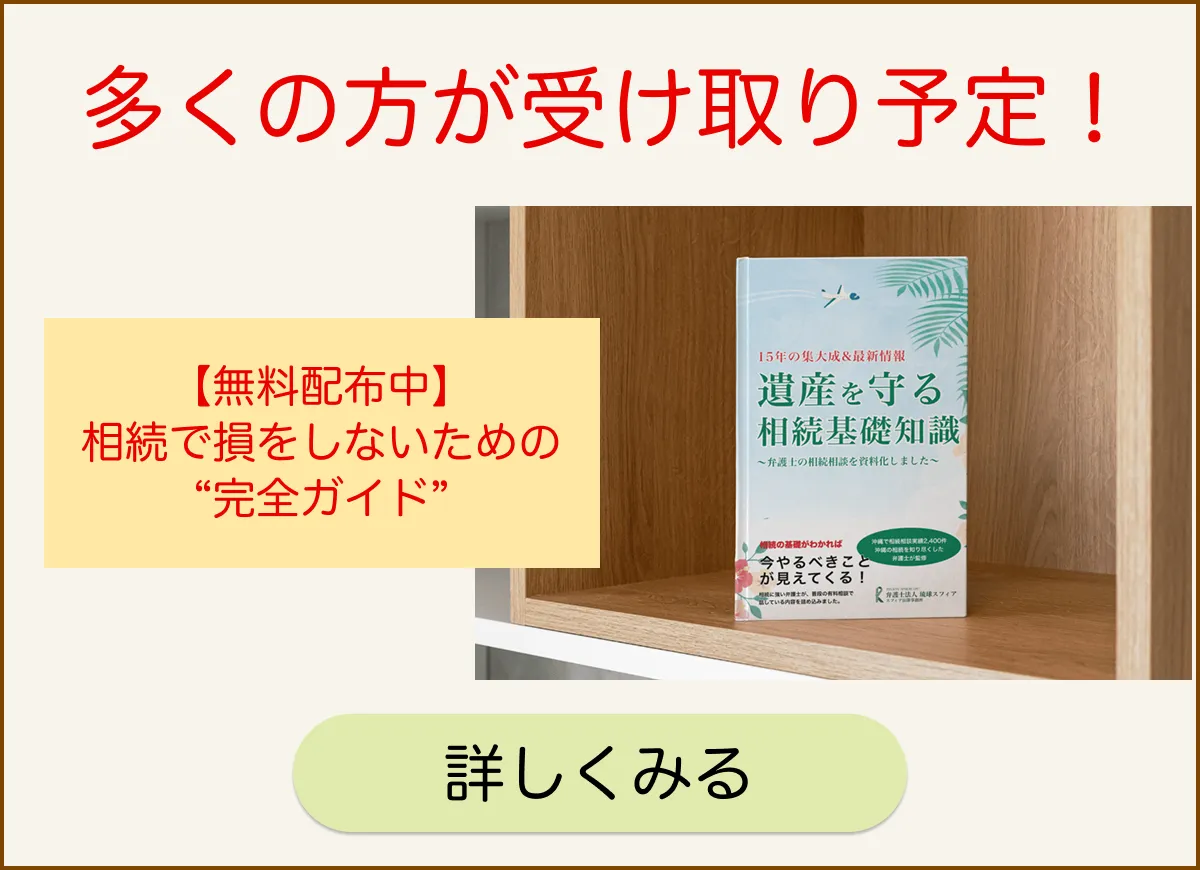
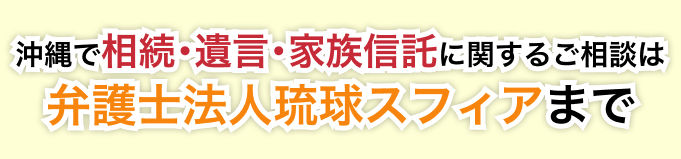

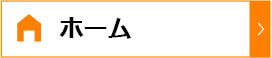
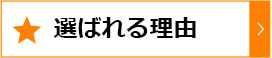
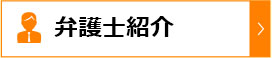
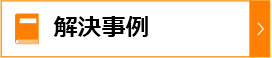
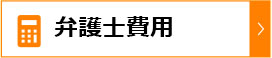
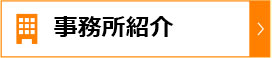

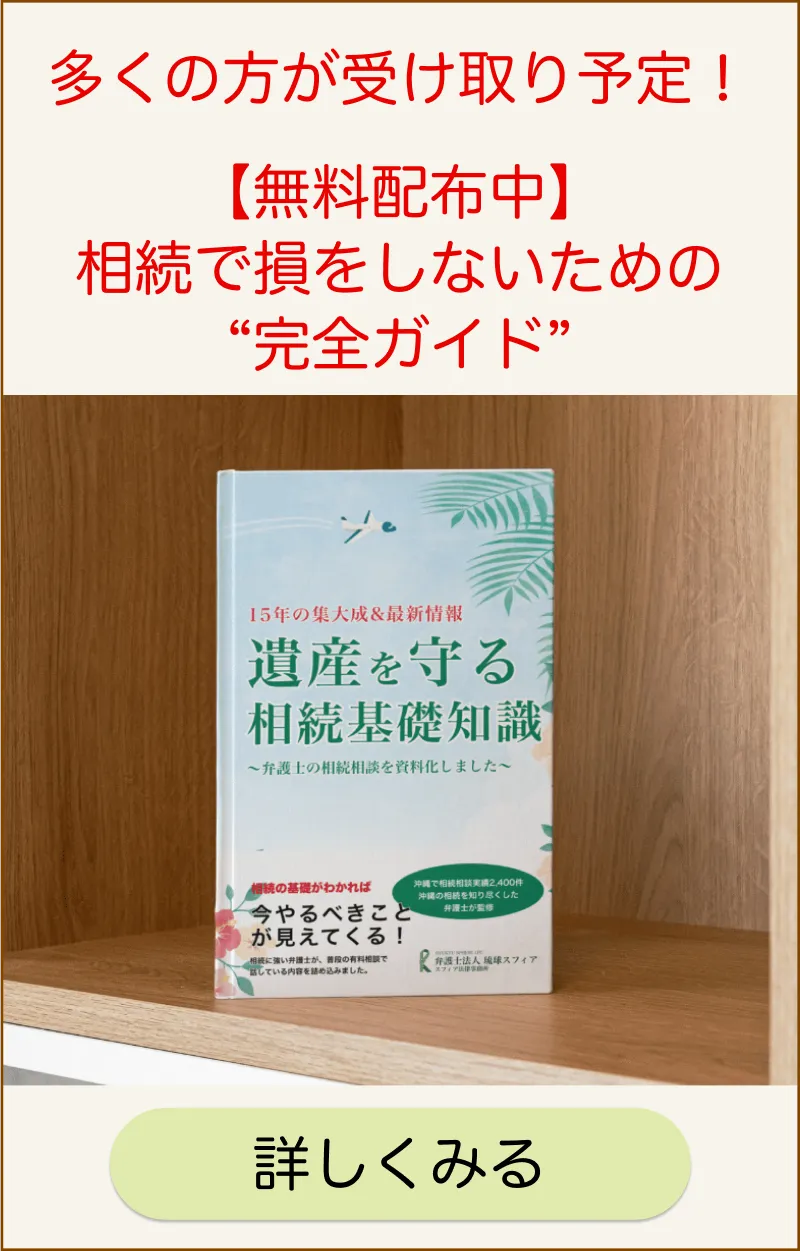

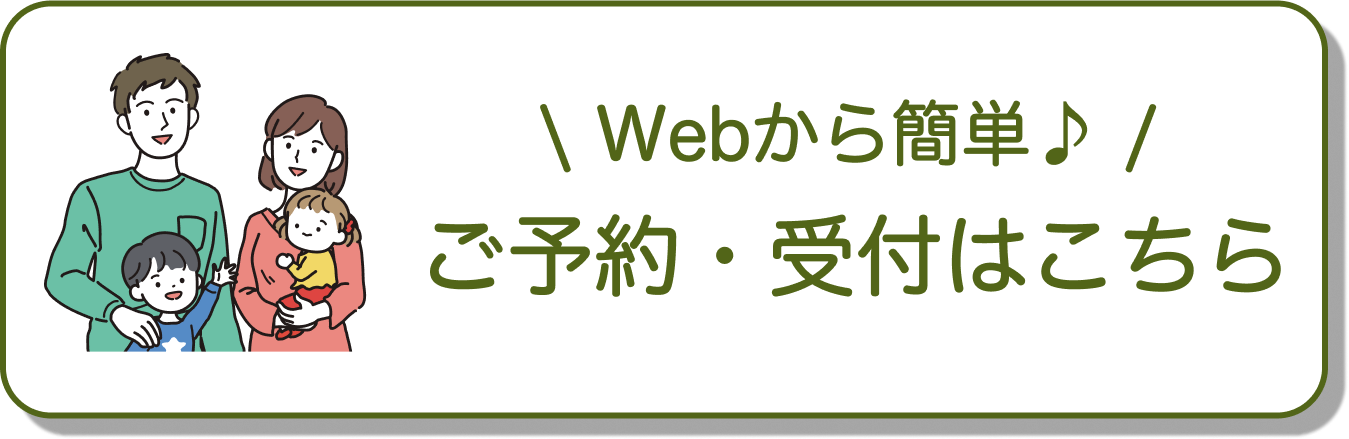


.png)
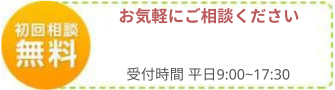
.png)