相続税はいくらかかる?計算方法や注意点の解説
1. 相続税の基礎控除とは 「相続税の非課税枠」
相続税は、遺産全体にかかるわけではなく、遺産の総額(課税価格の合計額)から「基礎控除額」を差し引いた後の金額に課税されます。遺産総額とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金や不動産など)から、マイナスの財産(借金や葬儀費用など)を差し引いた金額です。
この遺産総額から差し引けるのが「基礎控除額」で、相続税の非課税枠とも言われます。基礎控除額が大きければ、それだけ相続税の対象額が少なくなります。もし遺産総額が基礎控除額を超えない場合、相続税の申告や納税は不要です。
- 遺産総額 > 基礎控除額:相続税の申告が必要
- 遺産総額 ≦ 基礎控除額:相続税の申告は不要
まず「基礎控除額」がいくらかを確認し、遺産総額を計算した上で、それが基礎控除額を上回る場合には相続税の申告準備を進めることが重要です。
2. 相続税基礎控除額の計算方法
2-1. 基礎控除額の計算式:「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます:
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、被相続人に妻と子ども2人がいる場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は4,800万円になります。遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。しかし、遺産総額が1億円であれば、「1億円 – 4,800万円 = 5,200万円」となり、5,200万円に対して相続税が課税されます。
2-2. 相続人の数が多いほど、基礎控除が増える
相続税の基礎控除は、法定相続人の数が多いほど増加します。相続人の数を増やせる養子縁組は、相続税対策の一つとなり得ます。
2-3. 基礎控除額の法改正と影響
2015年1月1日以降、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と定められました。それ以前の基礎控除額は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」であったため、改正により課税対象者の割合が大幅に増加しています。財務省の統計によると、相続税の課税件数の割合は、2013年の4.3%から2021年には9.3%に増えています。
3. 基礎控除額の計算に必要な「法定相続人」の理解
基礎控除額を正しく計算するためには、「法定相続人」の数を正確に把握することが必要です。法定相続人は、民法に基づいて自動的に決まるもので、遺言の有無や実際に財産を相続するかどうかには関係ありません。
- 配偶者:常に法定相続人となります。
- 第1順位:被相続人の子(直系卑属)
- 第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
例えば、被相続人が妻と子を残して亡くなった場合、法定相続人は妻と子であり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。子がいない場合には、父母や兄弟姉妹が法定相続人になる可能性があります。
4. 相続税の基礎控除に関する注意点
4-1. 代襲相続の影響
法定相続人が相続開始前に死亡している場合、相続権は「代襲相続」として別の親族に移ります。例えば、被相続人の子が死亡している場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。代襲相続があると、法定相続人の数が変わるため、基礎控除額の計算に影響を及ぼします。
4-2. 養子縁組の数に制限あり
相続税対策として養子縁組を行うことが可能ですが、法定相続人として認められる養子の数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は養子1人、いない場合は養子2人までが基礎控除の対象になります。
4-3. 相続放棄の影響
相続放棄をした場合でも、基礎控除額の計算には影響しません。相続税の計算においては、相続放棄がなかったものとして計算されます。
5. 相続税に適用できるその他の控除
相続税には、基礎控除のほかにも特定の要件を満たせば適用できる控除があります。例えば、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除などがあり、税理士に相談することで最適な控除を選ぶことができます。
6. まとめ
相続税の基礎控除額を理解するためには、まず「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の計算式を覚え、遺産総額が基礎控除額を超えると相続税の申告が必要であることを理解しましょう。相続税の計算は複雑であるため、専門家への相談を検討することをおすすめします。

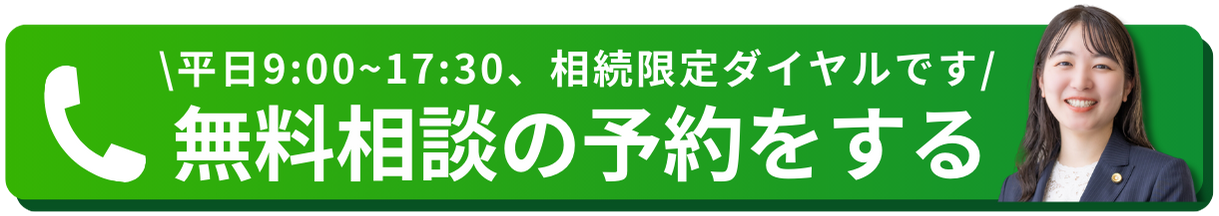
-1-1.png)
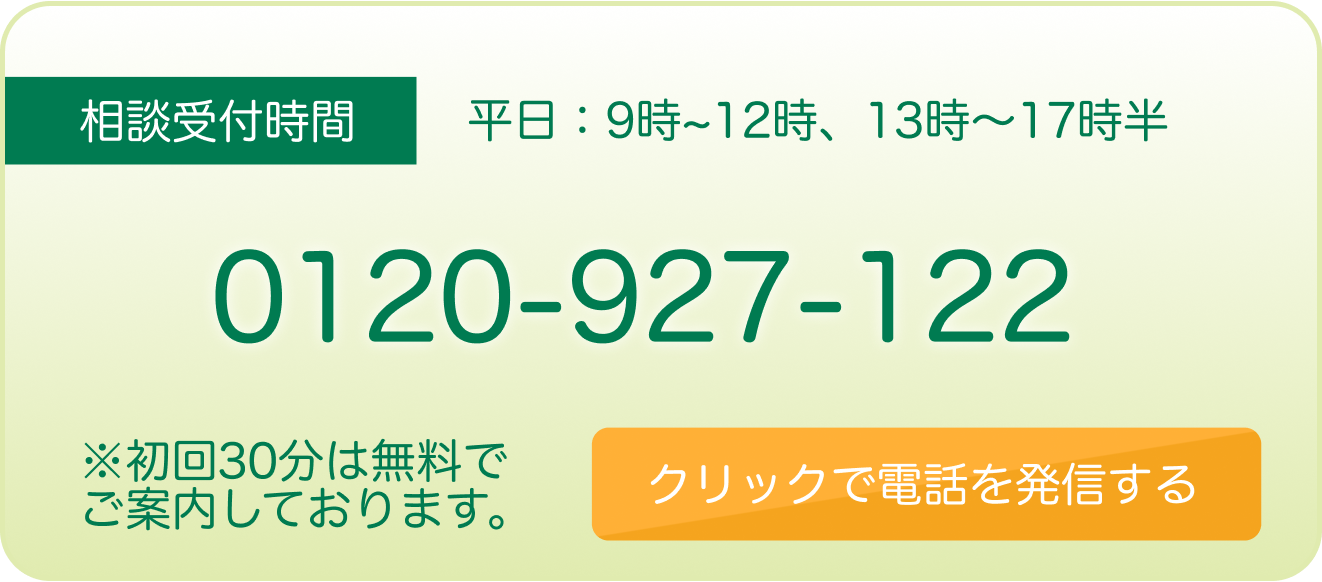
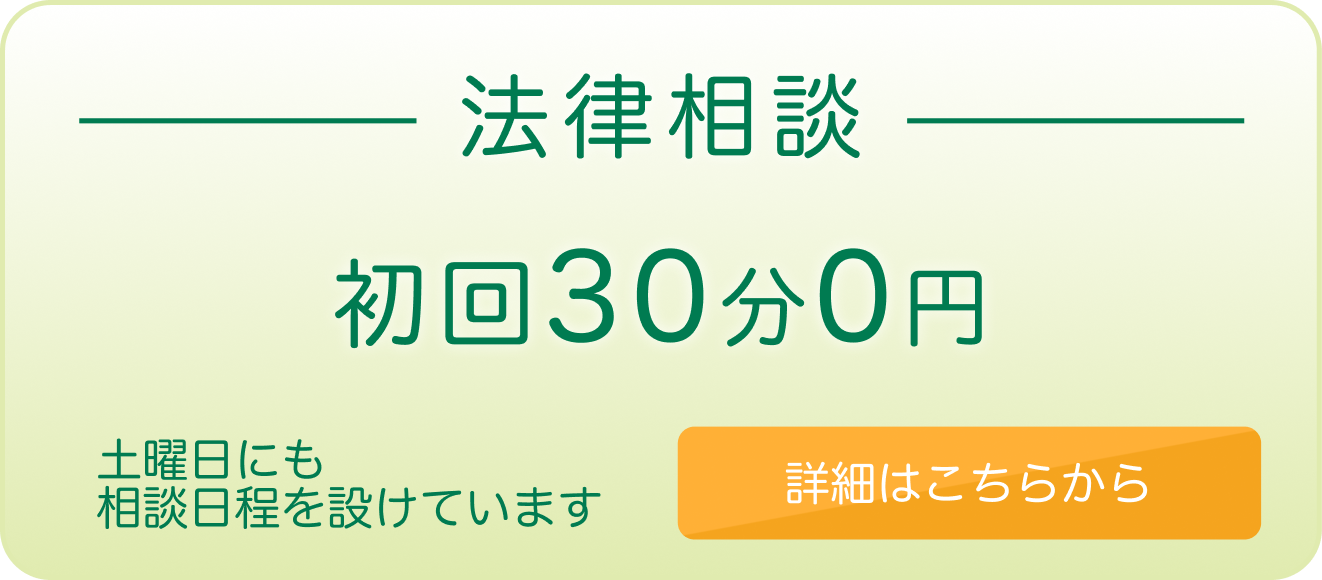
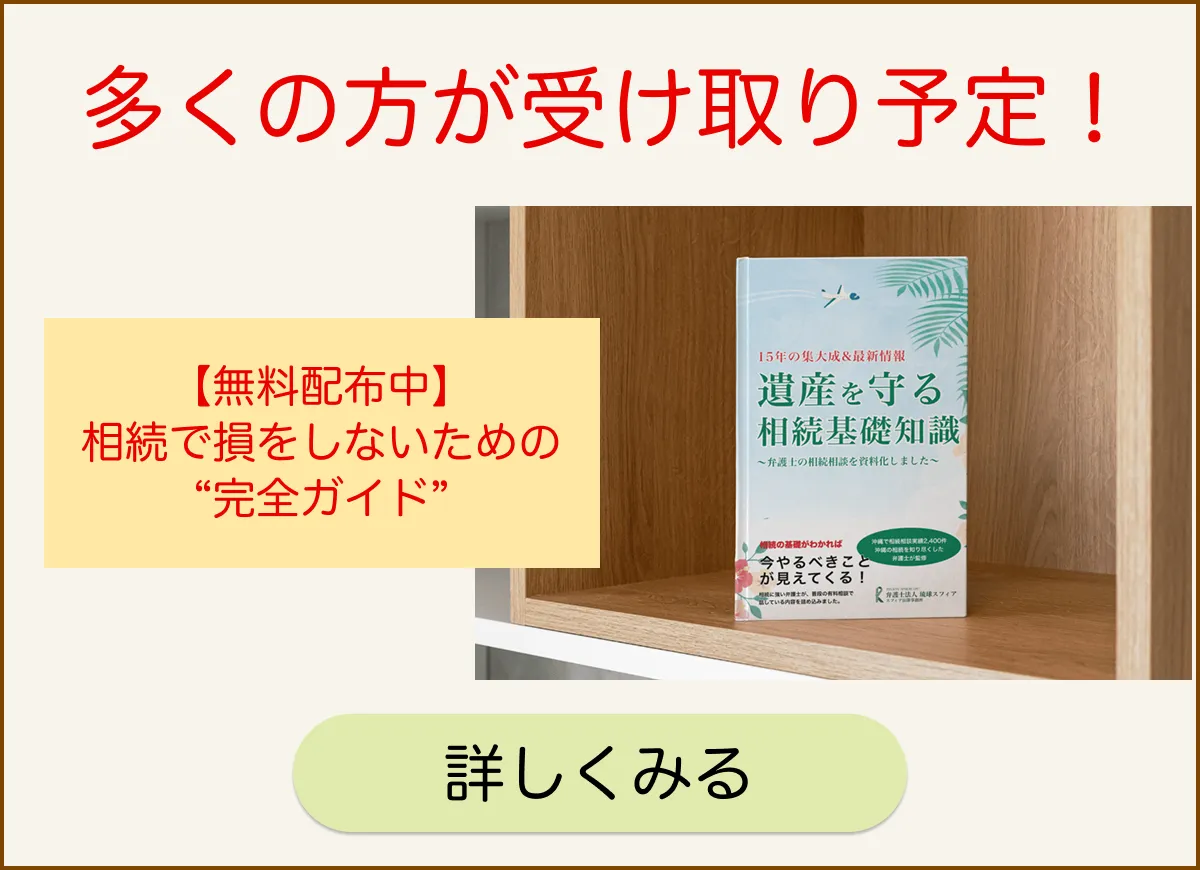
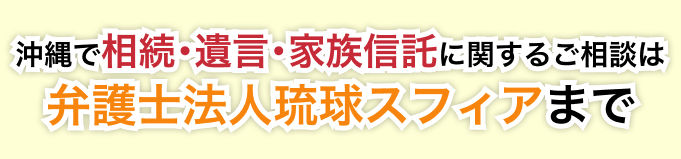

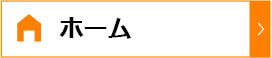
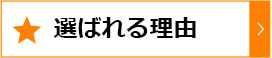
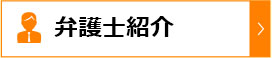
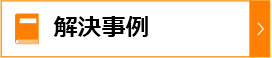
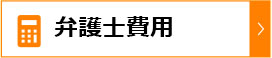
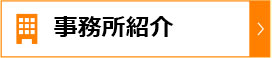

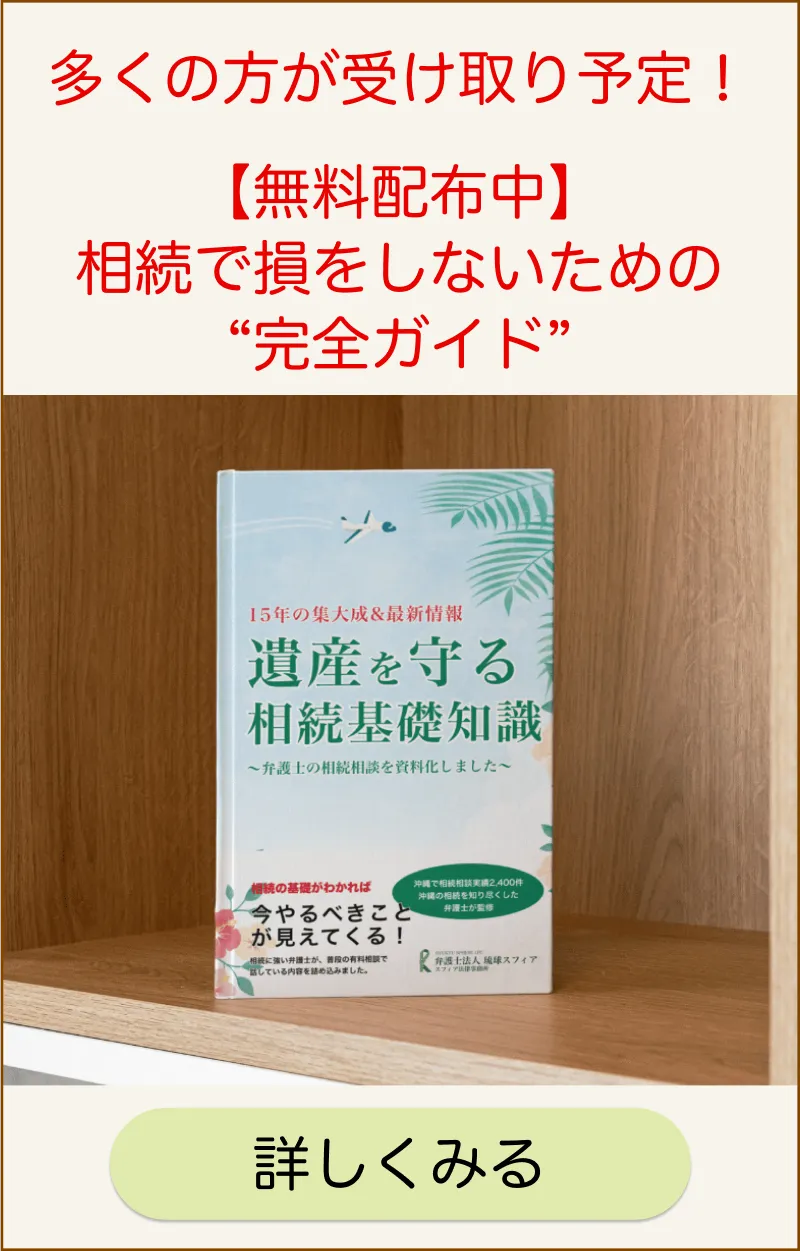

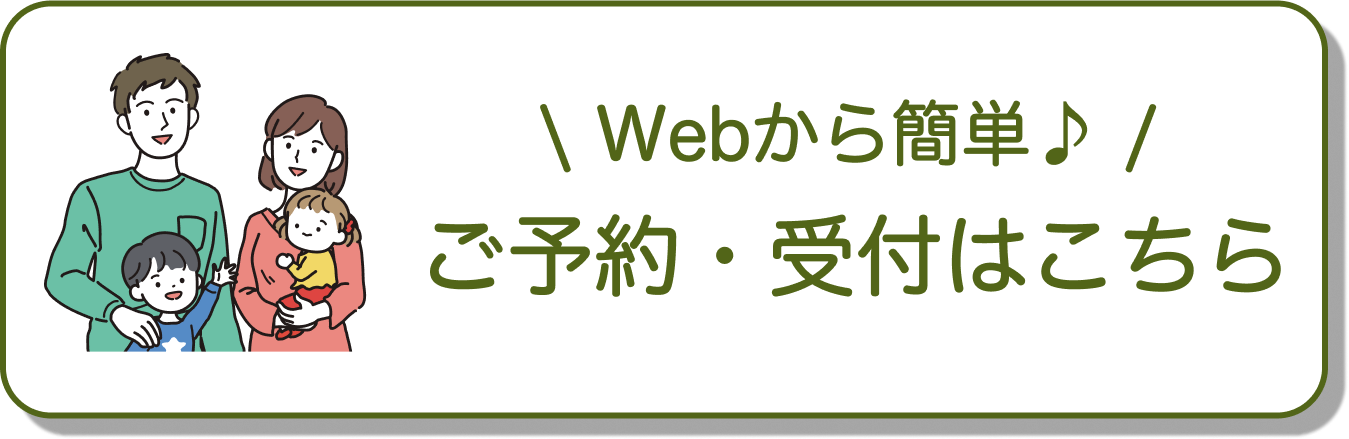


.png)
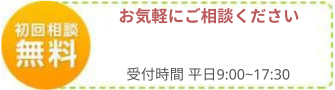
.png)