不動産の相続手続きは自分でできる?手続きの流れと専門家に相談すべきケースを解説

不動産を相続する手続き不動産を相続する場合、次のような流れで手続きを進めます。
- 遺言の有無を確認する
- 相続人を確定する
- 相続財産の把握(財産目録の作成)
- 遺産分割協議で分割方法を決定する
- 相続登記を法務局に申請する
- 相続税の申告・納付(基礎控除額を超える場合)
1-1. 遺言の有無を確認する
不動産所有者が亡くなった場合、まず遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がある場合は、基本的にその内容に従って相続手続きが進められます。したがって、他の手続きよりも先に遺言書を確認することが重要です。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を話し合います。仮に協議後に遺言書が見つかった場合でも、その内容が優先されるため、無駄な手続きを防ぐためにも早期に遺言書を見つけることが推奨されます。
1-2. 相続人を確定する
遺言書がない場合、法律で定められた範囲の親族が相続人となります。そのため、戸籍謄本を基に亡くなった方の親族関係を正確に調査し、誰が相続人であるかを確定する必要があります。後から新たな相続人が発覚した場合、遺産分割協議をやり直すことになるため、最初にしっかり確認することが重要です。
1-3. 相続財産の把握(財産目録の作成)
相続財産の内容を特定し、財産目録を作成することで、遺産分割協議がスムーズに進行します。預貯金は通帳や残高証明書を使って確認します。
不動産については、市区町村から届く固定資産税の納税通知書や権利証(登記識別情報通知・登記済証)を確認してください。また、市区町村役場で「名寄せ」という制度を利用すると、亡くなった方がその市区町村内で所有している不動産を確認できます。
さらに、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が法務局で導入され、個人が所有する全国の不動産を一覧でリストアップできるようになります。
1-4. 遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合う
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。この協議は、相続人全員の同意がなければ無効となるため、欠けることなく全員で話し合いを進めることが重要です。不動産を含む相続財産を誰が引き継ぐかが決まったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要です。これによって、協議の結果が法的に有効となり、次の手続きへ進むことができます。
1-5. 相続登記を申請する
不動産を引き継ぐ人が決まったら、その不動産の名義を相続人の名義に変更する必要があります。この手続きは「相続登記」と呼ばれ、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
なお、相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務化されます。相続登記を行わずに放置しておくと、過料が科される可能性があるため、必ず期限内に行うよう注意してください。
1-6. 相続税の申告・納付
不動産を含む遺産の総額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合、相続税が発生します。相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」となっており、この期限内に申告と納付を行う必要があります。
さまざまな手続きを行っているうちに期限が迫ることが多く、期限を過ぎると延滞税が発生する可能性もあります。できる限り早めに申告と支払いを済ませるよう心掛けましょう。
2. 相続した不動産の分け方
父が亡くなり、母(妻)と長男、長女の3人が相続人となる場合を例に、不動産の分割方法を解説します。
2-1. シンプルな現物分割
現物分割とは、不動産をそのままの形で相続人の1人が相続する方法です。たとえば、母(妻)が自宅を相続し、長男が預貯金、長女が有価証券を相続するようなケースが該当します。また、150坪の土地を50坪ずつに分筆してそれぞれが取得する方法も現物分割です。
この方法は一見シンプルですが、相続する不動産と他の財産で価値が大きく異なる場合、不公平が生じることがあります。たとえ土地を同じ面積で分けたとしても、形状や陽当たり、接道状況などで価値が変わるため、完全に公平に分割するのは難しい場合が多いです。
2-2. 不満が出にくい代償分割
代償分割とは、相続人の1人が不動産を単独で相続し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。これは、特定の相続人が他の相続人の相続分を買い取るような形になります。
たとえば、4,000万円の土地を長男が相続する代わりに、母(4分の2)と長女(4分の1)に相当する3,000万円を代償金として支払う場合です。母や長女が不動産を引き継ぐ希望がなく、代償金が正当に算出されている場合、不満が出にくい方法といえます。ただし、代償金を支払うためには、長男に十分な資力が必要です。
2-3. 不動産をお金に替える換価分割
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人で分割する方法です。
たとえば、4,000万円で不動産を売却した場合、母が2,000万円、長男と長女がそれぞれ1,000万円を受け取ることになります。現金での分割は平等に分配しやすい一方、相続人の誰かがその不動産に住んでいたり、買い手が見つかりにくい場合、売却が困難になることもあるため注意が必要です。
3. 不動産を相続するための必要書類
不動産を相続した場合は、相続登記を行う必要があります。相続登記とは、被相続人の名義となっている不動産を相続人の名義に変更する手続きです。たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続する場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請し、父親名義から自分の名義に変更する必要があります。
では、相続登記に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
相続登記には次の3つのパターンがあり、それぞれ必要書類が異なります。
- 遺言による相続登記
- 遺産分割による相続登記
- 法定相続分による相続登記
それぞれのパターンについて詳しく見ていきます。
注意:以下に記載する書類は、配偶者や子が相続人となる一般的なケースを想定しています。兄弟や姉妹が相続人になる場合や代襲相続、数次相続など、特殊な場合には追加の書類が必要となることがあります。
3-1. 遺言による相続登記の必要書類
遺言書がある場合、基本的に遺言書の内容に従って相続登記を申請します。自筆証書遺言の場合は、相続登記の前に家庭裁判所での検認が必要です。検認は、遺言書の内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐための手続きです。相続人の立ち会いのもと、家庭裁判所で開封します。公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言の場合、検認は不要です。
遺言による相続登記の特徴
遺言による相続登記は、他の方法に比べて必要な戸籍謄本の数が少なくて済みます。「遺言者の死亡」と「相続人が不動産を取得する事実」を証明する戸籍謄本のみで良いため、被相続人のすべての戸籍謄本を揃える必要はありません。不動産を取得しない相続人の戸籍謄本も不要です。
【必要書類】
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 遺言書(自筆証書遺言は検認済み、公正証書遺言はそのまま使用可能)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続登記申請書
- 不動産の登記識別情報通知(登記済証)
3-2. 遺産分割による相続登記の必要書類
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するかを決めます。協議が成立すれば、遺産分割による相続登記を行います。この場合、協議書や相続人全員の署名・実印が必要です。
必要書類:
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続登記申請書
- 不動産の登記識別情報通知(登記済証)
3-3. 法定相続分による相続登記の必要書類
遺言書がなく、遺産分割協議も行われなかった場合、または協議がまとまらなかった場合、民法に定められた法定相続分に従って相続登記を行います。この場合、不動産は相続人全員の共有状態になります。
共有不動産は、管理や処分を巡るトラブルの原因になりやすく、さらに相続が発生すると権利関係が複雑化するため、法定相続分による相続登記は慎重に検討する必要があります。
【必要書類】
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続登記申請書
- 不動産の登記識別情報通知(登記済証)
これらの書類を揃えて法務局に申請し、相続登記を完了させます。
4. 不動産の相続手続きは自分でできる?
不動産の相続手続きを自分で進めたいと考える方も多いでしょうが、実際には可能でしょうか。
4-1. 自分で必要書類をすべてそろえるのはとても大変
相続登記に必要な書類をすべて揃えるには、かなりの手間がかかります。特に戸籍謄本は、これまで本籍地の市区町村役場でしか取得できず、遠方に本籍がある場合は時間と労力がかかりました。
ただし、2024年3月からは最寄りの市区町村役場で本籍に関係なく戸籍謄本が取得できるようになり、負担が大幅に軽減されます。
とはいえ、兄弟姉妹の戸籍謄本やコンピューター化されていない古い戸籍は引き続き、本籍地の役場で取得する必要があり、郵送請求の場合は追加の手続きが必要です。記入ミスや小為替の不足で再送することになるケースもあるため、郵送請求に不慣れな方は注意が必要です。
4-2. 遺産分割協議書や登記申請書の作成にも法律の知識が必要
必要書類を集めた後、遺産分割協議書や登記申請書を作成することになりますが、これらの書類作成には法律の知識が求められます。
もし書類に誤りや不足があると、法務局から訂正や差し替えを求められるため、手続きがさらに煩雑になります。書類作成に自信がない場合は、最初から専門家に依頼する方が安心です。
4-3. 相続人同士が疎遠だったり不仲な場合は最初から専門家に
相続人同士が疎遠だったり、不仲な場合、遺産分割協議がまとまらず、手続きが進まないことがよくあります。特に、不動産の名義が曽祖父などの古い世代のままになっている場合、相続人の数が増え、相続人同士が顔も名前も知らないこともあります。
相続関係が複雑で、紛争の可能性がある場合は、無理に自分で進めず、最初から専門家に相談することをおすすめします。
5. まとめ
不動産の相続手続きは、複雑で手間のかかるプロセスです。書類を自分で揃えて申請するには知識と労力が必要で、さらに市区町村役場や法務局は平日しか開庁していないため、仕事などで時間的制約がある方は手続きが進みにくい場合があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されるため、今後はより速やかに相続登記を行う必要があります。書類集めが難しい、相続登記を放置している不動産がある場合は、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
(記事は2024年6月1日時点の情報に基づいています)
関連記事はこちら
- 親が認知症に…!?「資産凍結」の怖さと唯一の回避策
- 相続手続きの代行~費用相場や専門家選びのポイントを解説~
- 遺留分侵害額請求とは?改正で変わった内容や手続きのポイントを徹底解説
- 離婚した親の相続について徹底解説
- 遺産分割協議書の作成後に「騙された」と気付いた場合どうなる?
- 仲の良い兄弟でも争いが起こることもある――よくある相続トラブルの事例とその予防策
- 負の遺産がある場合の相続対策:相続人が取るべき行動とは?
- よく聞く代襲相続って? トラブルに関する事例や予防法を解説
- 軍用地の相続方法や手続き~重要なポイントを弁護士が解説~
- 相続の話はどう切り出すべき?事例を交えてご紹介
- 夫が亡くなった場合、家は誰のものに?相続の流れとトラブル回避のポイント
- 土地と現金を相続する際の分け方とは?遺産分割の方法と手続きの流れを解説
- よくある不動産登記トラブル3選
- 相続不動産の名義変更を成功させるには?費用や必要書類を徹底ガイド
- 養子縁組の相続トラブル5選:対策を解説します
- 家の名義変更って?これだけは知っておくべき知識8つを紹介!
- 遺産相続トラブルを防ぐ!調停・審判・訴訟の違いと弁護士活用のポイント
- 故人との同居の有無が「争続」の火種?!もめやすいケースと対処法を弁護士が解説
- 預金相続の手続き方法を徹底解説!
- 遺産に車があった場合はどのような手続きが必要?弁護士が解説します!
- 絶縁状態の兄弟姉妹との相続トラブル対処法
- 遺産に畑や山林がある!農家の相続を簡単に解説
- 遺産分割協議書を作成した後に「騙された」と気づいた場合、取り消しは可能?
- 子どもがいない夫婦の相続人は誰になるのか?注意点や対処法を弁護士が解説
- 不動産の名義変更は相続でどうする?必要な手続きや費用、注意点を解説
- 子どもがいない夫婦の相続ルールと注意点を解説
- 親が認知症になった場合の相続トラブルと対策について
- 株式相続の手続きとは? ~分割方法や評価額のポイントを徹底解説~
- 配偶者の連れ子に相続権はない!遺産相続の方法と対策
- 遺言書は全て有効?無効になるケースや注意点を解説!
- 「死後離婚」したい…相続に影響する?
- 息子の嫁に相続させたい!もめないための対処法を弁護士が解説
- 代償分割とは?代償金の決め方や相続税の計算方法について解説
- 弁護士が解説!お墓の管理と相続でトラブルを防ぐ2つのポイント
- 婿養子はどちらの財産も相続可能!妻の両親と実両親の相続分を徹底解説
- 一人だけに財産を渡してもいいの?遺言書作成の注意点や対策などを解説
- 「遺産隠し」されているかも…どうしたらいい?
- 遺言書の書き方は??要件や注意点を弁護士がわかりやすく解説
- 相続手続き、自分でやる?専門家に頼る?迷ったときの判断基準
- 不動産相続の分割方法から登記手続の必要書類まで解説
- 連れ子がいる場合の相続はどうなる?
- 借金は相続しなければならないのか?相続を回避するための手続きと注意点
- 遺言で赤の他人に財産を譲る方法と注意点
- 相続が発生!債務の支払いは?控除できる費用を解説
- 長男が先に亡くなっている場合、相続はどうなる?
- 子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみ?よくあるトラブルと対処法を弁護士が解説!
- 相続人で海外在住の場合、遺産分割協議書の作成はどうなる?
- 遺産相続で「がめつい」相続人とのトラブルが発生した場合の対処法は?
- 土地の相続放棄ができないケースとは?相続後に選べる対応策も解説
- 兄弟の子が相続人に?知っておきたい代襲相続のポイント
- 連帯保証人は相続放棄できない?
- 申述書の書き方と提出のポイントを徹底解説
- 祖父母の遺産を孫が相続するケースとそのポイント解説
- 親の借金を相続放棄できないケースとは?対策とポイント
- 実家の相続放棄おける重要なポイント
- 相続分とは?遺産の割合の決め方を簡単に解説!
- 疎遠な相続人がいるときの遺産分割のポイント
- 土地の相続放棄は兄弟一人でも可能?
- 海外在住の相続人がいる時の相続手続きは?注意点を弁護士が解説
- 相続放棄の費用について徹底解説!
- 海外在住の相続人がいる場合の相続手続きで知っておくべき注意点
- 相続放棄は弁護士に相談を!
- 兄弟姉妹が亡くなった時の相続と注意点について解説!
- 独身の方が亡くなった場合の相続権は誰になる?
- 相続放棄はどの専門家に相談する?
- 妻が亡くなった時の夫の遺産相続:知っておくべきポイントと手続き
- 兄弟姉妹の相続と遺留分の関係について解説
- いとこの財産は相続できる?注意点は?
- 不動産が必要ない時は相続放棄できる?注意点を弁護士が解説
- 相続人に障害者がいる場合の遺産相続について
- 続放棄後も空き家の管理義務は続く?【2023年改正】知っておきたい対策と対応策
- 子どもがいない夫婦の相続人は誰になる?
- 銀行預金の相続手続きに期限はある?必要な手続きとポイントを弁護士が解説
- 遺産相続で起こりがちな10のトラブル|生前にできる解決策も徹底解説
- 自動車も相続手続が必要?手続の流れとケース別必要書類を解説
- 兄弟姉妹に遺留分が認められない理由と遺産を受け取る手段
- 株式の名義変更について 手続きや照会方法について弁護士が解説
- 遺産相続に必要な手続きと期限について解説!
- 配偶者がいない場合の相続はどうなる?
- 一人っ子相続で注意すべきポイントを弁護士が解説!
- 土地や不動産の相続放棄は可能?
- 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎた場合の対処法!!
- 現金を相続したら?税金は?弁護士が解説
- 身寄りのない方が死亡したらどうなる?生前の対策はどうしたらいい?
- 相続放棄の期限は原則3ヶ月以内 起算点はいつから?
- 年金受給者が亡くなったら?相続や手続きについて弁護士が解説
- 子供がいない夫婦の相続によくあるトラブルと対処法を解説!
- 相続放棄の判断は3カ月以内に!期間が過ぎたら「上申書」で対応可能!
- 生前に相続放棄はできない!考えられる代替策とは?
- 親の借金は相続放棄で解決できる?
- 養子縁組にしても元の親の相続はできる?
- 親の介護をしない兄弟より多くの遺産を相続するには?弁護士が解決策を解説!
- 事実婚の夫・妻には相続権がない!財産を渡すための方法と対策を弁護士が徹底解説
- 相続税はいくらかかる?計算方法や注意点の解説
- 口座名義人が死亡した銀行口座はどうしたらいい?
- 破産者は遺産相続できる??注意点を弁護士が解説
- 専門家に依頼すべき相続による不動産の名義変更について
- いらない土地だけの相続放棄はできない?
- 沖縄で遺言書(自筆証書遺言)を書く時のポイントを弁護士が解説!
- 両親が離婚しても子供には相続権がある!相続分や注意点について解説
- 8/30(金)休業のお知らせ
- 生活保護を受けている人が遺産相続、相続放棄できる??
- 兄弟が親の介護をしてくれない!遺産を多く相続するための対策を弁護士が解説
- 相続放棄の3ヶ月の期限と注意点!!
- 兄弟姉妹が亡くなった時行う相続対策とは?弁護士が3つ紹介
- 家族へ相続の話を切り出しやすいタイミングと主な相続手続きの期限
- 家族信託とは
- 遺産相続の手続きの期限は??期限が切れた場合のデメリットを解説します!
- 親が亡くなったときの遺産相続の相続税とは?弁護士が解説!!
- 相続会議への掲載が始まりました
- 12月休業日・年末年始営業に関するお知らせ
- 【休業のお知らせ】9月1日はお休みです。
- 台風接近に伴う休業のお知らせ(8月2日更新)
- 遺言書作成のメリットは?相続で家族をもめさせたくない方必見です!
- 自筆証書遺言の書き方を弁護士が解説
- 休業日のお知らせ(8月30日、9月1日)
- 臨時休業日のお知らせ(6月30日)
- 皆様への感謝を込めて - 琉球法律事務所の新たな挑戦、テレビCMを公開
- 【休業日のお知らせ(4月6日~4月7日)】
- 【年末年始に伴う営業日のお知らせ】
- 休業日のお知らせ
- 弁護士兒玉竜幸入所のご挨拶
- 休業日のお知らせ
- 弁護士兒玉竜幸入所のご挨拶
- 年末年始の営業について
- 休業日のお知らせ
- Kindle書籍「キャリアとしての『国際弁護士』のススメ」発刊❗
- Youtubeイベントに登壇❗
- 在宅勤務終了のお知らせ
- 不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したいとき、どうすればいいですか?
- 在宅勤務のお知らせ
- 新型コロナウィルス(CORVID-19)感染者 およびその対応についてのお知らせ
- 休業日のお知らせ
- 退職のご挨拶(秀浦)
- 7月3日(土)軍用地相続セミナーを開催します【沖縄タイムス社後援】
- 休業日のお知らせ
- 年末年始の営業について
- 台風による営業停止に関して(9月3日追記)
- 休業日のお知らせ
- 当事務所で発生した新型コロナウィルス(CORVID-19)感染者およびその対応についてのお知らせ
- 愛人や隠し子に相続する権利はあるの?
- 養子縁組の子供の相続方法
- 異母兄弟がいる場合の相続方法
- 遺言執行を代わりに行ってもらうことはできる?
- 預貯金・借金などの相続財産の調べ方
- 遺産分割調停を欠席するとどうなる?
- 父の遺産を母がひとり占めすると言ったら?
- 「葬儀」にまつわる「相続」問題について
- 「香典」と「相続」にまつわる相続トラブルについて
- 【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止対応について
- 【相続Q&A】軍用地の倍率とは?相続に関係するの?
- 【5月18日(土)開催】沖縄相続トラブル・遺言無料法律相談会

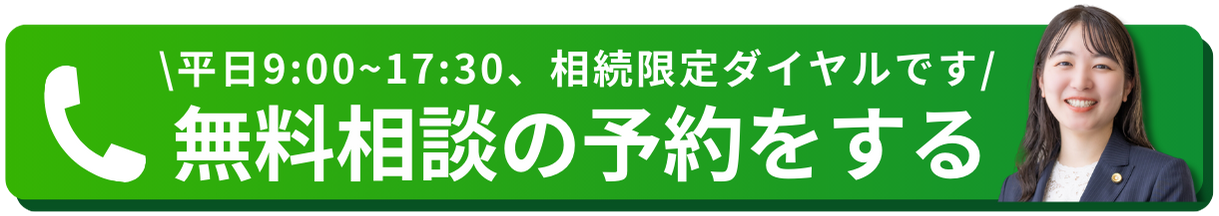
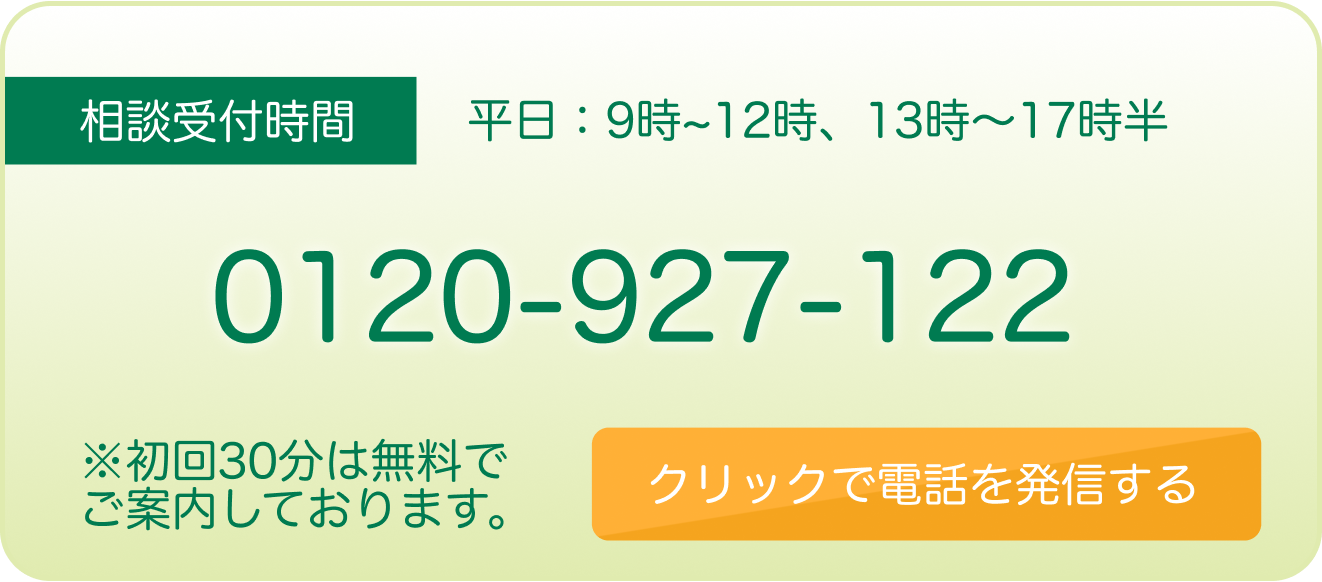
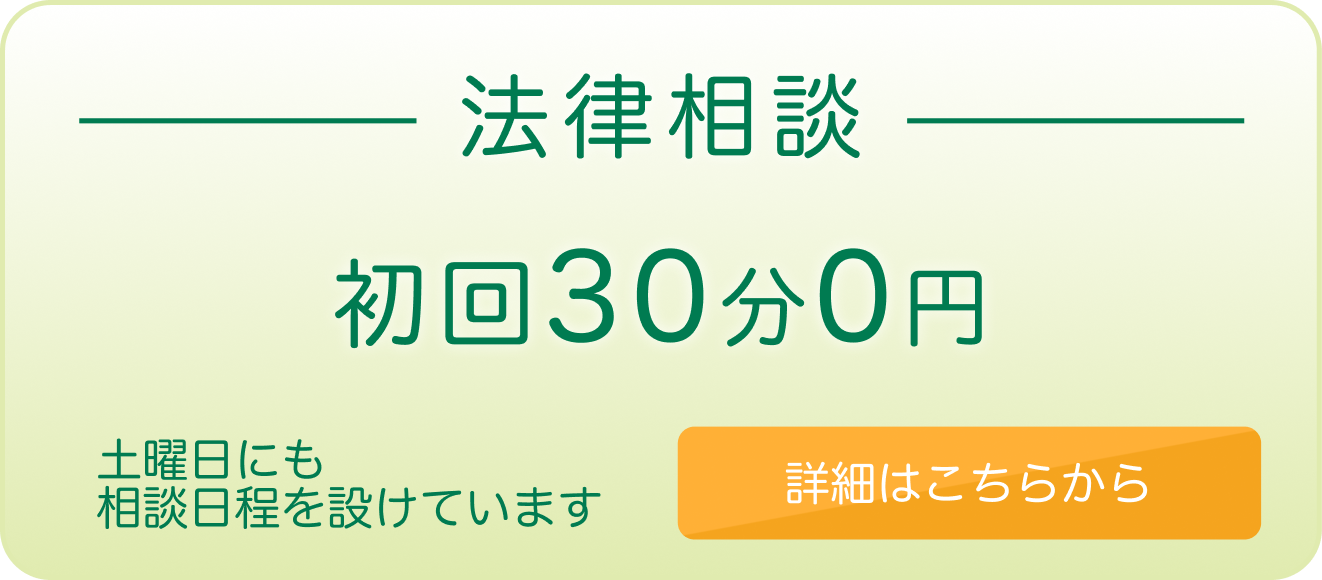
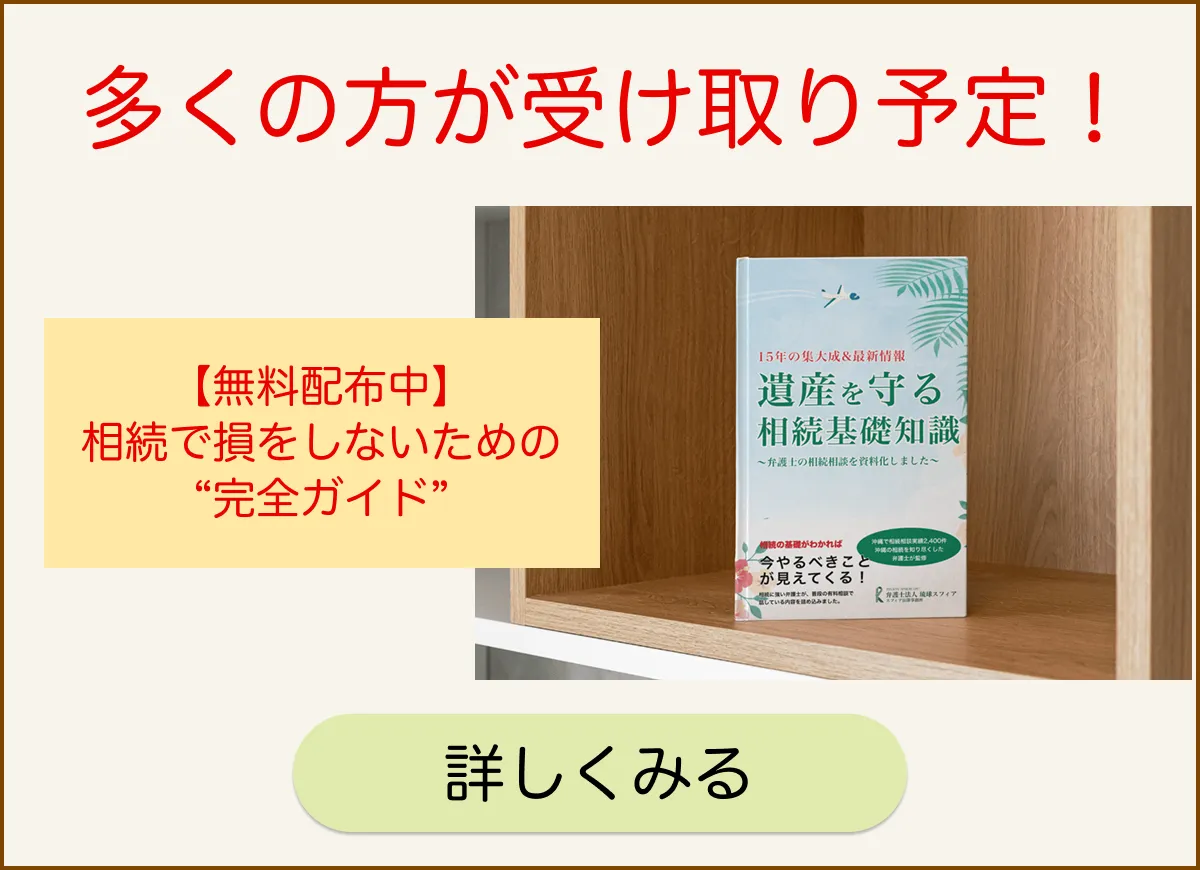
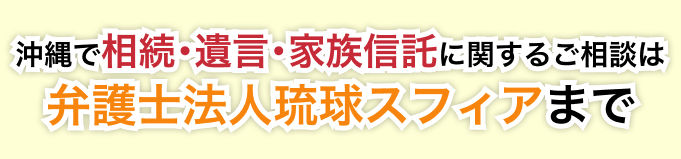

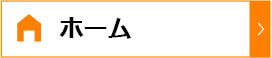
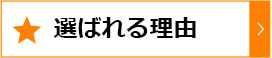
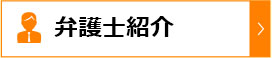
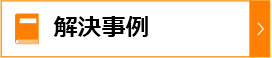
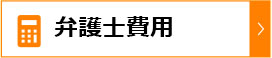
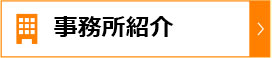

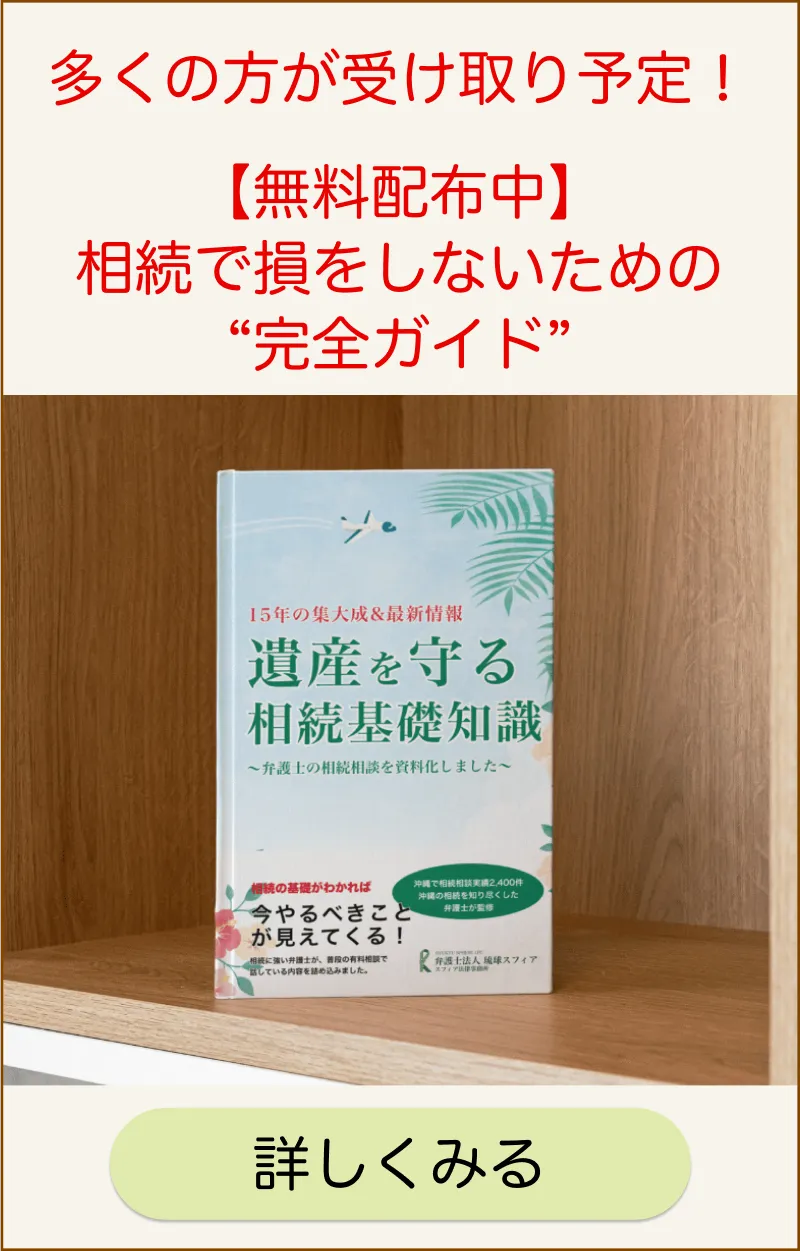

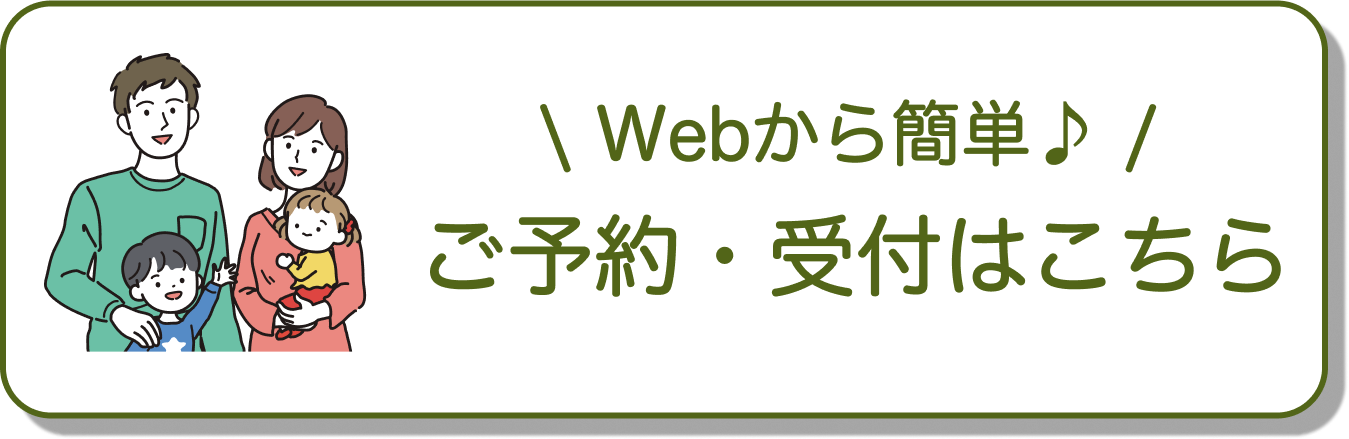


.png)
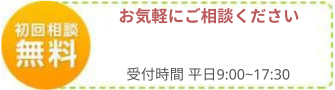
.png)