相続に関する総合FAQ
遺言書、遺留分、相続登記、海外資産(香港など)、軍用地、相続税、不動産評価など、相続に関する幅広い疑問にお答えします。
相続は法律・税金・不動産が絡み合い、少しの判断の違いで大きな損失や争いにつながることがあります。制度改正や期限のある手続きも多く、早めの対応が重要です。
当事務所では、相続に強い弁護士が税理士・司法書士・不動産専門家と連携し、最適な解決策をご提案します
相続の疑問や不安は、早めに弁護士へご相談ください。
目次
遺産分割協議でよくある質問
Q1: 父が亡くなり、相続人は兄と私だけですが、遺産分割協議を拒否されています。どうすればいいですか?
A1: 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。兄が協議に応じない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。最終的に調停での協議が合意に至らない場合には、家庭裁判所の審判手続により解決を図ることになります。
Q2: 生前に兄が父の財産を勝手に使い込んでいたようですが、遺産分割に影響しますか?
A2: 兄の行為が、不法行為にあたる場合や、不当利得にあたる場合は、遺産分割とは別にその返還を求めることができます。この場合には、原則として家庭裁判所ではなく、地方裁判所における訴訟手続を検討する必要があります。また、相続財産から費消された部分が、父から兄への生前贈与にあたるような場合には、遺産分割協議の中で、特別受益の対象として協議する可能性もあります。
Q3: 遺産の中に借金があります。これも分割の対象ですか?
A3: 借金(債務)は、原則として遺産分割の対象とはなりません。債務は、各相続人が法定相続分に応じて当然に分割承継することになります。但し、全相続人の合意により、相続人の中で誰が承継負担するかを協議すること自体は可能です。この場合、注意が必要なのは、債権者の側からすると、原則どおり各相続人が分割承継しているため、各相続人に請求がなされる可能性があります。
Q4: 親の家に私が住んでいたのですが、それでも家を売って分ける必要がありますか?
A4: 必ずしも家を売って分けなければならないわけではありません。不動産の遺産分割の方法は、主に単独取得、現物分割(分筆等)、共有、代償分割、換価分割などの方法があります。相続人全員の合意があれば、あなたがその家を単独で相続し、他の相続人には代償金を支払う(代償分割)、または他の財産で調整する(単独取得)、何人かで家を共有する(共有)といった方法も可能です。但し、合意が得られない場合は、最終的に家を売却して代金を分割すること(換価分割)も選択肢となります。
Q5: 遺産に農地や山林があります。評価や分け方はどう決めるのですか?
A5: 農地や山林の評価は、固定資産税評価額、相続税評価額、または不動産鑑定士による時価評価などを参考に、相続人全員の合意によって決定します。なお、農地や山林の評価に関しては、宅地として転用できるか否かも重要な考慮要素となるので注意が必要です。具体的な分け方としては、単独取得、共有、現物分割(土地を物理的に分ける)、代償分割(特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払う)、換価分割(売却して代金を分ける)が考えられます。農地の場合、農地法による制限も考慮する必要があります。
Q6: 他の相続人が音信不通です。遺産分割協議は進められますか?
A6: 音信不通の相続人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。以下の手続きを検討する必要があります。
1、戸籍等を取得し、音信不通となっている相続人の生死や所在を調査します。
2、不在者財産管理人選任の申立て: 調査しても、その相続人が行方不明で、財産を管理する者がいない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。選任された管理人が、その相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
3、失踪宣告の申立て: 音信不通の期間が長期(通常7年以上)にわたる場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。失踪宣告が確定すると、その相続人は法律上死亡したものとみなされるため、その相続人の法定相続人との間で遺産分割を進めることが可能になります。
Q7: 亡くなった父の預金口座を兄が一方的に引き出しています。取り戻せますか?
A7: 兄が単独で預金を引き出した場合、当該預金は遺産であるため、不当利得または不法行為にあたる可能性があります。そのため、他の相続人は、兄に対し、引き出した金額のうち自己の相続分に相当する部分の返還を求めることができます。ただし、被相続人の葬儀費用などに充てられた場合は、直ちに不当利得又は不法行為に該当するとは言えない場合があります。 また、民法の改正により、相続人全員(財産を処分した相続人以外)の同意により、処分された財産が遺産として存在するものとみなして、遺産分割を行うことも可能となりました。
Q8: 私は母の介護を長年してきました。その分を遺産に反映させられますか?
A8: はい、長年の介護が被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をしたと認められる場合、「寄与分」としてその貢献度を遺産分割に反映させることができます。この「特別の寄与」に該当するかを判断するに当たっては、看護の必要性、専従性、継続性や無償性、財産の維持・増加との間の因果関係などを総合的に考慮する必要があります。
Q9: 遺言書には「全財産を長男に相続させる」とありますが、納得できません。どうしたらいいでしょうか?
A9: 遺言書によって特定の相続人に全財産を相続させる内容であっても、あなたには「遺留分」という最低限の相続分が法律で保障されています。遺留分を侵害された場合、遺言によって財産を取得した長男に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。この遺留分侵害額請求には期間制限がありますので注意が必要です。
Q10: 遺産の一部に名義変更されていない古い不動産があります。どう扱えばいいですか?
A10: 名義変更されていない古い不動産も、被相続人が実質的に所有していたものであれば、遺産分割の対象となります。
まずは、登記簿謄本や過去の書類(売買契約書、固定資産税の納税通知書など)を確認し、被相続人が所有者であったことを証明する資料を集める必要があります。例えば、名義が被相続人の両親や祖父に当たるような場合で被相続人が相続人に当たるような場合には、現在の不動産の登記の名義人の相続人の間で、遺産分割協議を行う必要があります。
他方で、現在の不動産の名義人から、被相続人が過去に購入していたというような場合には、まずは被相続人の名義とすべく、遺産確認と登記名義の移転を求める訴訟の提起等を検討する必要があります。その上で、被相続人の遺産と確定されたことを前提に、遺産分割協議において、改めて誰がその不動産を取得するかを決定します。
Q11: 母が私だけを除いて他の子に財産を遺贈していました。遺留分はどうなりますか?
A11: 質問者様が子であれば、遺留分を請求できます。
Q12: 遺留分を請求したいのですが、遺産の内容がよく分かりません。どうすれば調査できますか?
A12: 弁護士への依頼を含め、戸籍・評価証明書・名寄帳・金融機関や保険会社への照会などで調査できます。
Q13: 遺留分の請求は弁護士に依頼した方が良いですか?費用はどれくらいかかりますか?
A13: 弁護士に依頼することで適切な対応や調査、交渉が可能となり、費用は着手金・報酬金・実費などが発生します。
Q14: 特定の財産(自宅や株など)が遺贈されている場合、どうやって金銭で遺留分を計算するのですか?
A14: 遺贈財産を相続開始時点の時価で評価し、遺留分算定の基礎財産に加えて計算します。
Q15: 遺留分の計算に生命保険金や死亡退職金は含まれますか?
A15: 原則として含まれませんが、金額や状況により例外的に含まれる可能性があります。
Q16: 遺留分を請求すると、相続税の負担はどうなりますか?
A16: 遺留分侵害額の取得分は相続税の課税対象となります。
Q17: 父が認知症のときに作った遺言書で私の相続分がゼロにされています。遺留分は主張できますか?
A17: はい、遺言の無効を主張するか、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
Q18: 相続人の一人が生前に多額の援助を受けていました。遺留分に影響しますか?
A18: はい、特別受益として遺留分算定に反映される可能性があります。
Q19: 遺留分の請求をしたら、相手から「争うなら調停に行け」と言われました。本当に調停が必要ですか?
A19: はい、原則として家庭裁判所の調停を経る必要があります(調停前置主義)。
Q20: 遺留分請求で裁判になった場合、どれくらいの期間や費用がかかりますか?
A20: 調停は数ヶ月〜1年、訴訟は1年〜数年かかることも。費用は数十万円〜数百万円程度かかる可能性があります。
遺留分に関するよくある質問
Q1: 父の遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。長女である私は遺留分を請求できますか?
A1: はい、請求できます。
Q2: 遺留分侵害額請求はいつまでに行えばよいですか?時効はありますか?
A2: 時効(又は除斥期間)があります。原則として、以下のいずれか早い期間内に請求する必要があります。①遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内。②相続開始の時から10年以内。
Q3: 父が兄に全財産を生前贈与していたようです。遺留分は請求できますか?
A3: はい、請求できる可能性があります。
Q4: 私は被相続人の兄弟ですが、遺留分はありますか?
A4: いいえ、兄弟姉妹には遺留分はありません。
Q5: 母が亡くなり、父が全財産を相続しました。長女である私は遺留分を請求できますか?
A5: はい、請求できます。
Q6: 遺言書が公正証書遺言でしたが、それでも遺留分請求は可能ですか?
A6: はい、可能です。
Q7: 遺留分を金銭ではなく不動産で請求することはできますか?
A7: 原則として、遺留分は金銭で請求することになります。
Q8: 遺留分を請求したら、他の相続人と関係が悪化しそうで悩んでいます。請求しないとどうなりますか?
A8: 請求しない場合、遺留分侵害額請求権は時効(又は除斥期間)によって消滅し、その分を受け取ることはできません。
Q9: 遺留分侵害額の計算はどうやって行うのですか?
A9: 父の相続において、相続人が子2人の場合、被相続人の唯一の遺産である土地(評価1000万円)が長男に遺贈された場合、もう1人の相続人である長女の遺留分の額は次の算定式で計算されます。
1000万円×総体的遺留分率2分の1×遺留分権利者の法定相続分2分の1=250万円
Q10: 請求先の相手が財産を使い込んでいた場合、どうやって回収しますか?
A10: 財産調査、財産開示手続、強制執行などを通じて回収を図ります。
Q11: 母が私だけを除いて他の子に財産を遺贈していました。遺留分はどうなりますか?
A11: 質問者様が子であれば、遺留分を請求できます。
Q12: 遺留分を請求したいのですが、遺産の内容がよく分かりません。どうすれば調査できますか?
A12: 弁護士への依頼を含め、戸籍・評価証明書・名寄帳・金融機関や保険会社への照会などで調査できます。
Q13: 遺留分の請求は弁護士に依頼した方が良いですか?費用はどれくらいかかりますか?
A13: 弁護士に依頼することで適切な対応や調査、交渉が可能となり、費用は着手金・報酬金・実費などが発生します。
Q14: 特定の財産(自宅や株など)が遺贈されている場合、どうやって金銭で遺留分を計算するのですか?
A14: 遺贈財産を相続開始時点の時価で評価し、遺留分算定の基礎財産に加えて計算します。
Q15: 遺留分の計算に生命保険金や死亡退職金は含まれますか?
A15: 原則として含まれませんが、金額や状況により例外的に含まれる可能性があります。
Q16: 遺留分を請求すると、相続税の負担はどうなりますか?
A16: 遺留分侵害額の取得分は相続税の課税対象となります。
Q17: 父が認知症のときに作った遺言書で私の相続分がゼロにされています。遺留分は主張できますか?
A17: はい、遺言の無効を主張するか、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
Q18: 相続人の一人が生前に多額の援助を受けていました。遺留分に影響しますか?
A18: はい、特別受益として遺留分算定に反映される可能性があります。
Q19: 遺留分の請求をしたら、相手から「争うなら調停に行け」と言われました。本当に調停が必要ですか?
A19: はい、遺留分に関しては、原則として、訴訟に先立ち家庭裁判所の調停を経る必要があります(調停前置主義)。
Q20: 遺留分請求で裁判になった場合、どれくらいの期間や費用がかかりますか?
A20: 調停は数ヶ月〜1年、訴訟は1年〜数年かかることも。費用は数十万円〜数百万円程度かかる可能性があります。
遺言に関するよくある質問
Q1: 遺言書って自分一人で作っても法的に有効ですか?
A1: 遺言書の種類によっては、ご自身一人で作成しても法的に有効な場合があります。最も一般的なのは「自筆証書遺言」です。
Q2: どのタイミングで遺言を作成しておくべきですか?年齢や病気など関係ありますか?
A2: 遺言は「書こうと思ったとき」に作成しておくべきです。認知症などで判断能力が低下すると作成できななるため、早めが望ましいです。
Q3: 子どもの一人に多く遺したいと思っています。他の子と差をつけても大丈夫ですか?
A3: はい、遺言で差をつけることは可能ですが、他の子には遺留分があるため注意が必要です。
Q4: 夫婦で一通の遺言書を作りたいのですが、共同で書いてもいいですか?
A4: いいえ、夫婦で共同して一通の遺言書を作成することはできません。
Q5: 自筆証書遺言を書いた後、どこに保管するのが安全ですか?誰かに見つけられたくない場合は?
A5: 法務局の遺言書保管制度の利用をお勧めいたします。詳しくは弊所までお問い合わせください。
Q6: 遺言の内容を将来変更したくなった場合、どうすればいいですか?
A6: 遺言はいつでも撤回・変更できます。新しい遺言を作成すれば古い内容は撤回されます。
Q7: 遺言書に財産の分け方以外のこと(例:介護してくれたことへの感謝)も書けますか?
A7: はい、「付言事項」として書くことが可能です。法的効力はありませんが、心情や意思を伝える手段となります。
Q8: 相続人以外の人(内縁の妻、友人、寄付先など)に財産を残したい場合、遺言で可能ですか?
A8: はい、可能です。「遺贈」という形で遺言に記載すれば、相続人以外にも財産を残すことができます。
Q9: 不動産を相続させたい場合、遺言にどう書けば登記手続きがスムーズに進みますか?
A9: 登記簿情報を正確に記載し、誰に相続させるかを明確にし、そして「遺言執行者」を指定します。
Q10: 認知症になってしまうと遺言は作れなくなりますか?判断能力に不安がある場合はどうすれば?
A10: 判断能力(法的には「遺言能力」)があるうちであれば作成可能です。不安がある場合はお早めに弁護士にご相談ください。
相続登記に関するよくある質問
Q1: 相続登記とは何ですか?相続登記をしないとどうなりますか?
A1: 相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きです。相続登記をしないと売却や担保として利用できず、将来の相続で手続きが複雑化し、トラブルや過料のリスクもあります。
Q2: 相続登記はいつまでにやらないといけないのですか?
A2: 2024年4月1日からは、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。2024年4月1日よりも前に相続した不動産も、相続登記の対象です。
Q3: 相続登記をしないまま放置していた土地があるのですが、今からでもできますか?
A3: はい、可能です。過去の相続であっても、必要書類を揃えれば登記できます。ただし、時間が経つと手続きは複雑化しますので、お早めにご連絡ください。
Q4: 遺言や遺産分割協議を経ておらず、相続人が複数いる場合、全員の同意がないと相続登記はできませんか?
A4: 法定相続分での共有登記は単独申請が可能です。
Q5: 相続登記に必要な書類は何ですか?戸籍はどこまで集めればいいですか?
A5: 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・住民票、遺産分割協議書や遺言書などが必要です。
Q6: 自分で相続登記をすることはできますか?それとも専門家に依頼する必要がありますか?
A6: 自分で相続登記をすることは可能ですが、手続きが複雑なため、司法書士や弁護士など専門家に依頼する方が確実で安心です。
Q7: 相続登記申請の費用はどれくらいかかりますか?登録免許税とは何ですか?
A7: 登録免許税とは、相続登記を申請する際に法務局に納める税金です。金額は、固定資産評価額の0.4%です。
Q8: 遺言書がある場合とない場合で、相続登記の手続きはどう変わりますか?
A8: 遺言書があると単独で登記できる場合が多く、手続きが簡略化されます。遺言書がない場合は遺産分割協議と相続人全員の同意が必要です。
Q9: 相続人の中に亡くなっている人がいる場合、相続登記はどうなりますか?
A9: その人の相続人(代襲相続人)が登記に参加する必要があります。戸籍も追加で集める必要があり、手続きは複雑化します。
Q10: 共有名義にしたくないのですが、相続登記で単独名義にすることは可能ですか?
A10: はい。遺言での指定や、遺産分割協議による合意があれば、単独名義で登記できます。
香港相続に関するよくある質問
Q1: 香港にある不動産や預金は、日本の相続手続きだけで相続できますか?
A1: いいえ、日本の相続手続きだけでは、香港にある不動産や預金を相続することはできません。現地での相続手続きが必要です。
Q2: 香港に住んでいた親族が亡くなりました。相続の手続きはどこの国の法律が適用されますか?
A2: 被相続人が亡くなった時点で住所地とされた国(domicile)の法律が適用されます。不動産については所在地国の法律が適用されるのが一般的です。
Q3: 香港にある財産を相続するには、香港での遺産承継手続きが必要ですか?
A3: はい、香港高等法院での相続手続き(ProbateまたはLetters of Administration)が必要です。
Q4: 香港にある預金口座を相続するには、どんな書類が必要ですか?
A4: 香港の裁判所が発行するProbateまたはLetters of Administrationが必要です。その他、死亡証明書や相続人の身分証などが求められます。
Q5: 香港にある遺産について、日本の相続税は課税されますか?
A5: はい、被相続人または相続人が日本に住所を有していた場合、日本の相続税の課税対象になります。
Q6: 香港では遺産税や相続税はかかりますか?
A6: いいえ、香港では2006年に遺産税が廃止されており、課税されません。
Q7: 日本の遺言書で香港の財産を処理することは可能ですか?
A7: 形式的要件を満たしていれば可能ですが、香港での手続きが必要です。
Q8: 香港に相続人が住んでいる場合、日本の相続手続きをどのように進めればいいですか?
A8: 日本の手続きは国内法に基づき進められますが、香港在住の相続人の署名・本人確認のため、領事館の証明などが必要です。
Q9: 香港にある会社の株式や法人名義財産を相続するには、どんな手続きが必要ですか?
A9: 株式の場合はProbateまたはLetters of Administrationを取得し、名義変更手続きが必要です。
Q10: 香港の相続手続きは、弁護士や現地の専門家に依頼した方がよいですか?
A10: はい、現地法の理解や手続きの複雑さ、言語の問題を考えると、専門家に依頼するのが最も安全です。
軍用地の相続に関するよくある質問
Q1: 軍用地の相続には、通常の不動産と違った手続きが必要ですか?
A1: はい、軍用地の相続には、通常の不動産相続とは異なる、あるいは追加の手続きが必要です。特に、地料(借地料)の承継に関する手続きが異なります。
Q2: 軍用地の借地料(地料)は誰がもらえるようになりますか?手続きは必要ですか?
A2: 軍用地の地料は、相続登記が完了し、防衛省に地料受給者変更の手続きを行った相続人が受け取れます。
Q3: 軍用地を複数人で相続した場合、地料はどう分けられますか?
A3: 共有名義となった場合、地料は原則として各共有者の持分割合に応じて支払われます。
Q4: 軍用地の地料は「遺産」になりますか?それとも相続後の収益ですか?
A4: 相続開始日以前に発生した未受領の地料は「遺産」、それ以降に発生した地料は「相続後の収益」です。
Q5: 軍用地の名義変更(相続登記)をしないままでも地料は受け取れますか?
A5: いいえ、防衛省は登記簿上の名義人に支払うため、名義変更がなければ地料は支払われません。
Q6: 軍用地の相続登記に必要な書類は何ですか?どこで手続きするのですか?
A6: 必要書類は通常の相続登記と同様で、所在地を管轄する法務局で行います。
Q7: 父の相続登記が終わっていないのに、祖父の軍用地の相続が必要になりました。どうすれば?
A7: 祖父→父→あなたという二段階の相続登記が必要です(数次相続)。
Q8: 軍用地の相続登記を司法書士に依頼すると、費用はいくらくらいかかりますか?
A8: 登録免許税(評価額の0.4%)と司法書士報酬、実費を含めて数万円〜数十万円が目安です。
Q9: 軍用地を相続放棄したい場合、どうすればいいですか?借地料は放棄できますか?
A9: 家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、地料を含む一切の財産を承継しない扱いになります。
Q10: 軍用地の評価はどう決まりますか?他の財産と合わせた遺産分割時に注意すべきことは?
A10: 固定資産評価額、実勢価格、収益性など複数の観点から評価します。流動性の低さや将来返還リスクも要考慮。
相続税に関するよくある質問
Q1: 相続税はどれくらいの財産からかかりますか?基礎控除の金額はいくらですか?
A1: 相続税は、被相続人から相続または遺贈により財産を取得した各人ごとの相続税の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合に課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
Q2: 相続税の申告はいつまでに行わないといけませんか?
A2: 原則として、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税が必要です。
Q3: 相続税を払うお金が手元にない場合、分割払いや延納はできますか?
A3: はい、一定の要件を満たせば延納や物納が認められます。延納は年賦払いで、物納は財産で納税します。
Q4: 生命保険金や退職金にも相続税はかかりますか?
A4: はい、みなし相続財産として課税対象です。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
Q5: 不動産を相続した場合、相続税はどのように評価されますか?時価ですか?
A5: 評価は相続開始日における「時価」ですが、実務上は路線価方式・倍率方式(固定資産税評価額)が用いられます。
Q6: 配偶者が相続する場合、相続税はどのくらい軽減されるのですか?
A6: 配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い方まで非課税になります。
Q7: 生前贈与を受けていた分は相続税に影響しますか?何年前までさかのぼるのですか?
A7: 被相続人死亡前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。令和5年度税制改正により、2024年1月1日以降に行われる暦年贈与から生前贈与の加算期間が「3年」から「7年」に延長されました。この延長に伴い経過措置が設けられ、加算期間は、2027年1月2日以降に開始した相続から段階的に7年まで延長予定です。
Q8: 相続税の節税対策として有効な方法にはどんなものがありますか?
A8: 生前贈与、生命保険の活用、小規模宅地の特例、不動産活用、養子縁組、遺言書作成などがあります。
Q9: 相続税の申告は自分でできますか?税理士に依頼する場合の費用は?
A9: 申告は可能ですが複雑でリスクも高いため、税理士への依頼が推奨されます。費用は遺産総額の0.5~1%が目安です。
Q10: 相続税の対象になる財産とならない財産にはどんな違いがありますか?
A10: 課税対象は現金・不動産・有価証券・生命保険金など。非課税は墓地・仏壇・公益目的の寄付などです。
不動産の評価に関するよくある質問
Q1: 相続税を計算するための不動産の評価は、どのように決められるのですか?
A1: 相続開始日の時価が原則ですが、「財産評価基本通達」に基づいて評価額が決まります。
Q2: 路線価がない地域の場合、土地の評価はどうするのですか?
A2: 「倍率方式」により、固定資産税評価額に国税庁公表の倍率を乗じて評価します。
Q3: 自宅の土地と建物を相続しました。土地と建物はそれぞれどう評価されますか?
A3: 土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価します。
Q4: 不動産の固定資産税評価額と相続税評価額は同じですか?
A4: 異なります。固定資産税評価額は市町村が算出し、相続税評価額は国税庁基準で評価されます。また、土地の固定資産税評価額は地価公示価格の70%程度、相続税評価額は地価公示価格の80%の評価となっています。
Q5: 貸している土地やアパートは、評価が下がると聞きましたが本当ですか?
A5: はい。借地権や借家権により使用制限があるため、評価額が減額されます。
Q6: 空き家の土地でも評価額は高くなることがありますか?
A6: 立地や周辺環境によっては空き家でも土地評価額が高くなるケースがあります。
Q7: 相続人の1人が住み続ける場合、不動産はどう評価・分割されますか?
A7: 評価自体は変わらず、遺産分割で代償分割や共有とする方法があります。
Q8: 不動産評価を下げて節税することは可能ですか?
A8: 合法的に評価減を活用すれば可能です。補正率、小規模宅地、貸家建付地評価減などがあります。
Q9: 複数の相続人で不動産を共有することになった場合、評価はどうなりますか?
A9: 不動産全体の評価額を各人の持分割合に応じて按分して評価します。
Q10: 不動産の相続税評価を専門家に依頼すると、費用はどれくらいかかりますか?
A10: 税理士なら申告報酬内。不動産鑑定士なら数十万〜数百万円が目安です。

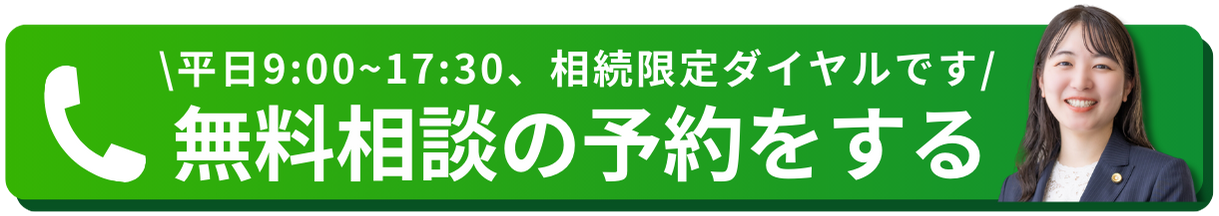
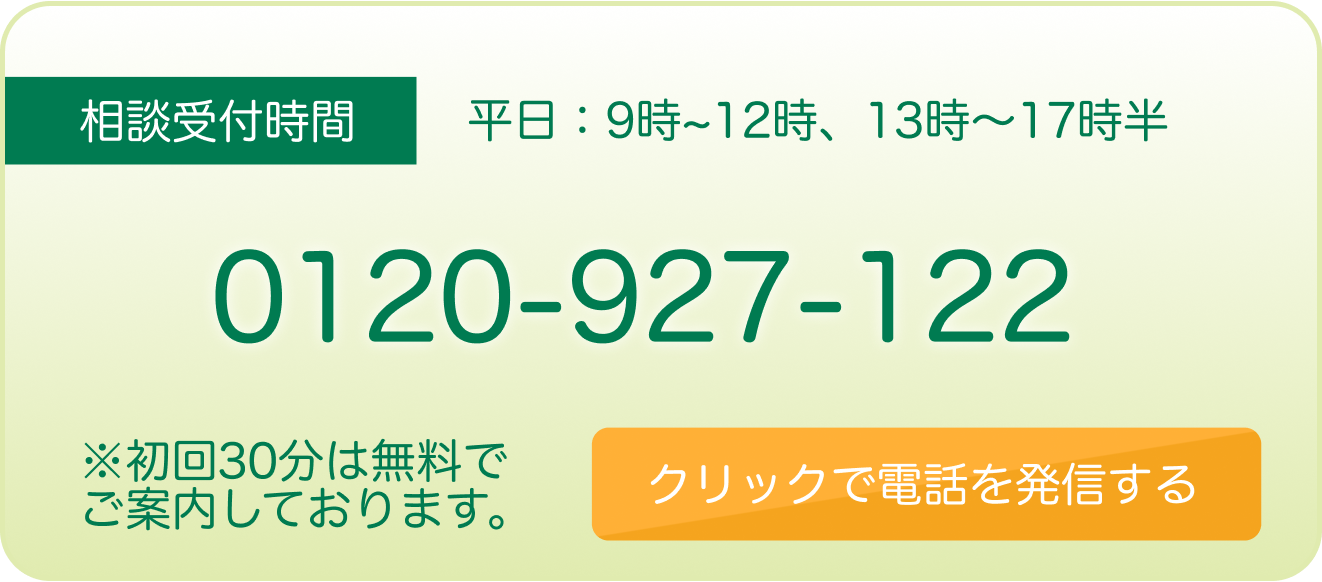
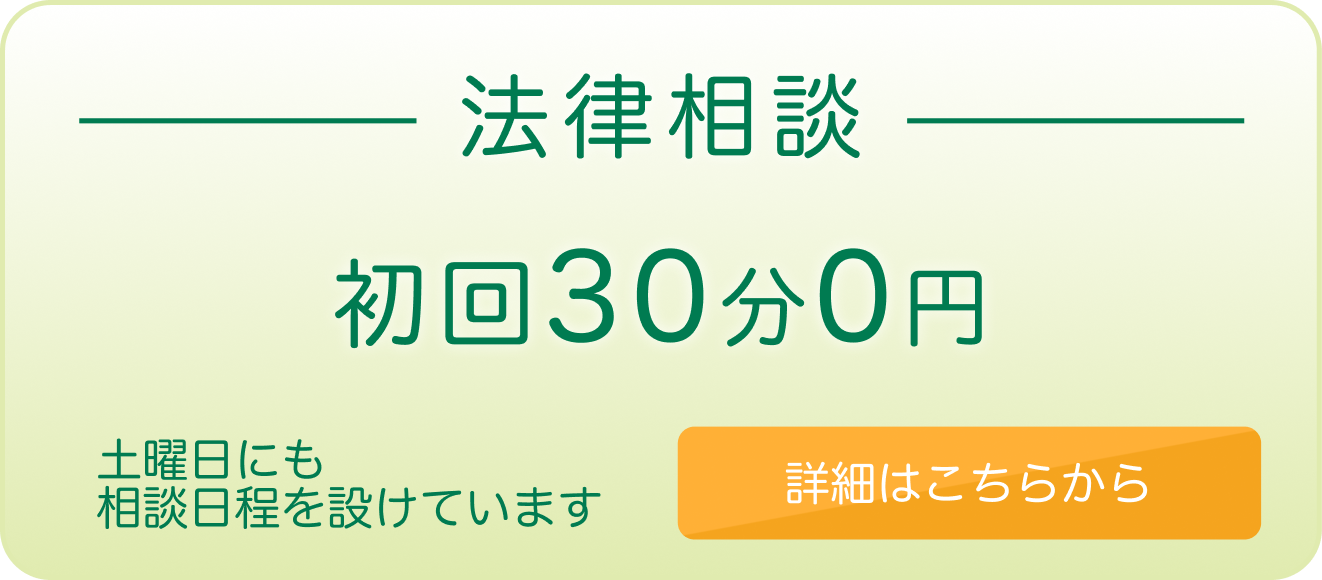
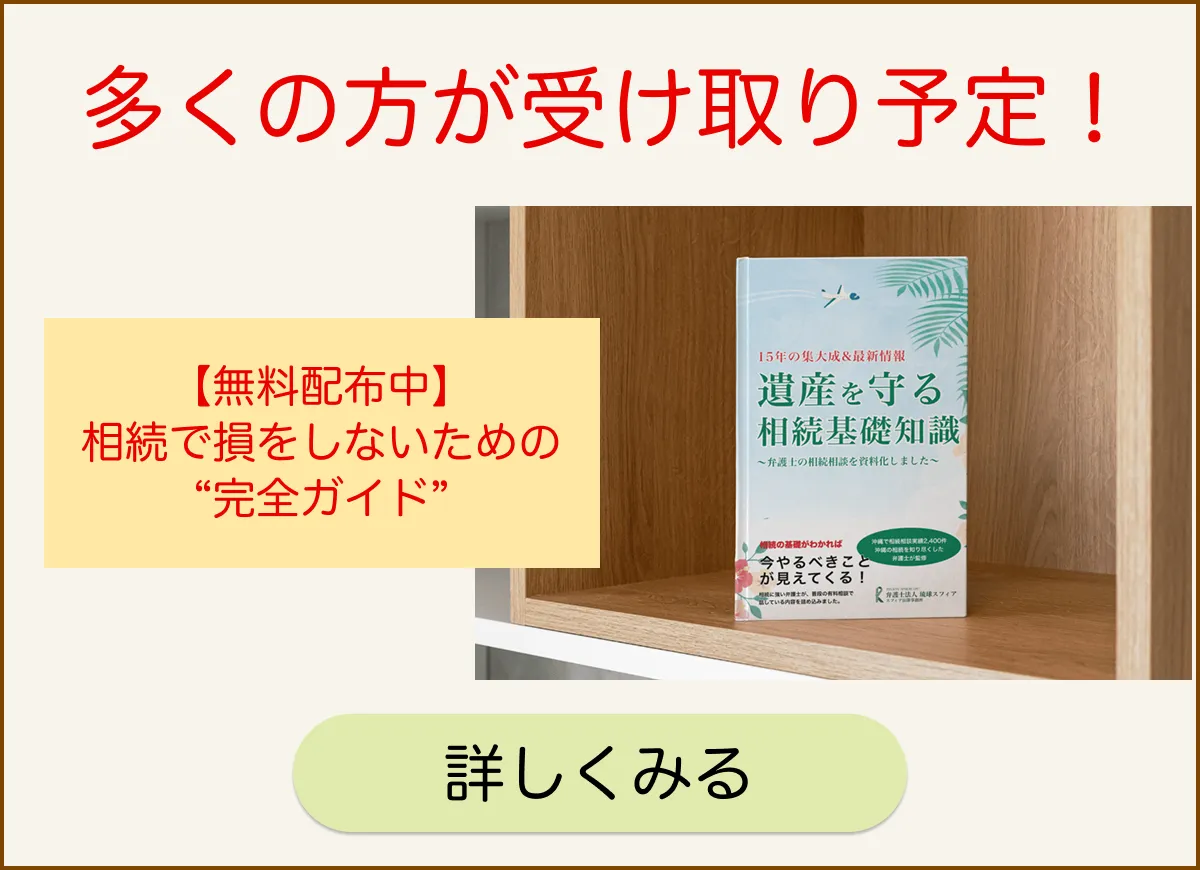
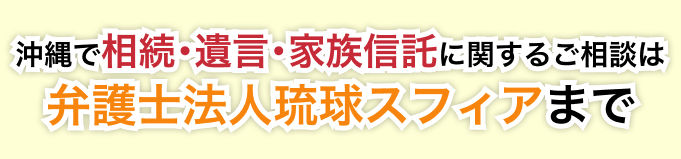

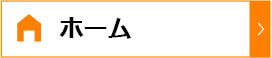
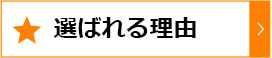
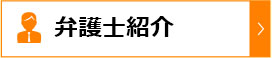
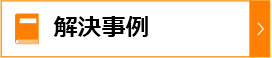
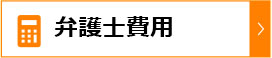
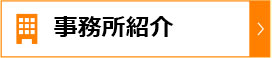

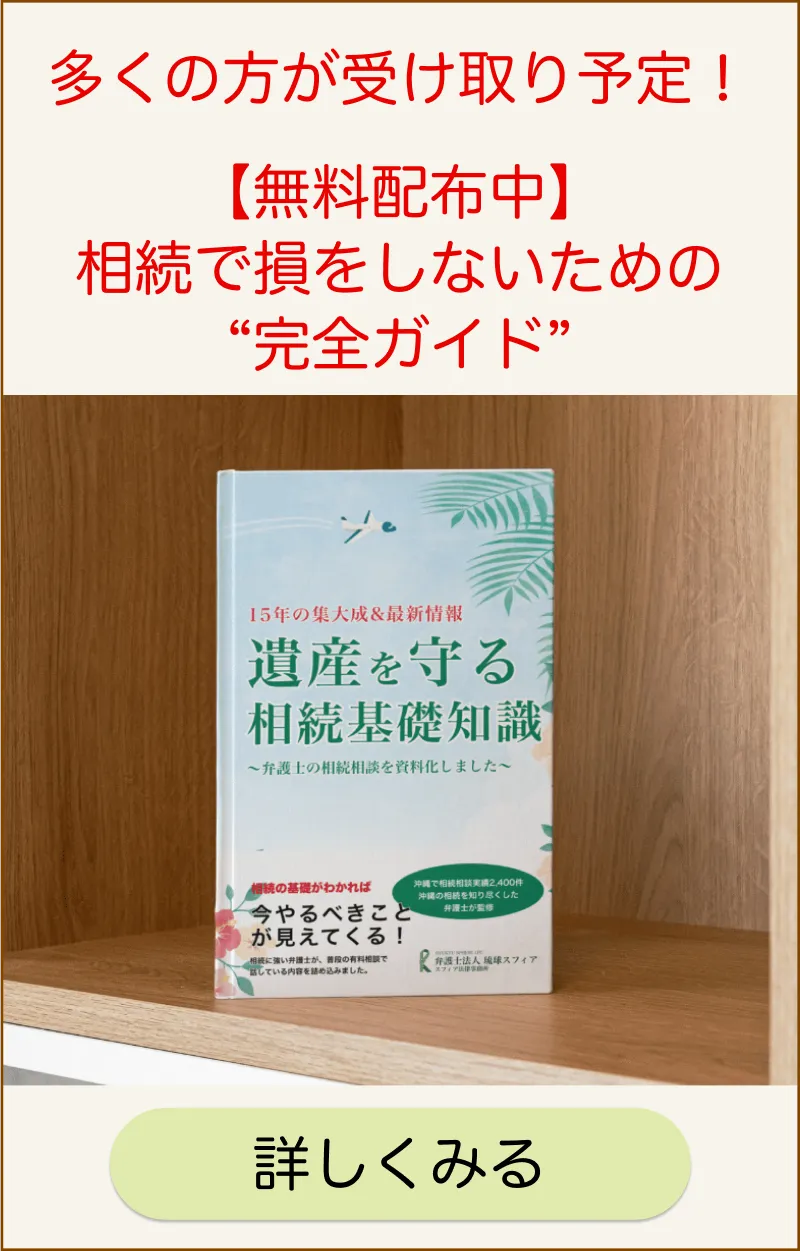

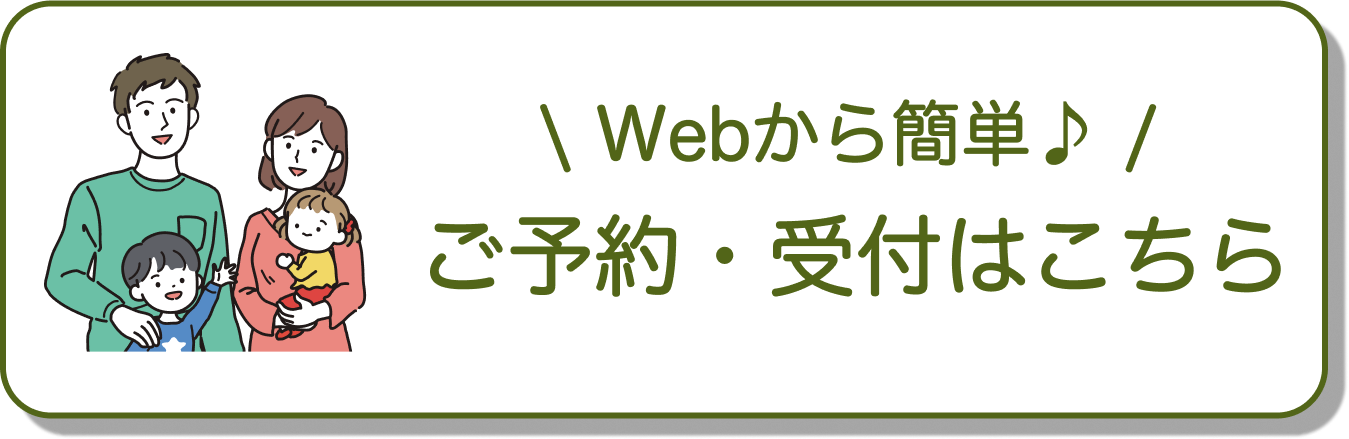


.png)
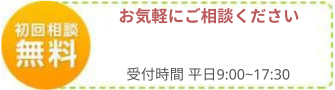
.png)