仲の良い兄弟でも争いが起こることもある――よくある相続トラブルの事例とその予防策
1. きょうだい間の相続争い、他人事だと思っていませんか?
夏目漱石の小説『こころ』には、こんな一節があります。
先生が主人公に「財産分与を受けておくべきだ」と助言した後、こう語ります。
「悪い人間という一種の人間……そんな鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよ。平生はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それが、いざという間際に、急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです」。
相続争いとは、特別な家庭だけの話ではありません。「普通の家族」の間でも繰り返される問題なのです。
2. きょうだい(被相続人の子)の相続分
民法では、相続人とその相続分が法定されています。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、子どもがいればその子どもも相続人になります。子どもが複数いる場合は、その法定相続分は均等です。例えば、配偶者がいない状態で子どもが3人いる場合、各自が財産の1/3ずつを相続することになります。
また、生前贈与や遺贈などで法定相続分の財産を相続できない場合でも、遺留分が法律で保障されています。遺留分とは、相続人に最低限保証される相続額のことです。子どもの遺留分は法定相続分の1/2とされ、先ほどの例では全体の1/6に相当します。
3. 兄弟間で起きやすいトラブルと予防策
相続の際に起こりやすいトラブルを六つに分け、その予防策を解説します。
3-1. 相続財産が不明確
例:両親と同居していた長男と、別居していた長女がいる場合。
両親の死後、長男は「思ったより財産が少ない」と言い、長女は「財産を隠されているのでは」と疑いトラブルに発展することがあります。
予防策:両親に財産目録を作成してもらい、管理する場合は収支を記録すること。定期的に見直し、関係者で共有しておくことが重要です。
3-2. 寄与度の不均衡
同居する子と、遠方に住む子では、それぞれの親への負担や貢献度に差が出る場合があります。双方が「自分の方が負担した」と感じると、均等分割に不満が出ることがあります。
予防策:生前から親への貢献度をきょうだい同士で共有し、相互理解を図ること。また、親に感謝の気持ちや遺産分割の意向を遺言に残してもらうことが有効です。
3-3. 不動産しか財産がない
実家だけが財産の場合、相続を巡って意見の食い違いが起きることがあります。
予防策:遺言を作成してもらう、生命保険を活用して代償金を用意するなどの対策が効果的です。
3-4. 生前贈与・遺言が不公平
生前贈与や遺言で一部のきょうだいに多くの財産が渡る場合、不公平感からトラブルが発生することがあります。
予防策:贈与や遺言の理由を明記した書類を残すこと。可能なら、生前にきょうだい全員で話し合う機会を設けるのが望ましいです。
3-5. 音信不通や知らないきょうだいの存在
音信不通のきょうだいや、存在を知らなかったきょうだいが現れることで、相続トラブルに発展するケースがあります。
予防策:戸籍をさかのぼって確認することや、遺言書を作成してもらうことで、連絡の取れない相続人がいてもスムーズな手続きが可能になります。
3-6. 配偶者が関わる
きょうだいの配偶者が相続に口を挟むことで、感情的な対立が生まれることがあります。
予防策:両親の生前から配偶者も交えて話し合い、一定の方針を共有しておくと良いでしょう。
4. トラブルが起きた場合の対処法
問題が起きた際は、まず情報を開示し、冷静に話し合うことが重要です。それでも解決が難しい場合、弁護士に相談したり、家庭裁判所で調停や審判を活用するのがおすすめです。
5. まとめ
きょうだい仲が良くても油断せず、生前から意思疎通を図り、必要に応じて遺言書を作成してもらうことが大切です。また、問題が大きくなる前に専門家に相談し、円満な解決を目指しましょう。

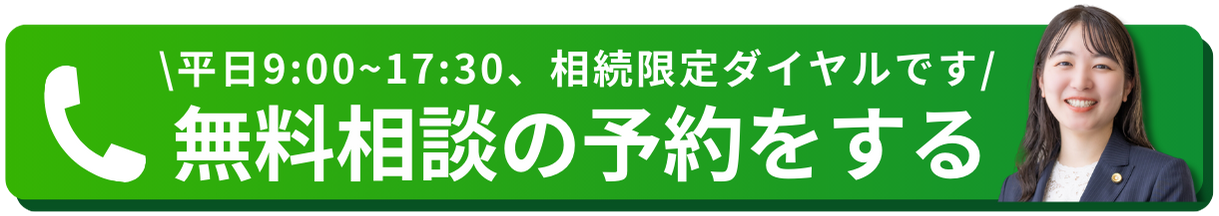

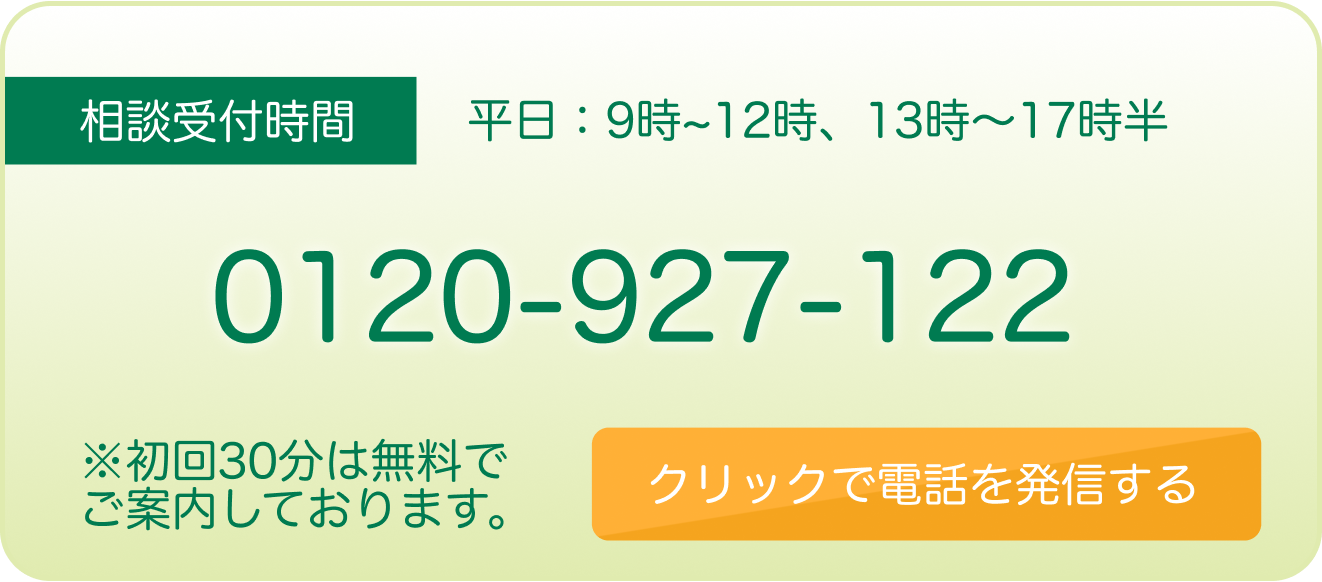
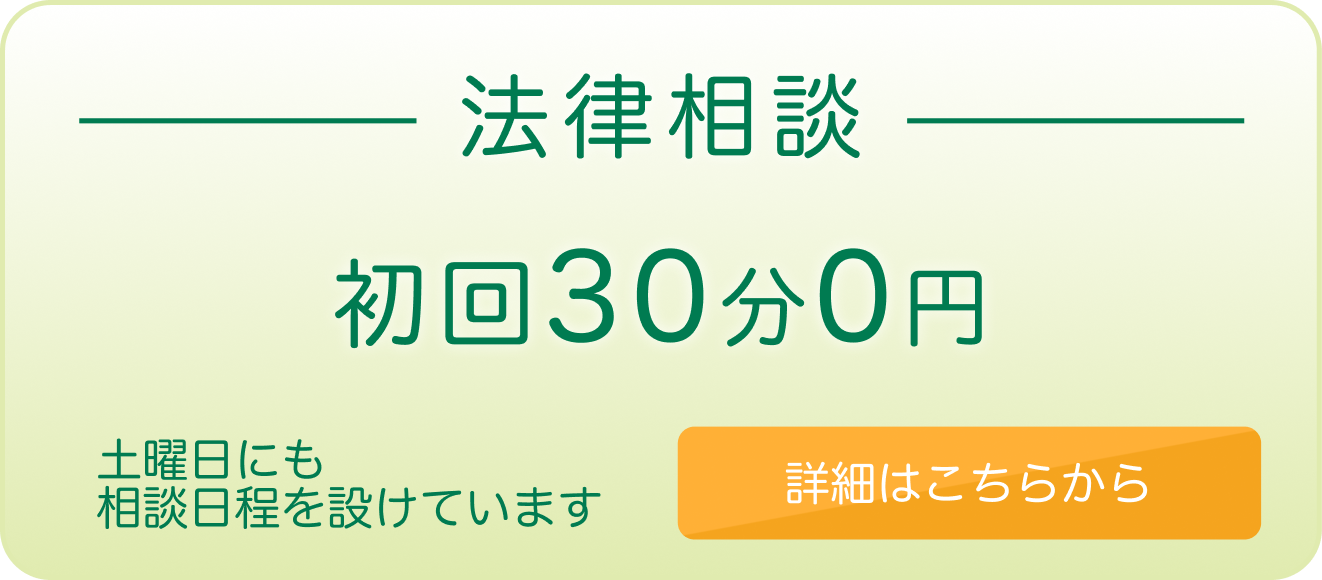
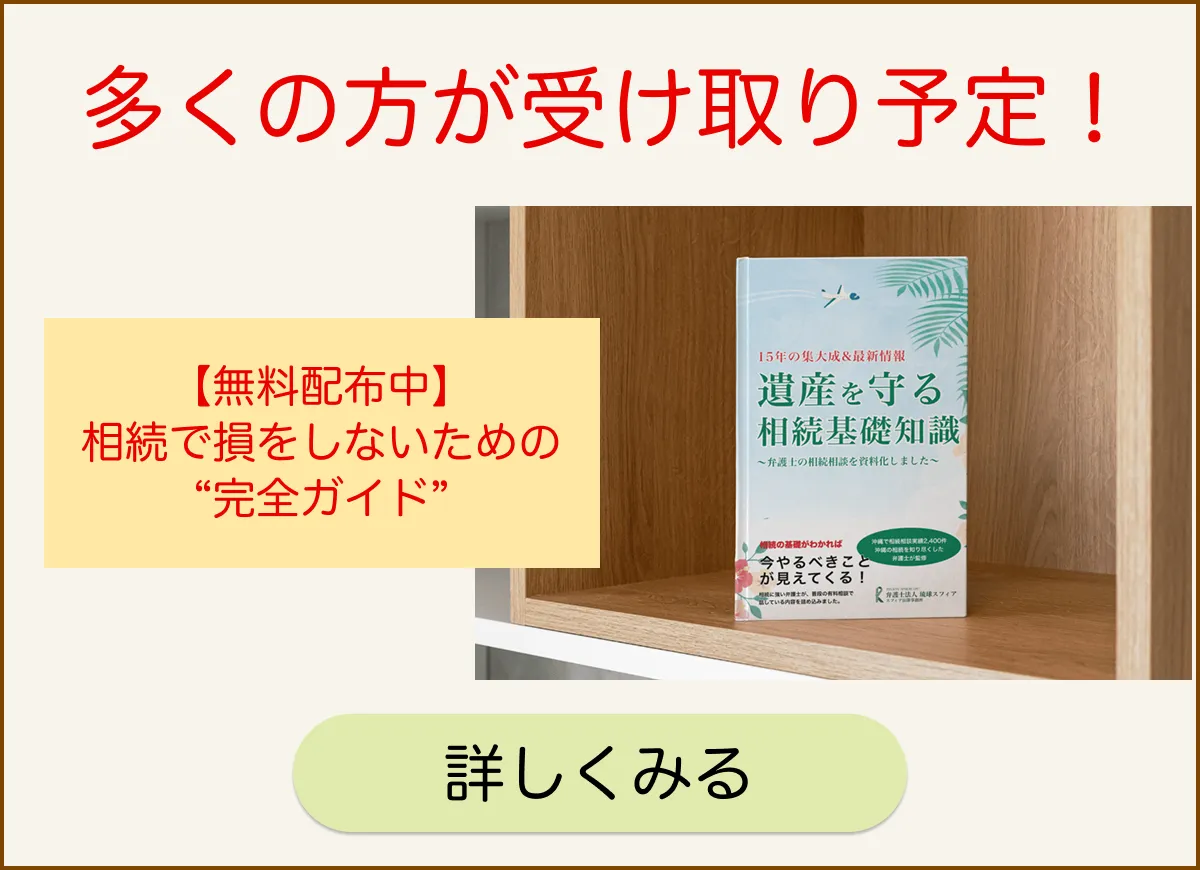
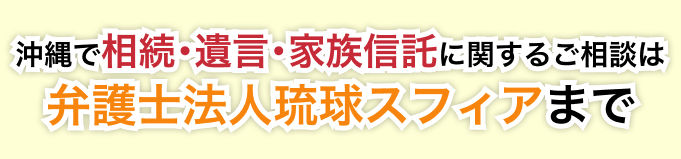

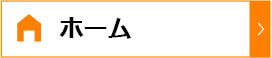
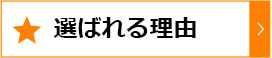
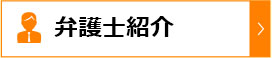
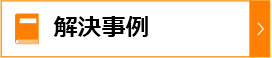
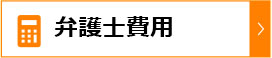
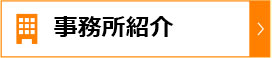

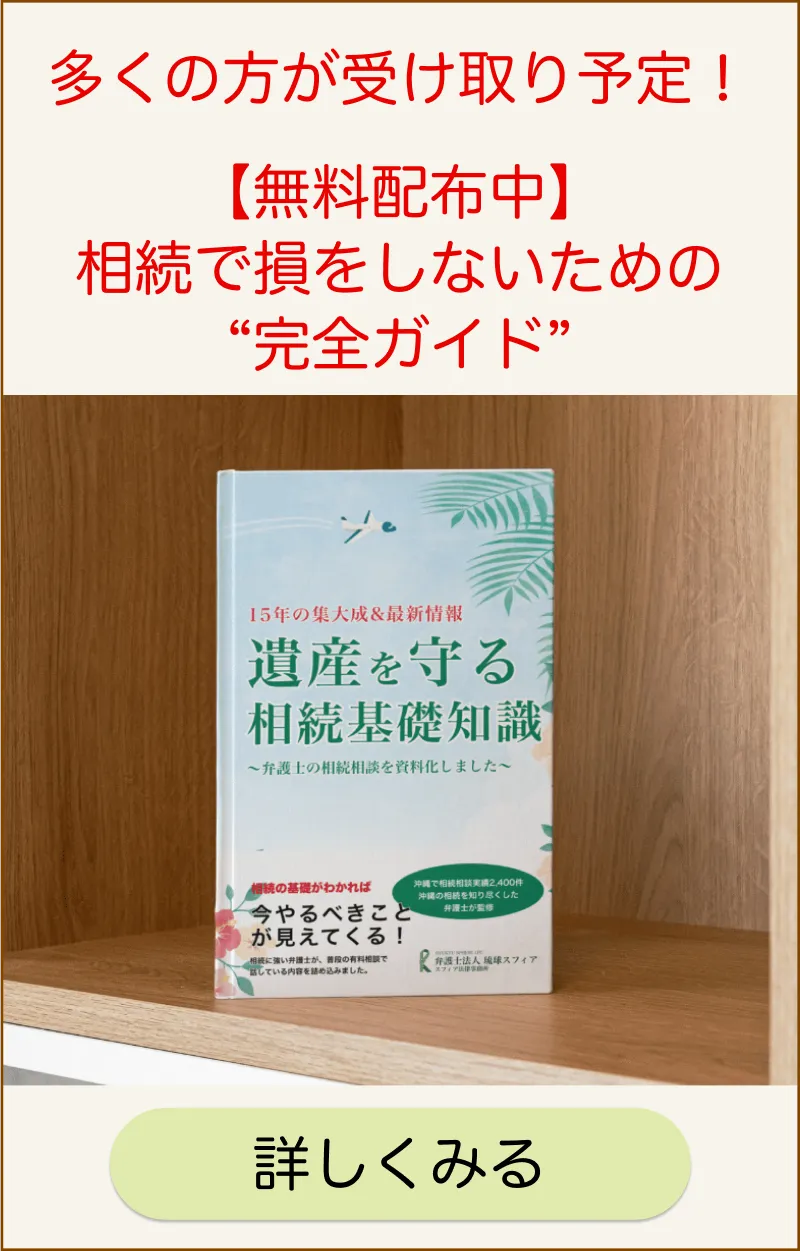

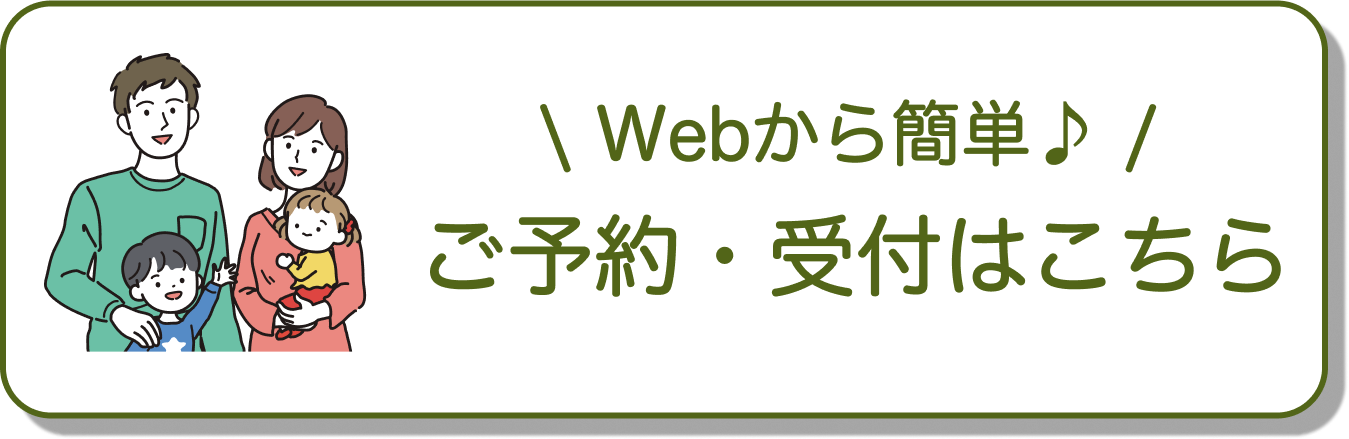


.png)
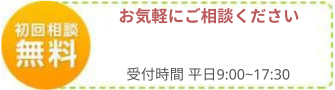
.png)