不動産相続の分割方法から登記手続の必要書類まで解説
 不動産相続の基本的な手続きの流れ
不動産相続の基本的な手続きの流れ
不動産を相続する際の手続きは、以下のステップに沿って進めます。
- 遺言の有無を確認
不動産を相続する際、まず最初に行うべき手続きは、亡くなった方の 遺言書があるかどうかの確認 です。遺言書が見つかれば、基本的にその内容に従って相続手続きが進みます。これにより、遺産の分け方や相続人の役割が明確になり、手続きがスムーズに進むことが期待できます。一方、遺言書が見つからない場合、 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を話し合う必要があります。ただし、遺産分割協議が完了した後に遺言書が発見されるケースもあります。この場合でも、遺言書の内容が優先されるため、協議内容を再検討する必要が生じる可能性があります。そのため、後の手間や混乱を避けるためにも、 遺言書はできる限り早い段階で探し出す ことが重要です。
遺言書が保管されていそうな場所(自宅、金庫、信託銀行など)や公正証書遺言の有無を含め、徹底的に確認しておきましょう。 - 相続人を確定
遺言書がない場合、亡くなった方の財産は 法律で定められた相続人 に分配されます。そのため、まず 誰が相続人になるのかを確定すること が必要です。これは、後々のトラブルを防ぐためにも非常に重要なステップです。相続人を確定するには、亡くなった方の 出生から死亡までの戸籍謄本を収集 し、その記録から親族関係を正確に調べます。この作業により、相続人の範囲が明らかになります。注意すべき点は、 新たな相続人が後から発覚した場合 です。このような場合には、一度決まった遺産分割協議をやり直す必要が生じます。特に、遠方に住んでいる親族や疎遠になっている親族がいる場合には、漏れがないよう細心の注意を払いましょう。
また、相続人が確定した後でも、 特定の親族が相続を放棄するかどうか が分からない場合もあります。これらの情報を確実に把握したうえで、スムーズに次の手続きを進められるよう準備することが大切です。
- 相続財産がどれくらいあるのか把握(財産目録の作成)
相続財産の特定は、スムーズな遺産分割協議を進めるために欠かせない作業です。これには、 財産目録(相続財産のリスト) を作成し、財産の全体像を把握することが重要です。
【預貯金の場合】
・通帳や残高証明書 を確認し、亡くなった時点の残高を把握します。
・銀行から必要な情報を取得する際には、相続関係を証明する書類が求められることがありますので、事前に準備しておきましょう。
【不動産の場合】
・固定資産税の納税通知書 から所有している不動産を確認します。
・権利証(登記識別情報通知や登記済証) を探して、不動産の詳細情報を確認します。
・名寄せ制度 を利用すると、市区町村内で所有する不動産を一覧で確認できます。
・2026年2月2日以降 は、法務局の「所有不動産記録証明制度」により、全国の所有不動産を一括してリストアップできるようになります。
【その他の注意点】
・借金や未
- 遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、不動産の分け方や所有者を決定します。協議内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の署名と押印を行います。以下のポイントを押さえて進めましょう。
【協議の進め方】
・相続人全員の参加が必須
相続人が一人でも欠けた状態で協議を行うと、その分割協議は無効となります。
・不動産の引き継ぎ先を決定する
不動産を誰が相続するかを相続人全員で話し合い、合意を得る必要があります。
【遺産分割協議書の作成】
・協議がまとまったら、遺産分割協議書 を作成します。
・遺産分割協議書には、協議内容を詳細に記載します。
・記載ミスや抜け漏れがないように注意しましょう。署名と実印の押印
・遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印します。これにより、協議書が正式なものとなります。
【注意点】
・協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停や審判を申立てることも可能です。
・不動産の分割方法について専門的な判断が必要な場合には、不動産鑑定士や弁護士に相談するとよいでしょう。
遺産分割協議書が完成したら、それを基に不動産の相続登記やその他の手続きを進めます。
- 相続登記の申請
不動産を引き継ぐ人が決まった後は、不動産の名義を相続人の名義に変更する手続き、相続登記 を行う必要があります。これは不動産を正式に相続するための重要な手続きです。不動産を相続する場合、法務局で相続登記を行い、所有者名義を変更します。なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されており、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続税の申告・納付の基礎ポイント
遺産に不動産が含まれる場合、総額が基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えると、相続税が課税されます。相続税の申告と納付の期限は、**「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」**と定められています。
【注意点】
・期限内に申告・納付を完了しないと、延滞税やペナルティが課される可能性があります。
・不動産は評価額の計算が複雑になることが多いため、早めに財産評価を進めることが大切です。
【対策】
・必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産の評価証明書など)を早めに揃えましょう。
・不動産の評価方法や控除の適用範囲を正確に把握するため、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。
・納税が困難な場合は、延納や物納などの制度を活用することも可能です。
・時間的な余裕がない場合は、専門家に依頼することでスムーズに進められます。計画的な対応が相続税負担を軽減する鍵となります。
相続した不動産の分け方(3つの主要な方法)
不動産の相続には、分割方法によって異なるメリットや注意点があります。ここでは、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法を具体例を交えて解説します。

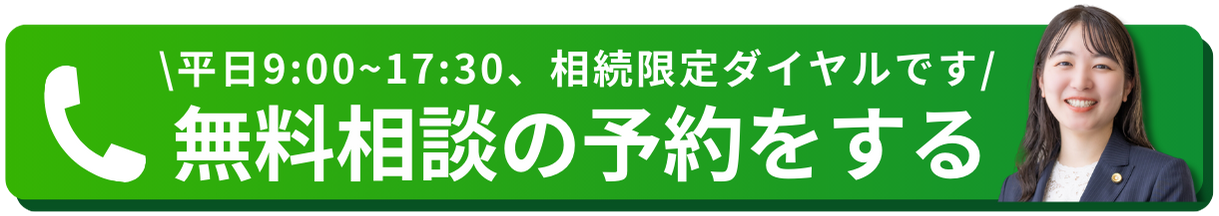
-4.png) 不動産相続の基本的な手続きの流れ
不動産相続の基本的な手続きの流れ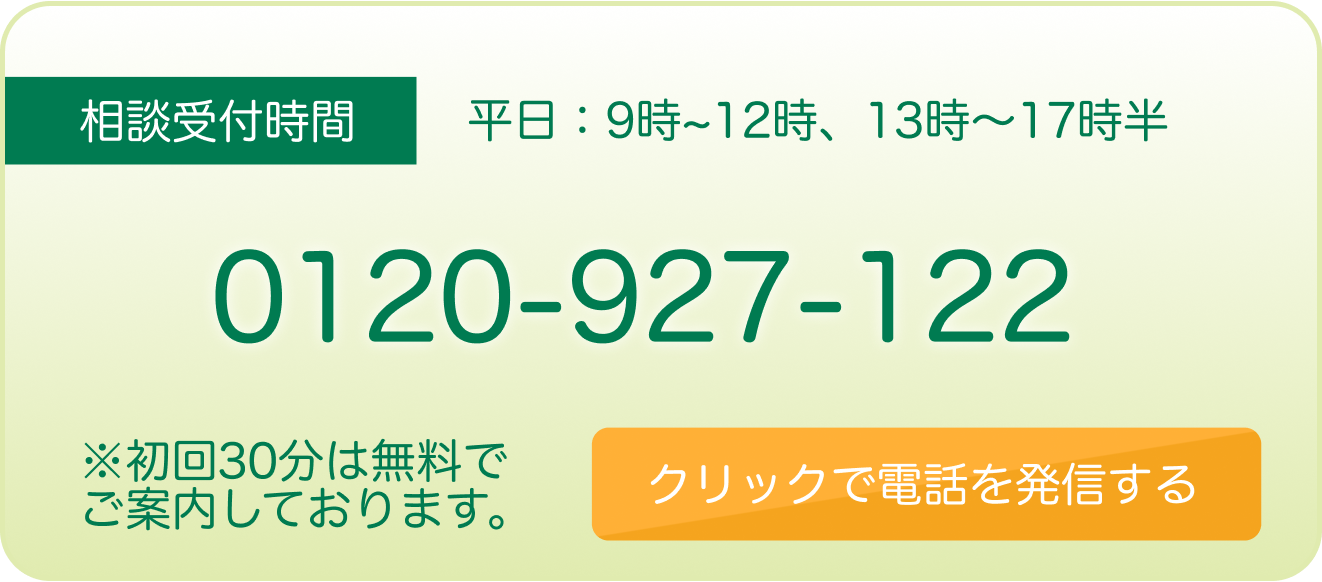
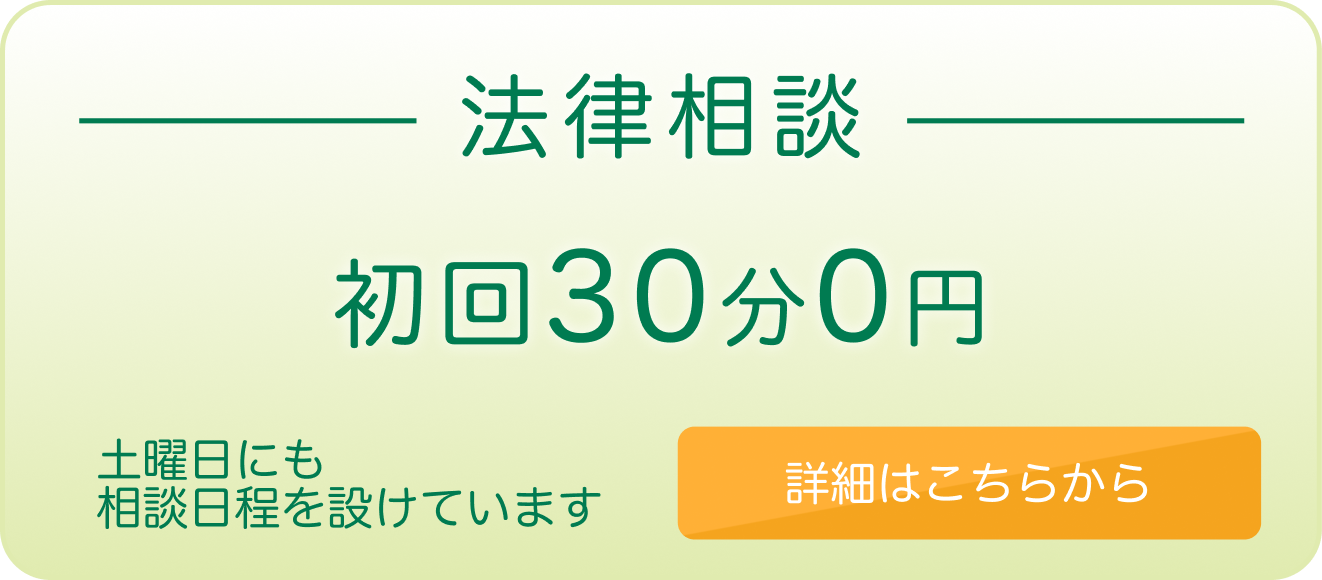
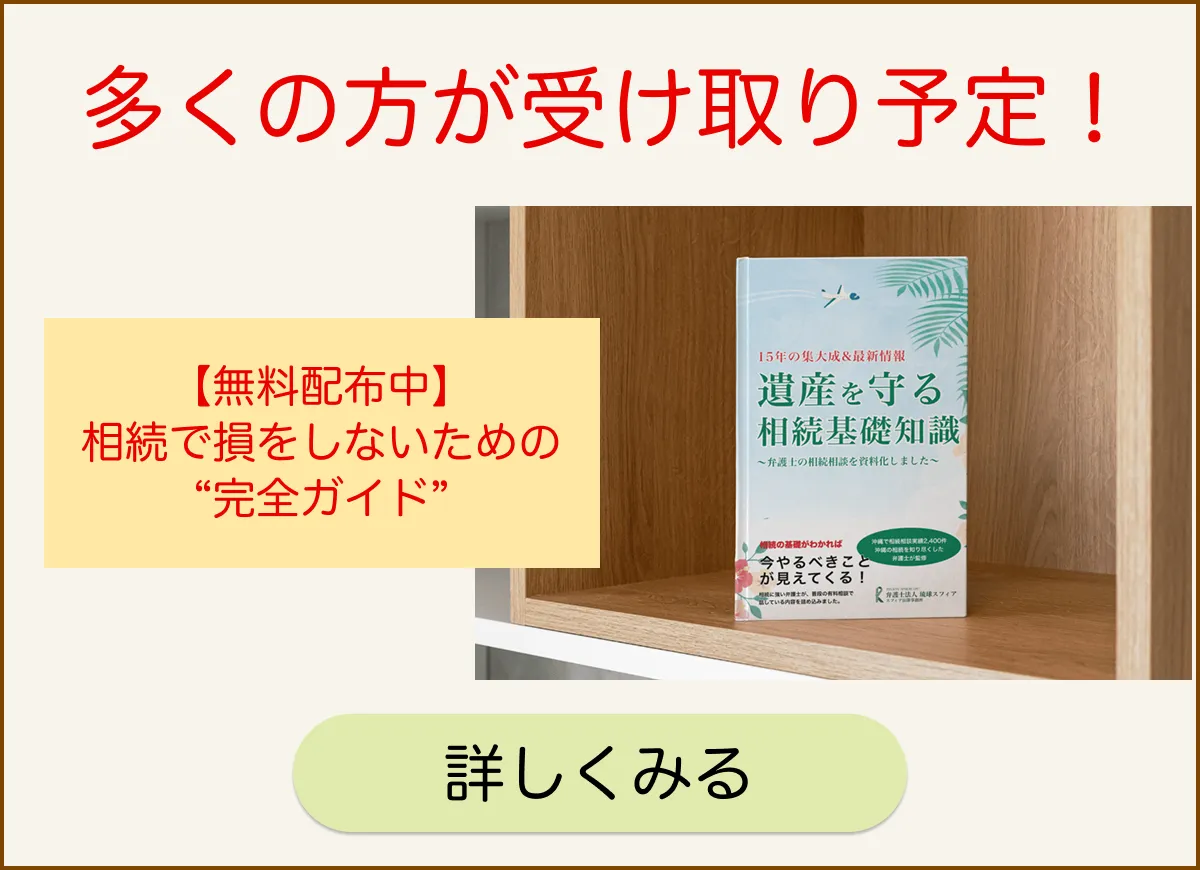
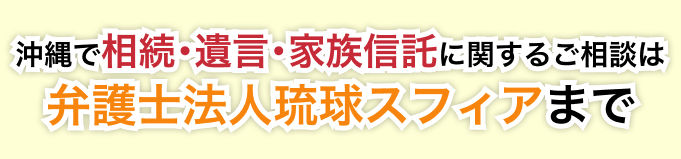

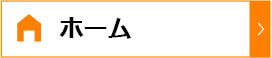
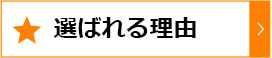
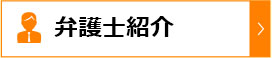
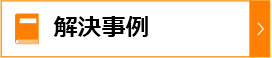
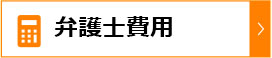
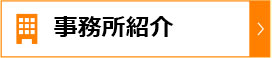

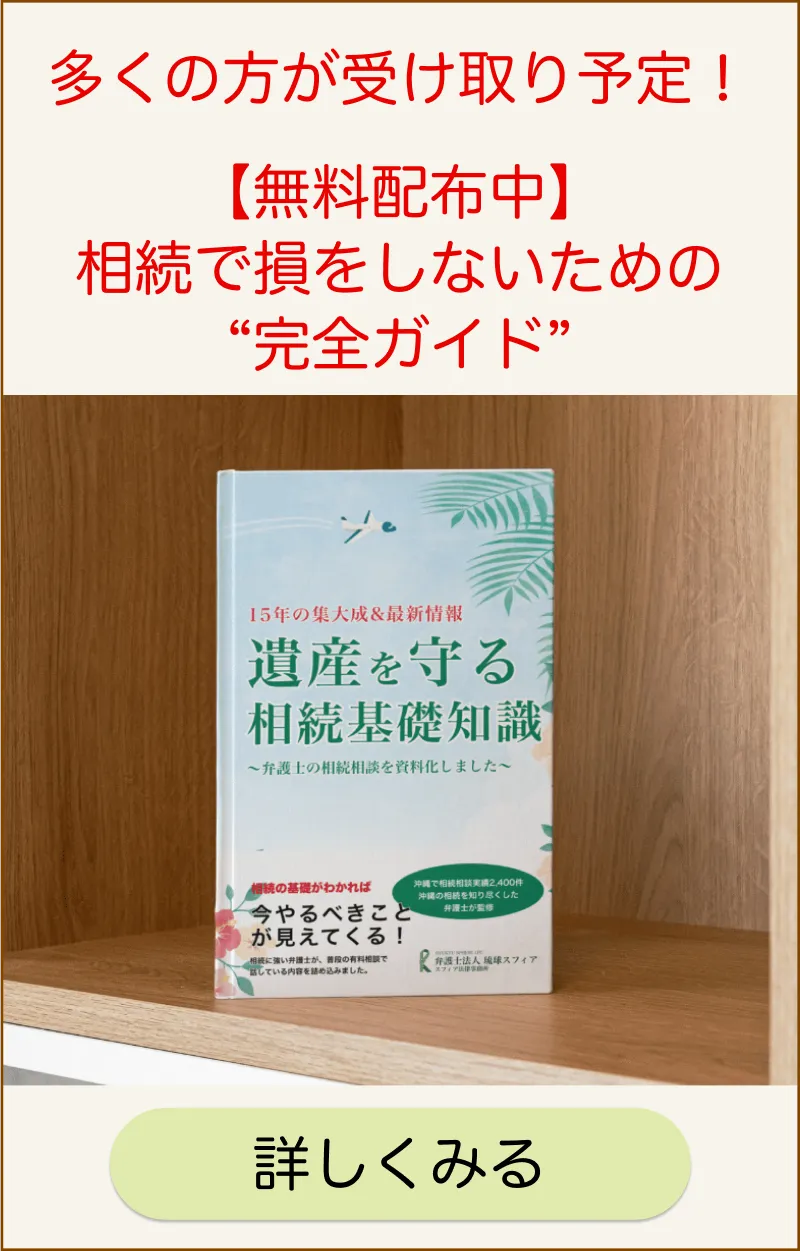

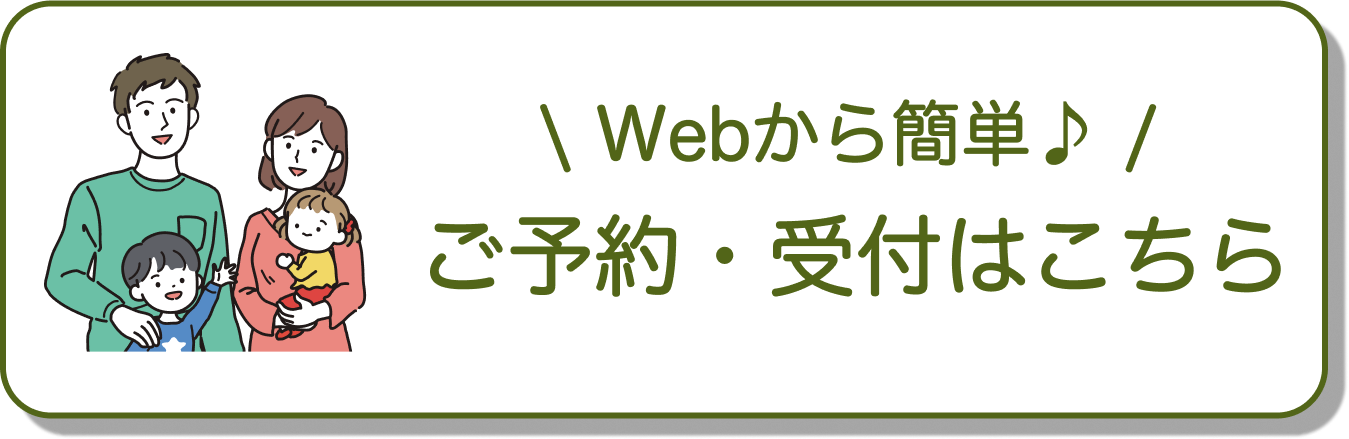


.png)
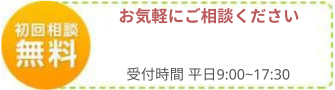
.png)