【解決事例】兄が寄与分と法事費用を主張したが、法定相続分での分割により調停が成立したケース
■ クライアント情報
40代・男性(次男)
被相続人:父
相続人:兄・本人(次男)・弟の三兄弟
■ 問題となっていた事柄
父の死後、三兄弟間で遺産分割調停を行っていたところ、弟が自身の相続分を次男(当職の依頼者)に譲渡。これに対して長男が強く反発し、「自分には寄与分がある」として主張を開始。調停が長期化する兆しを見せた。
■ 争点
長男は以下の点を主張し、自身の取り分を増やすよう求めた
- 家督を継ぐ者として祭祀を承継し、法事などを一貫して行ってきた
- 長男である自分は大学進学を諦めて働き、当時の給料を全額家に入れていたとして、5千万円の寄与分を計上
- 被相続人と同居していたこと、法事費用として3百万円を自分が負担したと主張
一方、当職の依頼者(次男)および弟は、これらの寄与分が法定上評価される特別の寄与には該当しないと主張し、争点となった。
■ 弁護士が介入した結果
調停において、長男の主張内容について以下のように整理された
- 祭祀承継や法事実施については、寄与分として評価することは困難
- 大学進学の断念や給与の提供は美談であるが、相続財産の形成・維持への具体的貢献としての立証が弱く、寄与分には該当しない
- 法事費用3百万円については、領収書等の証拠がなく、また相続財産の形成や維持との関連性が認められない
結果として、調停委員も長男の寄与分主張を認めず、法定相続分での分割を基本とした調停案が提示された。
次男が譲渡を受けた弟の持分も含めて、兄弟間での最終的な合意が成立し、無事調停は終了した。
■ 解決のポイント
- 寄与分の主張には、客観的な裏付けと法的要件の充足が不可欠であり、感情的・道義的な主張だけでは通らない
- 祭祀や法事は寄与分として評価されにくい領域であり、調停でも判断はシビアになる
- 弁護士が間に入ることで、冷静に事実と法律を整理し、感情的な対立を最小限にとどめて調停解決に導くことができた

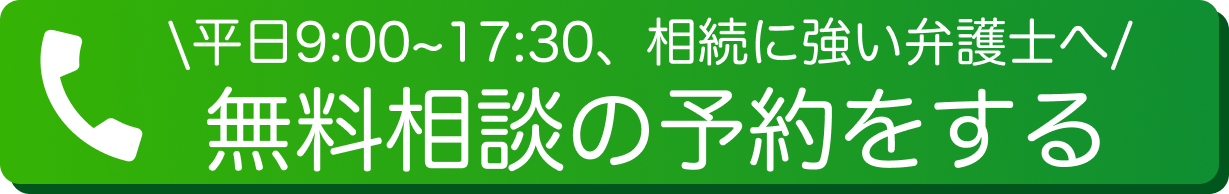
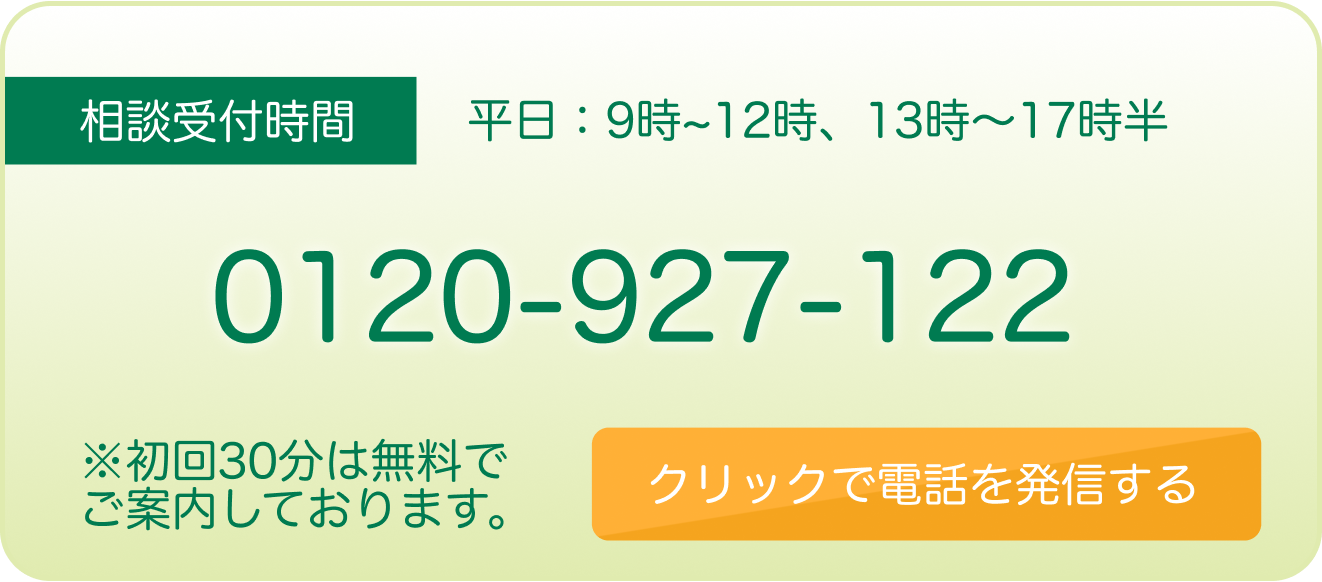
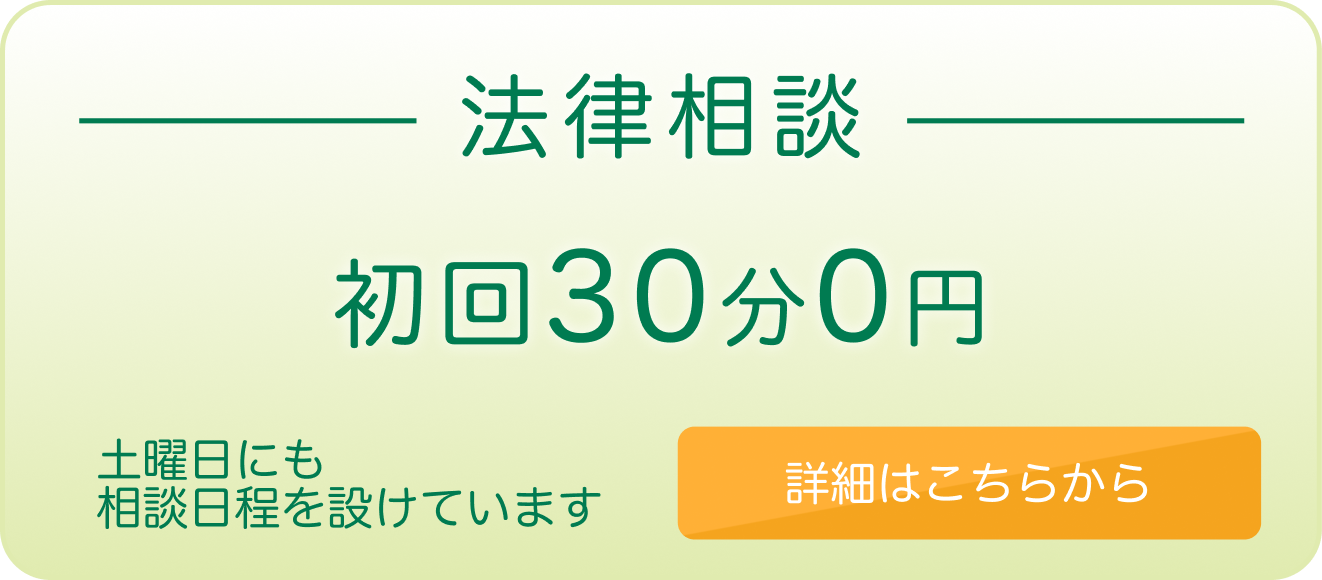
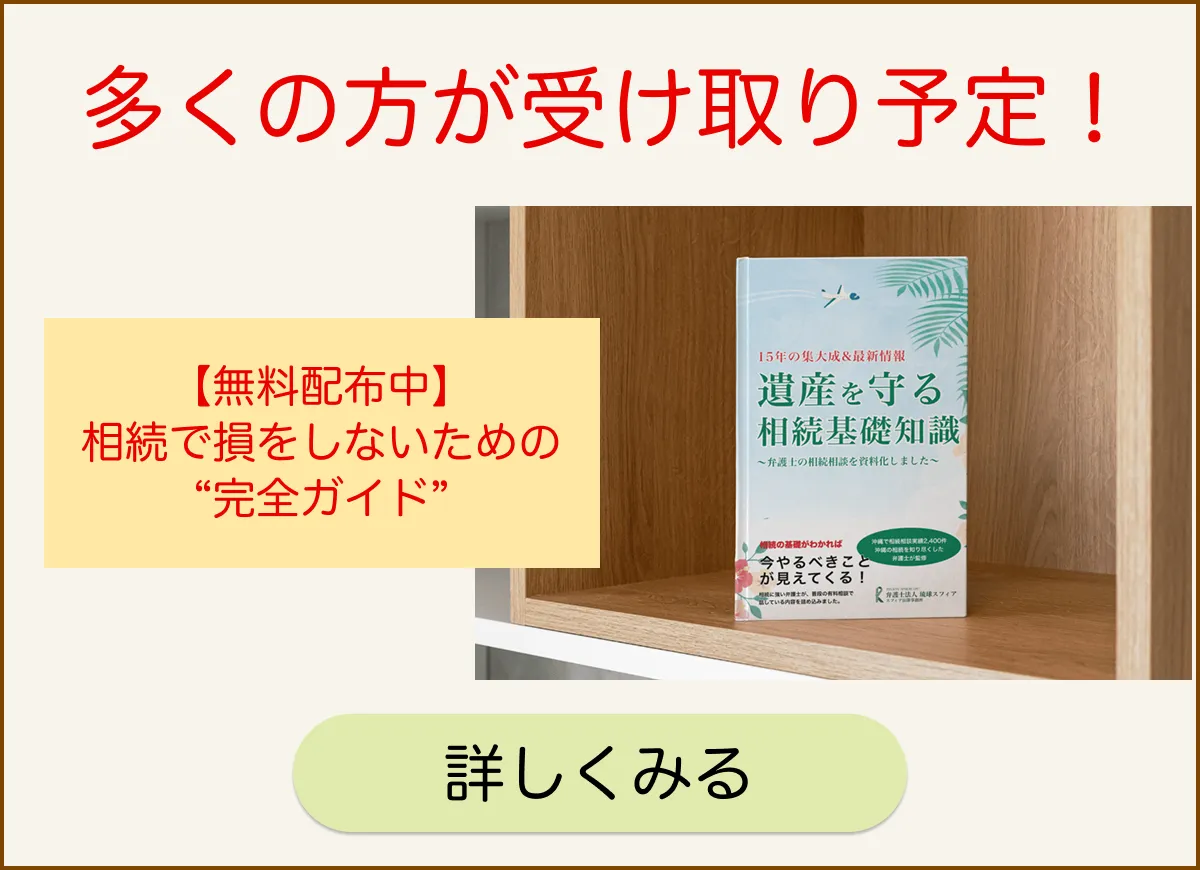
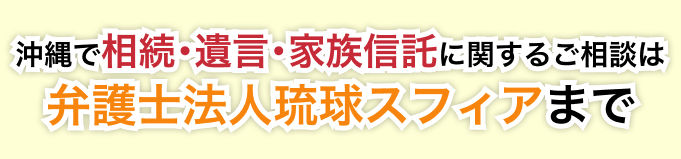

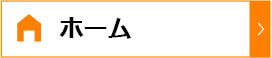
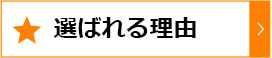
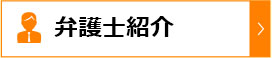
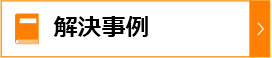
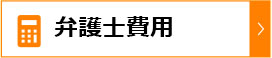
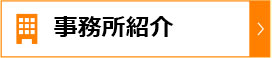

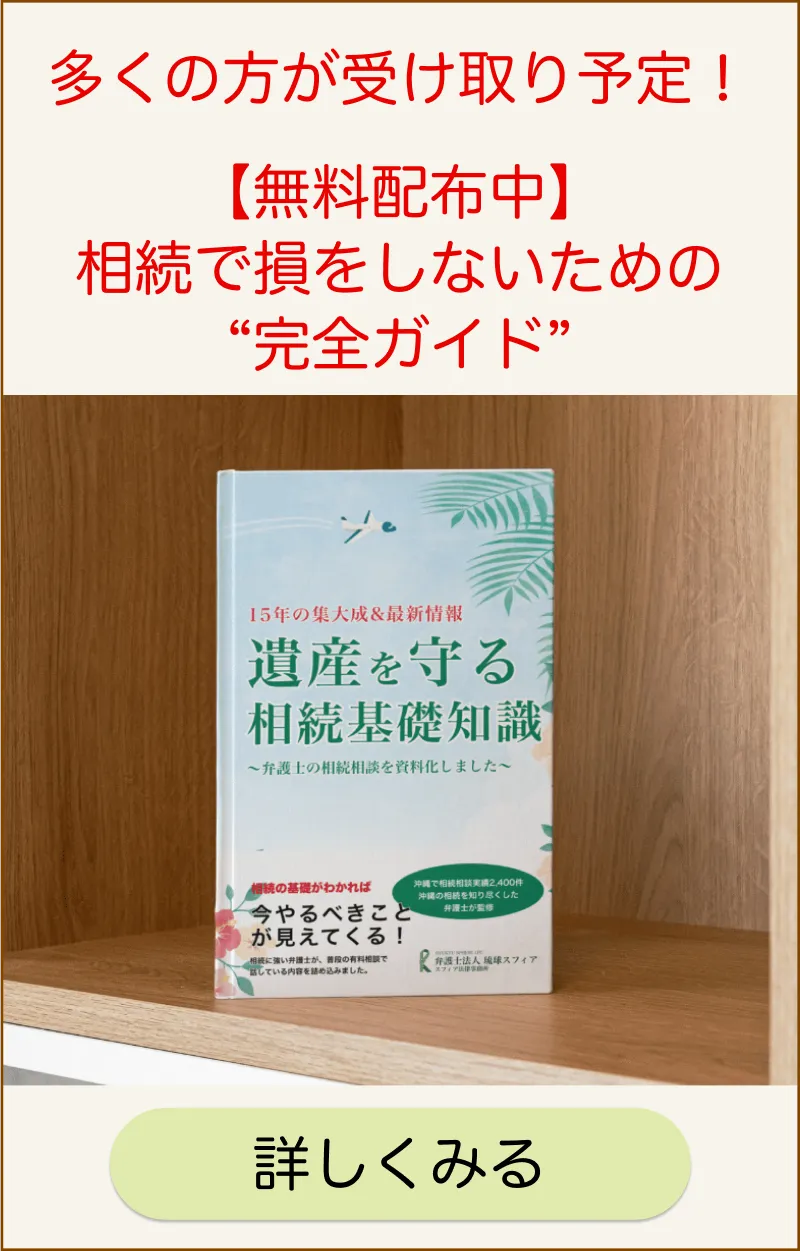

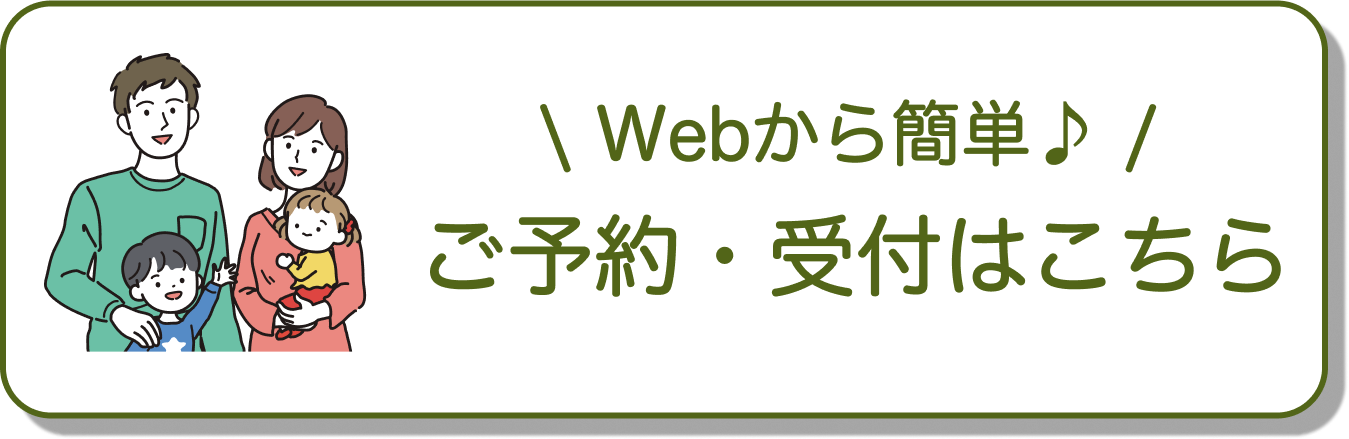


.png)
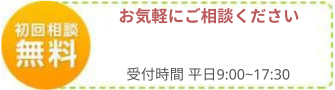
.png)