遺産分割協議のやり方講座!しっかりと相続するためのコツを沖縄の弁護士が解説

1、遺産分割協議書、ハンコを押す前に考えること
遺産分割協議が完了した後で、「こんな内容で合意しなければよかった」と後悔する方は少なくありません。特に、以下のような内容が含まれている場合は、ハンコを押す前に弁護士に相談することをお勧めします。
1-1. 不動産の評価が固定資産税の評価額となっている場合
遺産分割協議において、不動産が固定資産税の評価額で評価されていることがあります。特に、弁護士以外の専門家(税理士や司法書士)が作成した協議案には、そのようなケースが多いです。
しかし、固定資産税の評価額は、市場で取引される不動産の実際の価値、特に土地や軍用地などの場合には、非常に低く設定されていることがほとんどです。そのため、固定資産税評価額を基準にした遺産分割協議案には注意が必要です。不動産の正確な価値について詳しい弁護士に相談してみてください。
1-2. 預貯金の分け方が金額で記載されている場合
たとえば、「A銀行の口座○○の預金1000万円のうち、300万円は長男へ、残り700万円は次女へ」というように、具体的な金額で記載されている場合、銀行で預金を解約できないことがあります。
なぜなら、遺産分割協議が成立した後も、銀行預金の残高は日々の利息などで変動するためです。この場合、再び相続人全員と連絡を取り、預金引き出しに必要な書類に署名や押印をしてもらう必要が出てきます。
こうした問題を避けるためには、金融機関において他の相続人を巻き込まずに引き出せるような文言を盛り込んだ遺産分割協議書を作成することが重要です。このようなテクニックを駆使できる弁護士に相談することをお勧めします。
1-3. 生前贈与が正しく反映されていない場合
生前に親から多額の預金を受け取っている人や、軍用地を購入してもらった人、家を建ててもらった人など、特別な利益(特別受益)を受けている相続人もいます。
これらの特別受益が考慮されていない遺産分割協議書が作成されると、相続人の間で数千万円単位で損失が生じる可能性もあります。
1-4. 死後に発生した費用を考慮していない場合
相続が発生した後(被相続人の死亡後)に支払われた固定資産税や火葬費用などの費用が遺産分割に考慮されていない場合、これらの費用を負担した相続人が不満を持ち、相続トラブルが再燃することがあります。
こうした費用の負担をどうするかについては、専門の弁護士に相談するのが良いでしょう。
1-5. ハンコを押しても後から無効にできる?
遺産分割協議書に一度ハンコを押してしまうと、裁判で覆すのは非常に困難です。そのため、不利益を被る可能性がある場合や、後々紛争が再燃するリスクがある場合には、遺産分割協議書にハンコを押す前に一度弁護士に相談することを強くお勧めします。
2、遺産分割の話し合いはなぜ紛争になりやすいのか
遺産分割の話し合いが始まると、仲の良かった兄弟姉妹の関係が険悪になることがあります。これは、家族という密接な関係性があるがゆえに、不満や不平を直接ぶつけやすいからです。
例えば、「兄は親からこんなに支援を受けていた」とか「家を建ててもらった」など、相続の分割に影響する事実に加え、「親に暴言を吐いた」とか「葬式に来なかった」など、遺産分割には関係のない過去の出来事までが持ち出されることがあります。このように、当事者間で関係ある話とない話が混在し、気がつけばお互いの批判合戦になってしまうことが少なくありません。
また、親(被相続人)から他の相続人が生前にどれだけの支援を受けたかについて、家族であっても詳細な金額までは知っていることは少ないです。このため、何かを隠していると感じられたり、実際に隠していたりすると、それが原因で協議が進まなくなったり、争いの火種となることがあります。特に、相続の場面では、相手が自分より多くの支援を受けているのではないか、あるいは多くの財産を引き出しているのではないかと疑いを持ちやすいものです。そのため、少しでも隠し事があると、相手がさらに多く得ているのではないかと不安や不信感が募るのです。
では、具体的にどのようにすれば円滑に遺産分割の話し合いができるのでしょうか。
3、遺産分割の具体的な手順
3-1. 相続人の範囲を確定する
⑴ 戸籍の取り寄せと相続人の確認
まず、相続人が誰であるかを確認する必要があります。被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を、市役所などで取得します。
場合によっては、複数の自治体(県外など)から戸籍を取り寄せる必要があります。また、相続手続きの段階で戸籍を取り寄せた際に、被相続人が再婚していたり、別の子供を認知していたりして、知らなかった兄弟姉妹が判明することもあります。このような調査は、当事務所でも代行しています。
⑵ 相続人の住所確認
戸籍を取り寄せて相続人を特定した後でも、相続人の住所がわからない場合があります。その際には、戸籍の附表を取得して相続人の現住所を確認します。このような方法で相続人の所在を突き止めることが可能です。
ただし、自分で調査するのは非常に難しい場合があるため、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めします。当事務所では、遺産分割の前提として、相続財産や相続人の調査も行っています。
◆行方不明の相続人がいる場合の対処方法
遺産分割の協議は、すべての共同相続人が参加しなければ有効ではありません。そのため、行方不明の相続人がいる場合には、通常の分割協議を行うことはできません。
このような場合には、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるか、失踪宣告を受けることが考えられます。これらの手続きにより、行方不明者がいる状況でも適切な遺産分割を進めることが可能です。
3-2. 被相続人の財産をすべて開示する
まず、被相続人の財産を一覧にまとめ、相続時点での評価額を記載したリストを作成します。預貯金、現金、不動産、株式、出資金など、すべての財産をリストアップすることが重要です。
⑴ 預貯金
相続財産の基準となるのは、亡くなった時点での預貯金残高です。ただし、実際に分割する際には、現在の預貯金残高を基にします。相続人全員で通帳を記帳し、亡くなった後に支払われた固定資産税、火葬費用、葬儀代、不動産の維持費(電気代、ガス代など)について、誰が負担するかを協議し、負債として計上することが必要です。
また、被相続人の生前の預金を生活費として管理していた相続人がいる場合、その情報もできるだけ開示することが望ましいです。これを隠していると、トラブルの原因になります。被相続人のために使った金額についてもきちんと説明することが、後々の争いを避けるポイントです。
⑵ 不動産
不動産に関しては、名寄帳(なよせちょう)を取得すると、物件の詳細な所在地まで確認できます。不動産の評価は時価で行うのが一般的です。不動産会社に査定を依頼するのが良い方法ですが、信頼関係のない不動産会社だと断られることもあります。
当事務所では、相続に関する案件を多く取り扱っているため、不動産の所在地からおおよその市場価値を相談時にご案内することができます。また、提携している不動産会社に依頼し、市場価値の査定を行うことも可能です。
不動産の評価方法や分割の仕方によって、遺産分割の内容や相続人が受け取る財産の額が大きく変わることがあります。そのため、遺産分割を検討している方は、専門家である弁護士に一度相談することをお勧めします。
⑶ 負債の整理
負債も財産と同様にリストアップし、遺産分割の際に協議することが重要です。不動産の固定資産税や被相続人の未払いの所得税なども含めて、負債リストを作成します。
なお、負債の方が相続財産を上回る場合、相続放棄を検討することも必要です。相続放棄は亡くなった日から3ヶ月以内に行う必要がありますので、その点も考慮に入れてください。
3-3. 相続人の範囲、順位、相続持分の確認
相続人の範囲、相続順位、そして相続持分の割合を確認するために、相続人の調査を行います。これは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を市役所で取得し、それを基に相続人を特定するプロセスです。
戸籍は結婚時に新しく作成されたり、住所の移動が多い場合には複数の自治体から取得する必要があることもあります。当事務所では、こうした相続人の調査も承っておりますので、ぜひご相談ください。
3-4. どうしても必要な不動産を先に分ける
相続人ごとに、まず必要な不動産を分けます。沖縄では、伝統的に「トートーメー」が入った家を長男が相続する習慣がありますが、この風習にこだわると遺産分割が難航する場合もあるため、弁護士に相談することをお勧めします。使わない不動産については早期の売却が望ましいです。特に、建物の耐用年数を超えると売却が難しくなるため注意が必要です。ただし、沖縄では先祖代々の土地を売ることに反対する親戚がいることも多いですので、「トートーメー」に関しては専門の弁護士に相談することが賢明です。
※特に軍用地のような不動産がある場合、固定資産税評価額で分割するのはお勧めしません。実際の市場価値と大きく乖離するためです。
3-5. 残った財産の分割
不動産を相続して多くの財産を得た人は、代償金を支払ったり、負債を引き受けるなどして、他の相続人と公平な分配を心がけます。ただし、不動産のみが主な相続財産の場合、代償金を支払うことが難しいケースもあります。その場合は、不動産を売却し、その代金を分ける「換価分割」が選択肢となります。
3-6. 遺産分割協議書の作成(ハンコを押す前に注意!)
遺産分割協議書は、相手方が用意したものにすぐハンコを押してしまう方もいますが、これは非常に危険です。税理士が作成した場合でも、後から不満が出ることがあります。いったんハンコを押してしまうと、協議書を覆すのは極めて困難です。したがって、必ずハンコを押す前に弁護士に相談してください。当事務所では、初回30分の無料相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
4、当事者同士の話し合いによる遺産分割のリスク
遺産分割を当事者同士で行うことは可能ですが、以下のようなリスクがあります。
4-1. 兄弟間の関係が悪化する
遺産分割の話し合いでは、関係のない過去の問題を持ち出し、感情的になることが多く、これが原因で兄弟間の仲が悪くなるケースが多々あります。
4-2. 不動産の価値を正確に把握できず、損をする可能性がある
不動産の評価額は、固定資産税の評価額や税務申告の価値とは異なり、実際の市場価値と大きく乖離することがあります。特に軍用地はその差が顕著で、正確な市場価値を知らずに遺産分割を進めると、大きな損失を被ることがあります。
4-3. 分割方法がわからず、争いが長引く
不動産の適切な分割方法には専門的な知識が必要です。市場価値や売却の可否についての知識がないと、具体的な分割方法を決められず、遺産分割がまとまらずに長期化することがあります。
4-4. 有効な遺産分割協議書の作り方がわからない
遺産分割後に新たな財産が見つかった場合や、代償金の支払い、銀行預金の払い戻し方法、固定資産税の精算方法など、専門的な表現や設計が必要です。これらが不適切だと、せっかくまとまった協議が無効になったり、思わぬ手間が発生したりします。
4-5. 遺産分割調停に進むとさらに時間がかかる
調停は個人でも申し立てが可能ですが、手続きには非常に時間がかかります(1~2年程度)。また、戸籍や登記の準備、話し合いへの参加など、多くの時間と労力を要します。
4-6. 意見が通りにくい人が不利益を被る
当事者同士の話し合いでは、意見が通りにくい人が不利な条件を押し付けられることがあります。特に沖縄の遺産分割では、「嫁に行った女性には相続権がない」や「長男が優先」という考え方が根強く、女性や他の相続人が不当に損をするケースが少なくありません。
5、弁護士に遺産分割協議を依頼するメリット
5-1. 兄弟間の感情的な対立を避けられる
弁護士を代理人に立てることで、遺産分割協議では必要な主張(例えば、軍用地の評価や生前贈与の考慮など)のみを伝え、相手からの感情的な発言をブロックすることができます。これにより、当事者同士で直接話し合う場合に比べて、より円滑に遺産分割を進めることができます。
琉球法律事務所の解決事例
→【遺産分割】長男からの攻撃をブロックし、法定相続分通りの遺産を獲得できた事例
5-2. 不動産処分や遺産分割の具体的な提案ができる
弁護士は遺産分割に関する豊富な経験を持っているため、調停まで進んだ場合のシナリオや、不動産を売却した場合の結果、分筆を行った場合の影響など、さまざまな解決策や見通しを提供できます。そのため、当事者同士で争うよりもスムーズで納得のいく遺産分割方法を提案することが可能です。
琉球法律事務所の解決事例
→【遺産分割】一棟のアパートを区分所有にして遺産分割し解決した事例
5-3. 相続人の特定や不動産評価などの手間を省ける
遺産分割には、相続人の特定や預貯金・不動産の価値の調査が必要です。これを個人で行う場合、会社を休んで市役所を回ったり、不動産会社を探したりと、多大な手間がかかります。弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きから解放されます。
5-4. 法的に有効な遺産分割協議書を作成できる
弁護士に依頼することで、法律的に有効で問題のない遺産分割協議書を作成することができます。これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
5-5. 発言が通りにくい人でも公正に扱われる
当事者同士での協議では、控えめな人や意見が通りにくい人が不利な状況に追い込まれることがあります。しかし、弁護士を代理人に立てることで、全ての相続人の意見が公平に考慮され、親族間の感情的な対立も避けることができます。声の小さい人の意見も適切に代理し、相手にしっかりと伝えることができます。
遺産分割でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

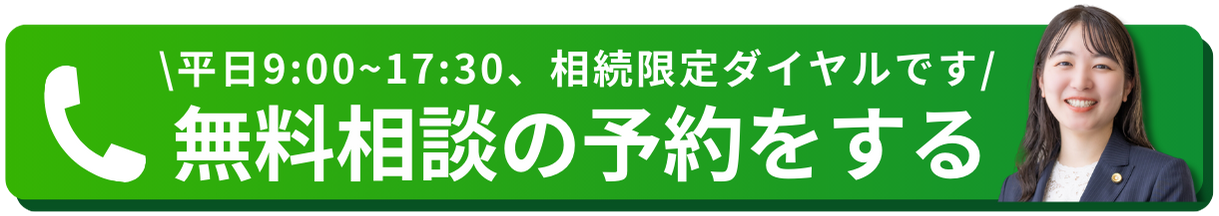

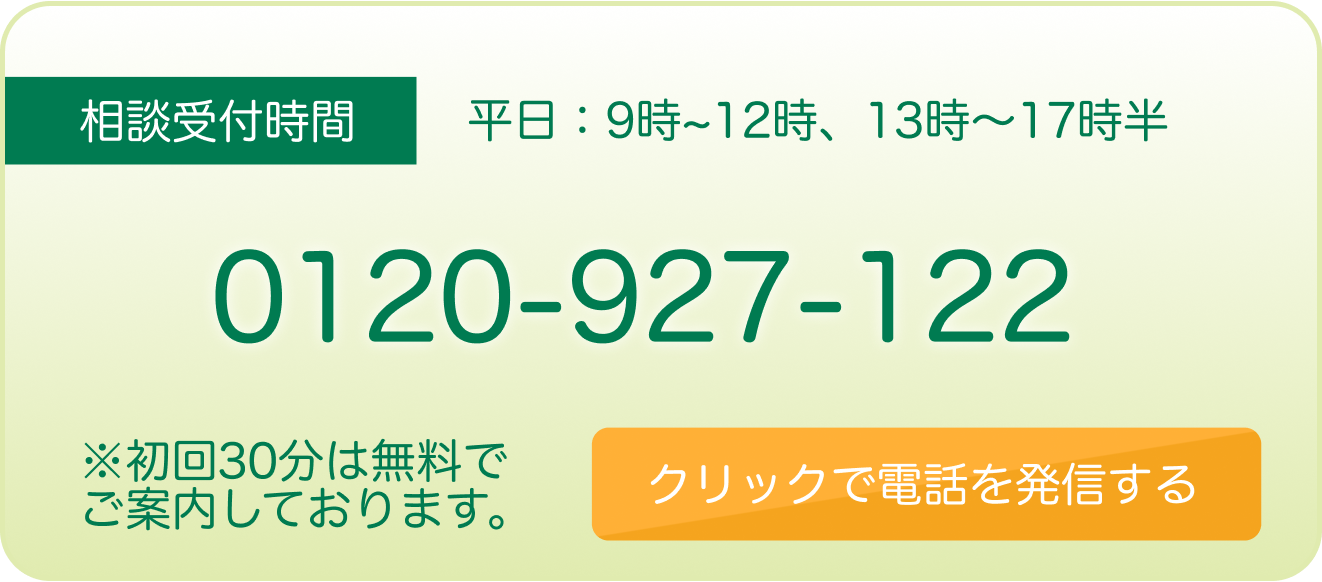
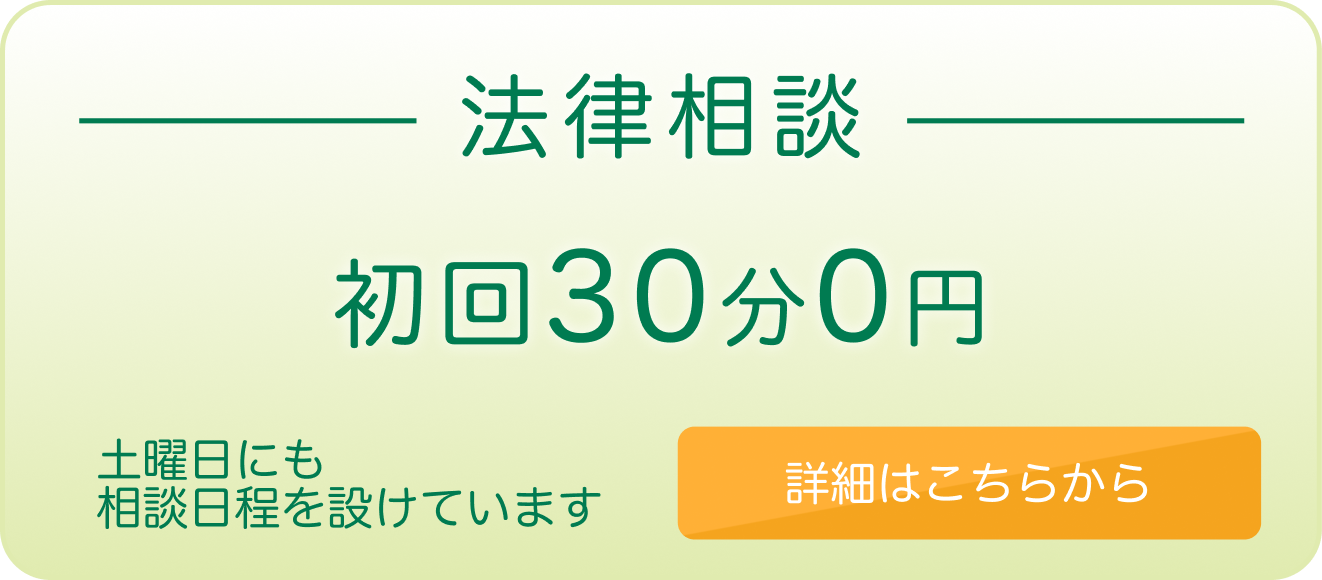
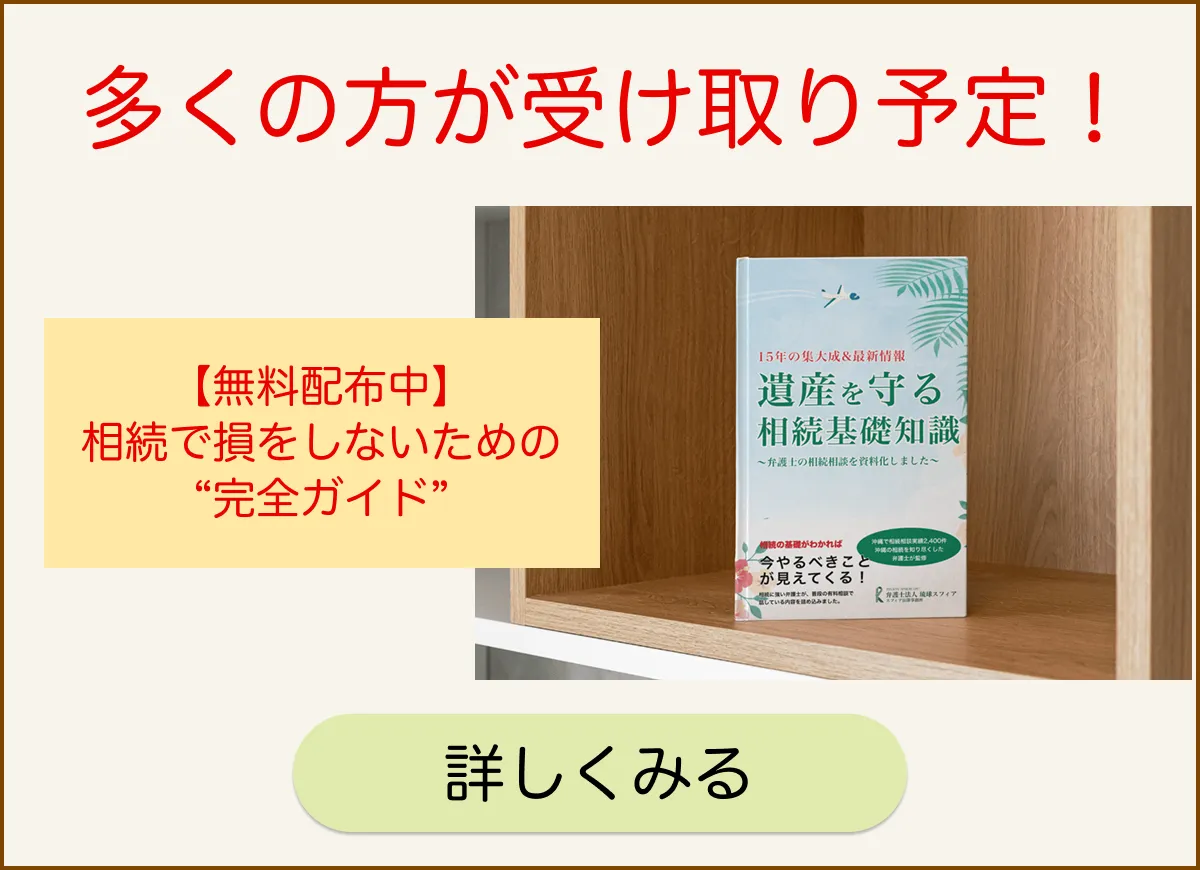
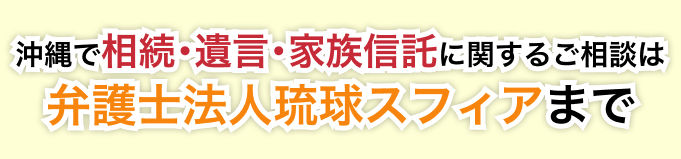

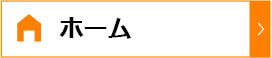
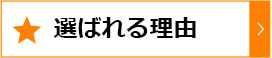
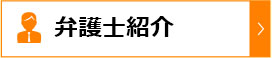
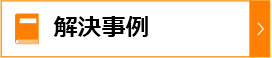
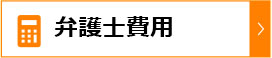
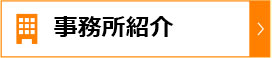

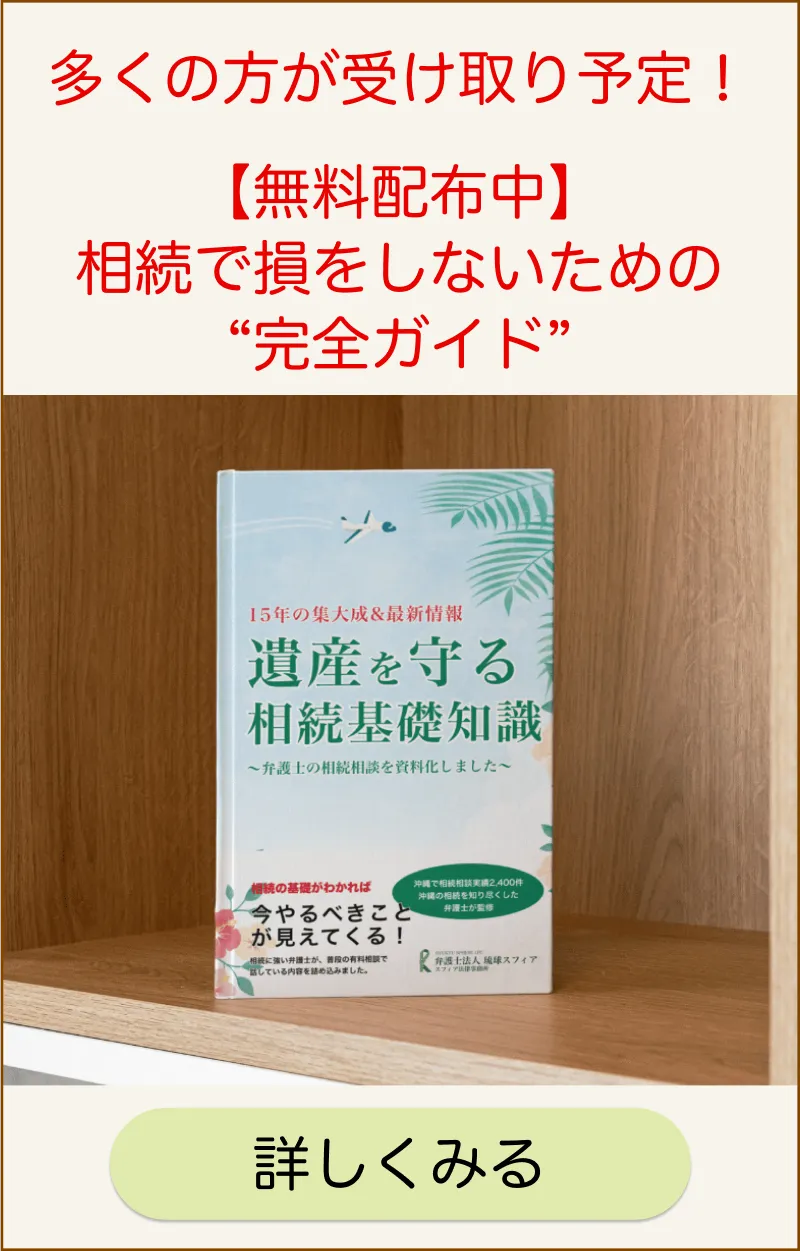

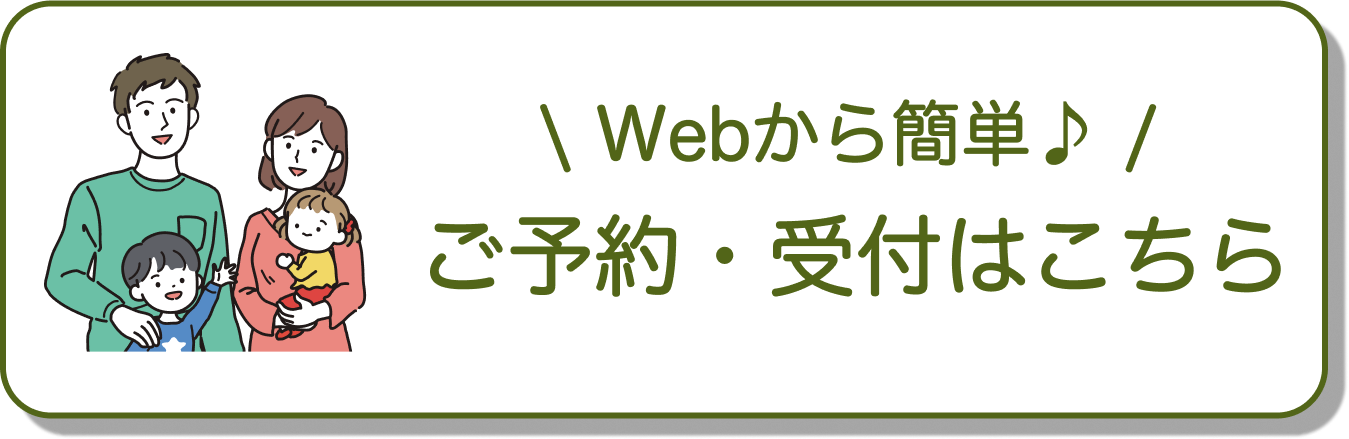


.png)
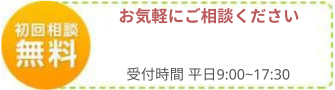
.png)