なぜ遺言書を作った家族が、もめてしまうのか?

初めまして。琉球スフィア代表の久保です。
今日は、遺言についてです。
「遺言書があるから安心だと思っていたのに、結局もめてしまった」
弁護士をしていると、こういう相談を受けることが少なくありません。
僕自身、実際に多くの案件に関わってきて、その理由が見えてきたので、今日はそんな話しをしようと思います。
▼相続の専門家として、遺言書について取材を受けた時の写真

もめる原因①:内容が不公平に見える
遺言書は法的に効力があります。でも、受け取る側の気持ちは別です。
「兄には不動産、妹には現金」という書き方をされると、評価額が同じでも不公平に感じることがあります。
現金はすぐに使える。
不動産は処分しにくい。
同じ金額でも価値の受け止め方は違います。
本人にとっては合理的でも、相続人の立場からすると「不平等」に見える。
ここから感情的な対立が始まります。
もめる原因②:書き方があいまいである
遺言書には「誰に」「どの財産を」「どの割合で」という明確さが必要です。
ところが、実際にはあいまいな表現が多い。
「長男に不動産を相続させる」
こう書かれていても、どの不動産か分からないことがあります。
「次女に預金を与える」
預金といっても口座はいくつもある。どの口座か分からない。
遺言書の表現があいまいだと、結局は相続人同士で解釈をめぐった争いになります。
もめる原因③:財産の全体像が書かれていない
遺言書で一部の財産しか、触れられていないこともあります。
例えば「自宅は妻に」と書かれていても、預金や他の不動産は書かれていない。
この場合、残りの財産は遺産分割協議が必要になります。
つまり、遺言書があっても協議を避けられないのです。
「遺言書があるから安心だと思っていたのに、結局話し合いになった」
これがトラブルの原因になることは珍しくありません。
もめる原因④:お金のことになると人が変わる
遺言書があれば、法的には分配が決まります。
でも、人の気持ちは法律だけでは割り切れません。
「父は兄ばかり優遇していた」
「母は私のことを分かっていなかった」
そうした思いが、相続の場で一気に噴き出します。
感情的な対立があると、遺言書があってもスムーズにはいきません。
僕は調停の場で、実際にそういう空気を何度も経験しました。
法律上は決まっているのに、納得できないから争いになる。
これが相続の難しさです。
もめる原因⑤:遺留分の問題
民法には「遺留分」という仕組みがあります。
一定の相続人には、最低限の取り分が保障されている。
例えば「全財産を長男に相続させる」という遺言書を書いたとしても、他の相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
この制度がある以上、極端に偏った遺言書は、ほぼ確実に争いを生みます。
「遺言書があるから大丈夫」と思っても、遺留分の問題が残る限り安心はできません。
僕が学んだこと
遺言書は確かに重要です。
ただ、それだけで相続トラブルが防げるわけではありません。
・内容が不公平に見える。
・書き方があいまい。
・財産の一部しか触れていない。
・感情が整理されない。
・遺留分の制度がある。
こうした要因がある限り、遺言書があっても揉め事は起きます。
僕は弁護士として、この現実を何度も見てきました。
それでも遺言書は必要
誤解してほしくないのは、「遺言書は意味がない」という話ではありません。
むしろ遺言書はあった方がいい。
ただし、作り方と使い方が重要です。
⚠️財産を漏れなく書く。
⚠️あいまいな表現を避ける。
⚠️遺留分に配慮する。
⚠️そして、相続人の気持ちも考える。
ここまでやって初めて、遺言書は争いを減らす役割を果たします。
遺言は、数百万から数千万単位の財産をスムーズに守るツール
遺言書を正しく作り、相続トラブルを防ぐことは、経済的にも大きな意味があります。
揉めれば時間がかかります。
調停や審判に進めば、数年単位で財産が動かないこともあります。
その間に不動産の価値が下がることもある。
現金も引き出せない。
逆に、遺言書と正しい手続きを組み合わせれば、数百万から数千万単位の財産をスムーズに守ることができます。
僕が担当した案件でも、遺言書の有無で依頼者の取り分が大きく変わった例がありました。
結局のところ、遺言書は「感情を整理するため」だけでなく「資産を守るため」のツールでもあるのです。
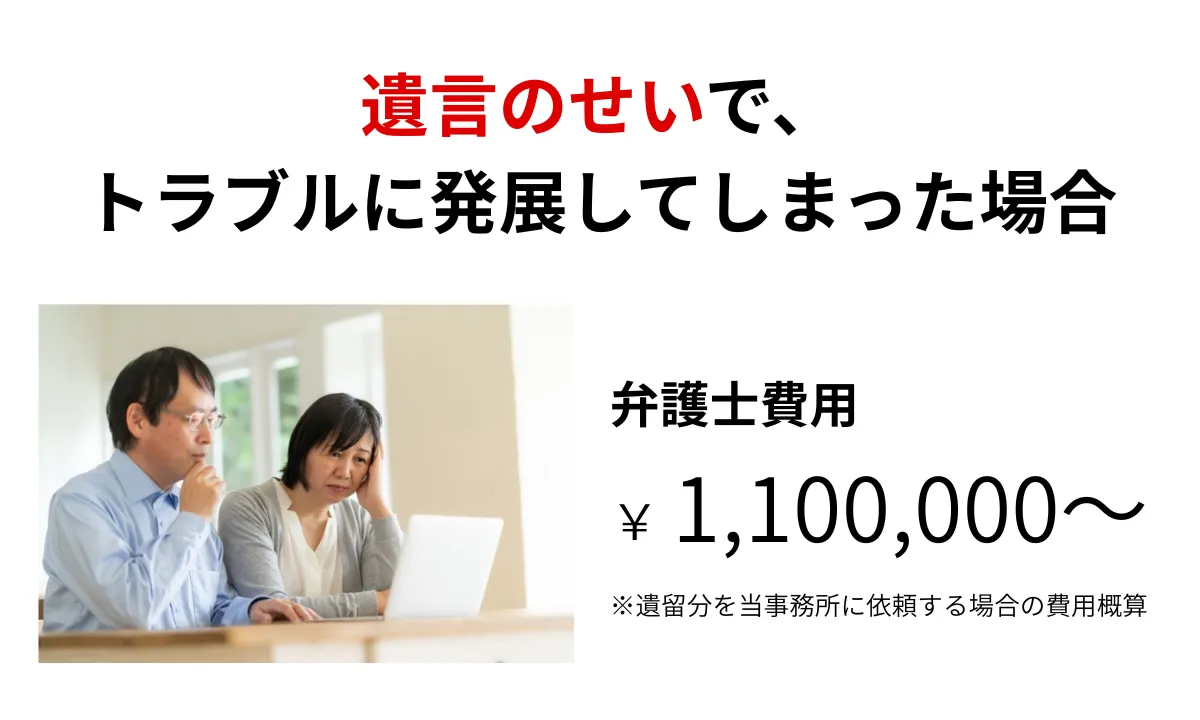

事務所の実績などに関して
琉球スフィア法律事務所は、沖縄県で弁護士数ナンバーワンの規模を持っています。
相続相談は 2,400件以上。
代理人として関わった案件で、1年間に依頼者へ取り戻した金額は 1億円以上 に達しました。
遺言書の作成から相続手続きまで、一貫してサポートしています。
沖縄特有の不動産事情にも対応できるのが強みです。
新規相談を再開しています(無料)
料金は「無料」です。
僕は正直、かなりお得だと思っています。
無料相談で分かることは、例えば次のようなことです。
・遺言書をどう作れば争いを減らせるのか
・遺留分を請求されたときにどう対応すべきか
・不動産の分け方をどうすれば公平にできるか
・遺言書があっても揉めたとき、どんな手段があるのか
もちろん、相談しただけで全てが解決するわけではありません。
時間がかかるケースもあります。
再現性も100%ではありません。
それでも、次にやるべきことが見えるだけで、状況は大きく変わります。
僕はこれまでの経験から、無料相談をきっかけに数百万、数千万単位の財産を守った依頼者を何人も見てきました。
まとめ
遺言書があっても、相続トラブルは起きます。
不公平に見える内容。
あいまいな表現。
財産の漏れ。
感情の対立。
遺留分の問題。
こうした要素が重なると、遺言書だけでは不十分です。
だからこそ、正しい作り方と専門家のサポートが必要です。
それは感情を整理するだけでなく、経済的に大きな利益を守ることにもつながります。
琉球スフィア法律事務所は、これまで2,400件以上の相続を扱い、年間で1億円以上の財産を依頼者に取り戻してきました。
もし「遺言書があっても不安だ」と感じているなら、まずは無料相談を使ってみてください。
大切な財産を守るために。
ここで動けば、きっと損はしません。

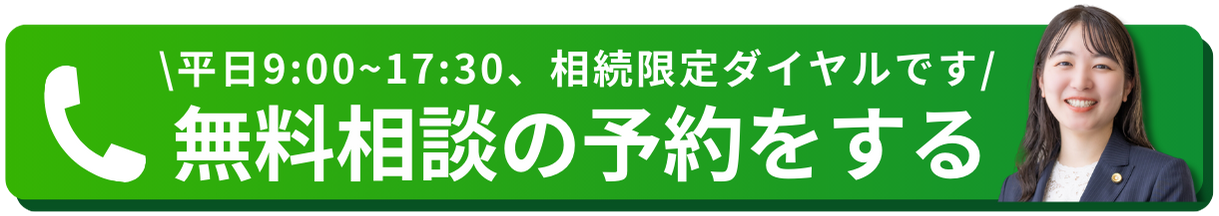
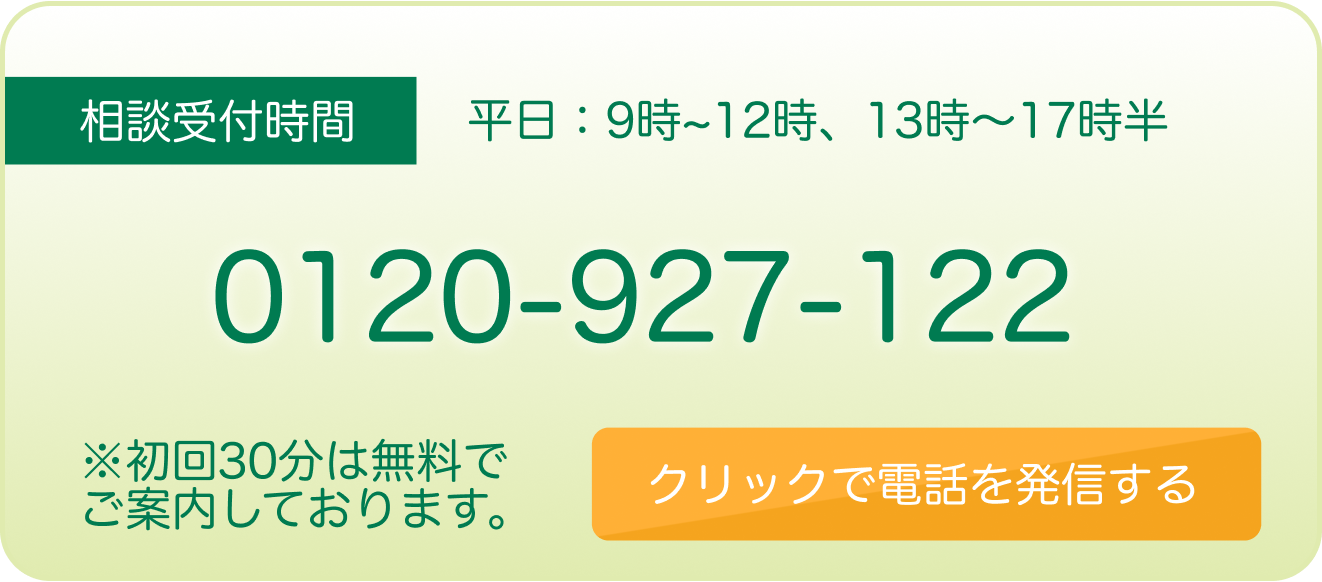
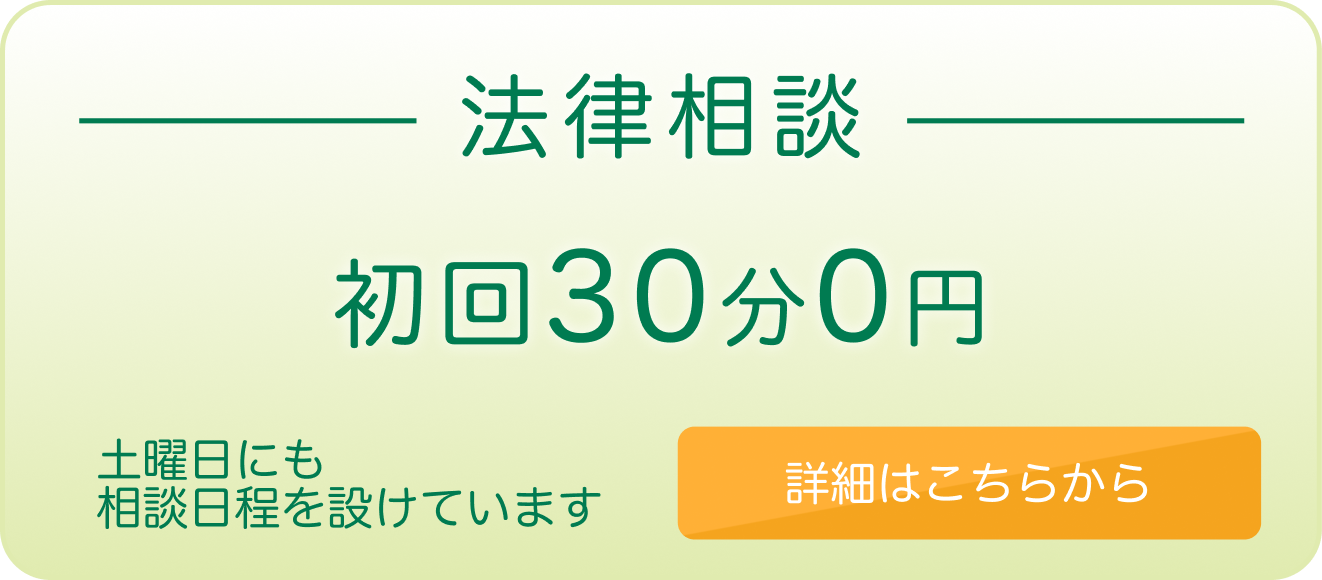
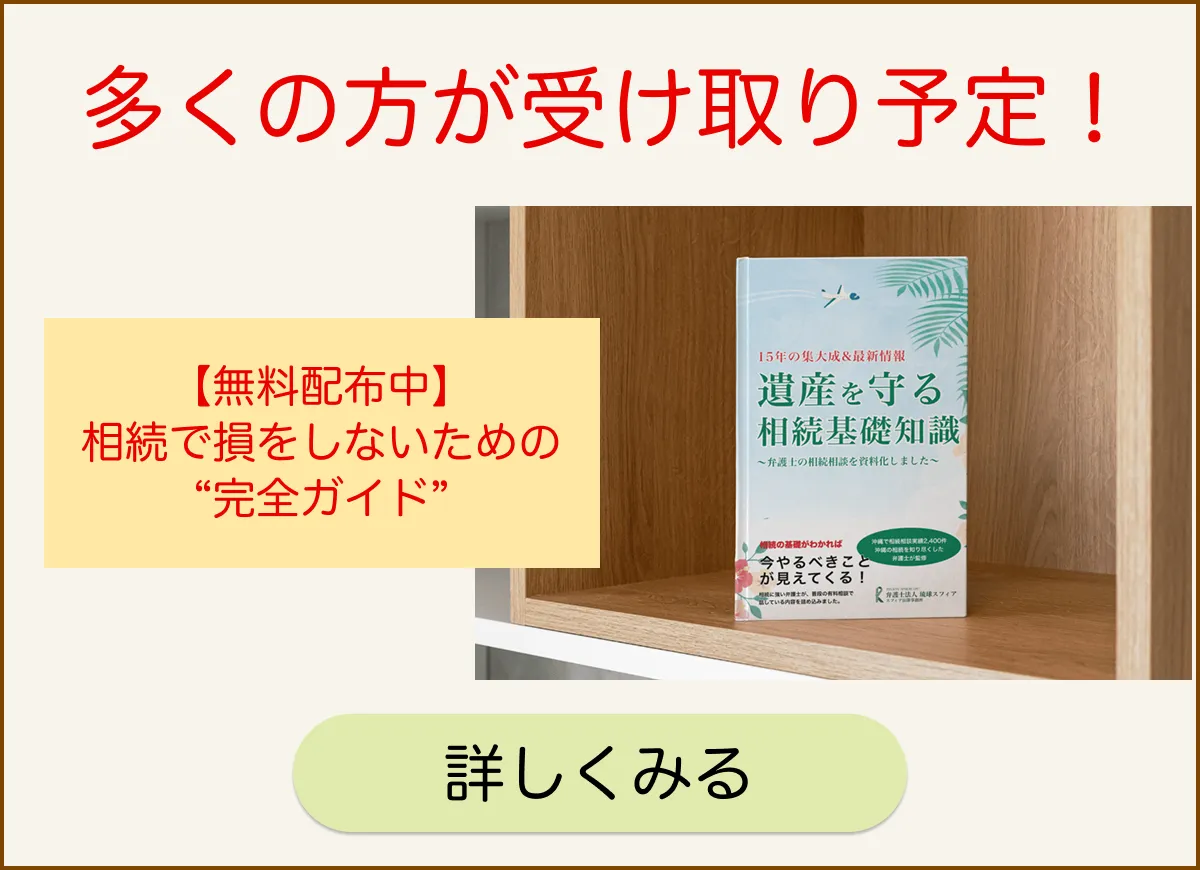
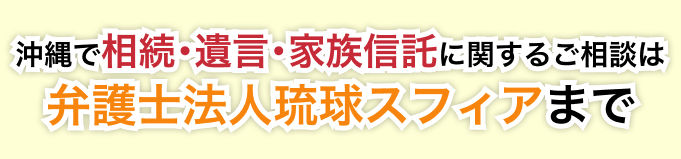

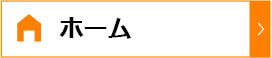
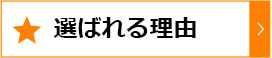
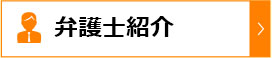
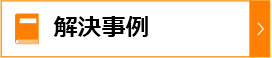
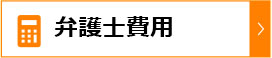
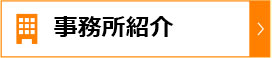

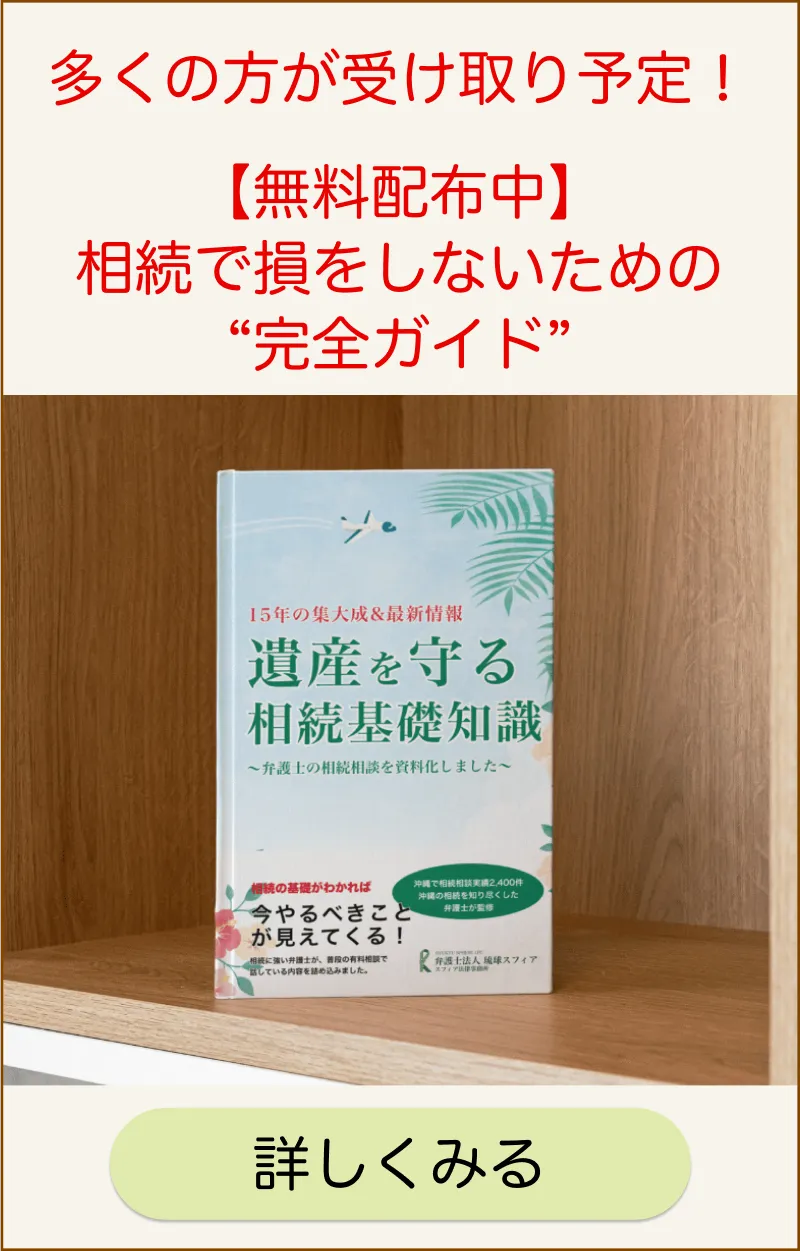

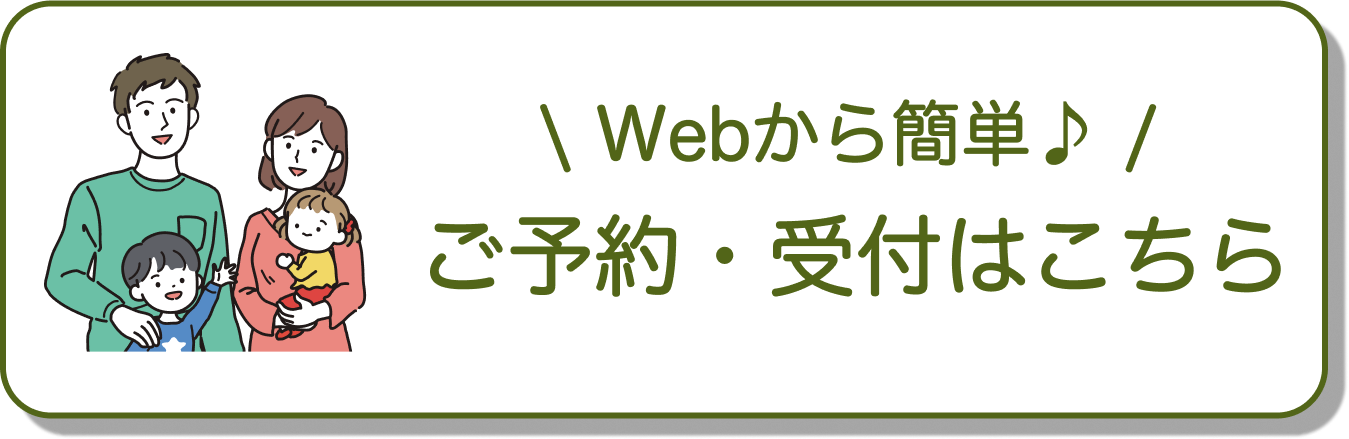


.png)
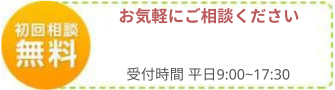
.png)